© 表現未満、webマガジン All rights reserved.

「共振」に目覚めるアートプロジェクトとして
text:影山 裕樹
ローカルアクティビストの小松理虔さんに誘われて、浜松のクリエイティブサポートレッツに滞在する機会をいただいた。小松さんと出会ったのは、2012年ごろ、小松さんが地元いわきで立ち上げたオルタナティブスペースUDOK.を訪ねていった頃だ。その当時、アサヒアートフェスティバル(AAF)10周年本の編集に携わっていた僕は、AAFのメンバーとともにいわきに訪れたのだった。
小松さんとはその後、全国各地の大人になってまで秘密基地を作ってしまった人々を取り上げた『大人が作る秘密基地』(DU BOOKS)、全国各地のローカルメディアの作り手に寄稿をお願いした『ローカルメディアの仕事術』(学芸出版社)で一緒に仕事をした。
折を見てイベントに登壇してもらったり、弊社で企画制作を行なっているウェブマガジン「EDIT LOCAL」に寄稿してもらったりもしていた。しかし、一泊二日でがっつりと、しかもレッツで一緒に滞在して酒を飲み交わす時間は初めてだったのでいろんな話をした。

そもそも、AAF10周年本は2013年に『地域を変えるソフトパワー』(青幻舎)として出版されており、そのなかの事例の一つとして取り上げたのがレッツだった。奇妙な縁というか、僕自身、ずっと来たかったレッツに小松さんから呼んでいただけたのは大変嬉しかったし、滞在してみて、レッツという場の持つ力や可能性にこれまで以上に関心を抱くことになった。
レッツが提示する「表現未満、」という言葉は、とてもクリティカルだと思う。人間は生きているだけで何かしらの表現をしている。人に何かを伝えたいときに、人は表現するのだと思う。では表現未満、とはなんだろう。呼吸したり、水を飲んだり眠ったり、生命を維持する活動そのものと、人に何かを「伝えたい」という想いの“間”にあるもの。小松さんの言葉を借りれば、「関係性を構築するための言葉」。それが「表現未満、」というコンセプトに現れているのではないか。
人に何かを伝えたいという想いを昇華したものは「作品」と呼ばれる。そして作品は作者と鑑賞者の対話や交渉のツールとして十全に機能するものでなくてはならない。プロの作家が作った「作品」とは違う、という意味で「作品未満、」だったらしっくりきていたのに、と思う。レッツに日々訪れる利用者や職員、よそものである僕や小松さんのような人々が「伝えたいと思っても伝えきれないギリギリの想い」は、作品というかたちに昇華される前の「表現」であり、あるいは「表現未満、」なのかもしれない、そのことをレッツのみなさんは伝えたいのかもしれない、と深読みさえしてしまった。

これまで、全国を回って様々な福祉施設に訪れる機会はあった。近年は福岡の「よりあい」や神戸の「はっぴーの家」に訪れた時に衝撃を受けた。そんな時、いつも、フランスのラ・ボルド病院のジャン・ウリ氏の言葉が頭によぎる。
ラ・ボルド病院は、思想家のフェリックス・ガタリが勤めていたことでも知られる古城を改装したクリニックである。年に一度、患者とスタッフが共同で行なう演劇祭を追った、ニコラ・フィリベール監督のドキュメンタリー映画『全ての些細な事柄』(1996)の舞台にもなっている。
そんなラ・ボルドに実に6年に渡り通い、写真集『ソローニュの森』(医学書院)を出版した田村尚子さんから、現在は亡くなっているジャン・ウリ氏について話を伺っていたこともあって、日本語で翻訳されている数少ない文章を読んだことがあった。
「私は生物学的に見て、創造は一種の生命の防衛だと考える。代償作用とでも言ったらいいか、世界の再構築の試みのようなもの……」「錯乱自体が生産的なのである……それは審美的“意欲”とでも言うべきものだ」(共に『ドゥルーズとガタリ 交差的評伝』(フランソワ・ドス著、河出書房新社)。ウリ氏にとっては、患者は理解不能な他者なのではなく、彼らの「精神の冒険」は寄り添うことが可能な、創造的な行為なのだという。
たとえばアウトサイダー・アートが観る者の心を捉えるのは、表面的な抽象性よりも、内的な必然性に貫かれた表現であるからだ。ヘンリー・ダーガーの不可解極まりない世界観への執拗なこだわりは鑑賞者に謎を残すけれども、それらは、あらゆる美的な相貌を備えた美術作品よりもずっと「内的に厳密」なのだと思う。およそ「作品」と呼ばれるものは、鑑賞者に向けて放たれるものではなく、自らの内的必然性において厳格であるべきなのではないだろうか。確かにそれは、人に何かを「伝えたい」という思いより優先される何かだろう。それこそが作品未満、どころか、表現未満、な営みなのだと僕は思う。
一日目は「たけし文化センター」でたけしくんに会い、黄色いガムテープをあらゆるものにぐるぐる巻きにして「これ持って帰る」と言い続ける舞さんとの時間を過ごした。一日目の夜は小松さんたちと夜の浜松を少しだけ開拓して、翌日は入野にある「のヴァ公民館」へと移動。そこで出会ったのが電子機器が大のお気に入りのオガちゃんだ。
人差し指を突き出して「ドーン!」とまるで笑ゥせぇるすまんのようなコミュニケーションで一通り盛り上がり、木造のカートのリビルド工作に飽きた頃に、散歩に同行することになった。どうやら、一緒に散歩に付き合ってくれた水越さんからすると、大通りを左に曲がると「詰み」なのだそう。オガちゃんは電気店に一度訪れると、気に入った商品を買ってもらうまで絶対にそこを離れなくなってしまうそうなのだ。小松さんが以前滞在した時は、ゲームセンターに入り浸り、延々とそこを離れなくて大変だったそうだ。そこで、今日は大通りを右に曲がり、オートバックスに入ってカーナビを見て遊ぶことにした。


一通りカーナビのスピーカーの音源に興奮してそこを後にするのだが、オガちゃんはずっと大通りの先にある電気店を捉えていた。水越さんや小松さんが言うことも聞かず、CDを200枚くらい入れた重いリュックを背負っていちもくさんに電気店へ向かう。その足取りに、僕たちのあいだで緊張感が走った。
なにより、さっきまで割れんばかりの笑顔でシンセをかき鳴らしていたオガちゃんの顔が険しい。一日の間で普通、人が味わう感情の起伏のピークを超えているくらい、さっきと正反対なくらい落ち込んで機嫌が悪くなっている。顔を見るだけで、やりたいことがやれない彼の気持ちが痛いほど伝わってくる。


そこで僕たちは、さっきオートバックスで見た、売れ残りのケータイスピーカーを買おうという提案をした。でも、つまらないものを買おうという雰囲気を出してはいけない。さっきドリルで補強した木製カートに積んで、音楽を鳴らしてまちを闊歩したら楽しいよ、あれ300円は安すぎるよ、ちょっと買いに行こうよ! という提案で臨んだ。
そしたら顔の表情が一気に戻って、「買っちゃう?」とご機嫌になってくれた。10キロくらいあるリュックを背負ってオートバックスに戻るオガちゃんと同行者一行。帰り際、僕や小松さんに、「疲れた?」と尋ねてくれる。ああ、こうやって気を使ってくれているんだな、と嬉しい気持ちになる。
オートバックスに戻ってからも1、2時間、一悶着はあったのだが、無事300円のスピーカーを買って散歩から帰ることができた。思いの外スピーカーの性能が良くて、僕も一個買ってしまったくらいだった。秋の夜長に河川敷でこれを使って路上呑みでもしようと思う。
もともと、僕自身、自閉症の傾向が昔からあり、一つのことに集中すると他のことができなかったり(マルチタスク不可なので企業勤めに向いていない)、他者を慮ったりできなくなってしまう。それがいろんな人との軋轢につながってしまい、「なんだか生きづらい世の中だなぁ」と適当に社会のせいにしてバランスを取ってきた。だからこそ、一つのことに集中して他の瑣末なことに関心を持てない彼の気持ちがとてもよくわかる。
他者の内的な精神の冒険に寄り添うことができたとき、涙が出そうになるくらい、“それ”は“自分”に似ていると感じる瞬間が誰しもあると思う。共感という生易しいものではない。それはある種の電撃が走るようなもので、自分自身の存在が危ぶまれるような危機感に苛まれる瞬間だ。それは、「共振」とでも呼べるものかもしれない。
障害者、高齢者、外国人といったように、社会包摂の議論をするときに、どうしても僕たちは健常者や日本人という立場から、彼らを境界線の向こう側に追いやって「対象化」しようとする。この構図は、残念なことにアート業界にもある。「作品」という扱いやすいツールが表現者―鑑賞者という構図を固定化してしまうのだ。
「神経症や精神病というのは、生の移行ではなく、プロセスが遮断され、妨げられ、塞がれてしまったときに人が陥る状態である。……それゆえ、そのような存在としての作家は病人ではなくむしろ医者、自分自身と世界にとっての医者である」『批評と臨床』(ジル・ドゥルーズ著、河出書房新社)
この感情のプロセスの遮断こそが、健常者―障害者の区別なく、我々ひとり一人の人間にとって一番ストレスに感じるポイントだ。そして、大勢が取るしぐさに反して、自分の内的必然性を裏切ることができず、自らの感情を優先してしまうことが、自閉症的傾向を持つ僕自身にも多分にある。
しかしそうした社会における異物性こそが、空気を読みあう社会の構成員の中で特殊性を発揮し、ある種の「医者」としての役割を発揮できる、と思っている。ディスアビリティではなくアドバンテージになる瞬間が10回のうち3回くらいある、というソロバンを日々はじくことこそが、なにより僕らのような人間の生存戦略なのだ。
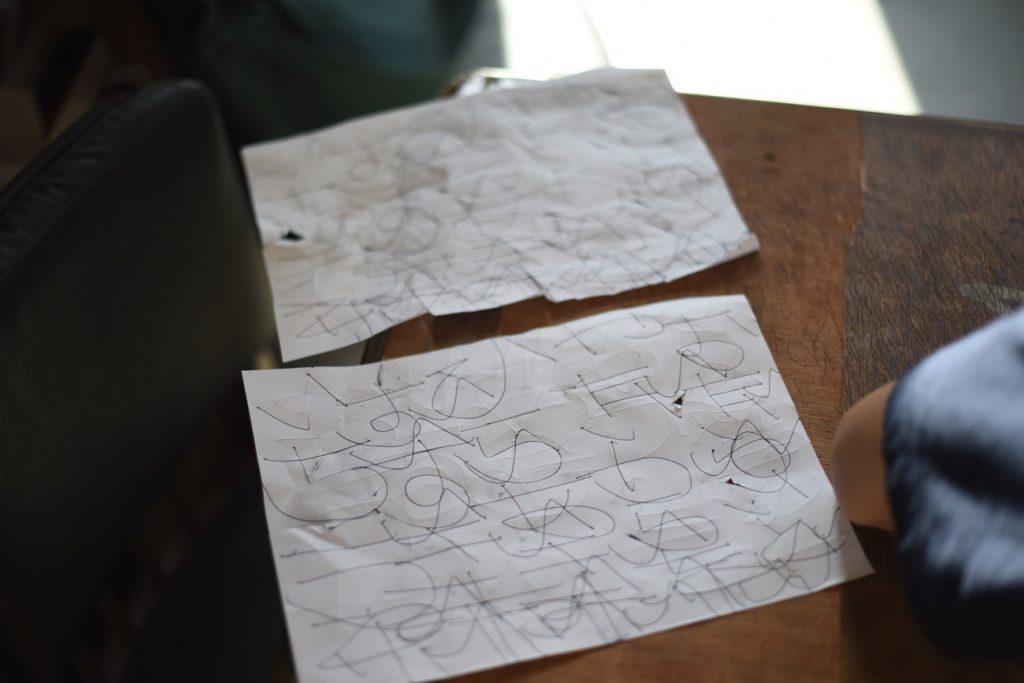
ある意味、誰も手を出さない「秘密基地」だとか「ローカルメディア」だとか、多くの人が注目しないところをじっくり集中して掘り続けていくことで今の社会の停滞している部分を破裂させていく編集の仕事が、だから小気味よくて自分には相性がいいのかもしれない。
はたまた、こんな議論もある。人間は、約束をする動物だ、といったのはニーチェだったか。とはいえ、約束を破る人間はゴマンといる。人間と動物の間に、程度の差こそあれ、本質的な差はない。そこにはグラデーションがあるだけだ。人間と動物の違いを「言語」だとか言っていても、いずれイルカが話す言語が体系的に研究されればその差はたいした問題ではなくなる。
僕たちは、常に他者との間に境界線を引きたがる。境界線の上にはともすると「作品」が鎮座する。プロの作家と素人の鑑賞者の間に。アイドルとファンの間に。境界線の向こう側とこちら側で、それぞれが作品を受容する側と提供する側で分かれなければならない理由はどこにあるのだろう。ある種の差別構造が、こうした些細な場所から生まれるのかもしれない。
なぜ、人は自分と他人を別の存在と分けて考えたいのだろう。もちろん分けるのは構わない。違いはもちろんある。これは政治の話でも一緒で、原発賛成か反対かで自分と他人の間に境界線を引きたがる人がゴマンといる。そうじゃない。これは小松さんが言う「共事」と近いかもしれない。境界線を取り払い、同じ場所に立って「共振」し、まだ見ぬ未来をともに開拓しようと一歩歩み出すこと。
いま、ここにあるのはただ一つの生命だけだと考えてみるといい。凶悪な犯罪者の死ぬ間際の病窓に立って、彼と自分との違いを語る意味は果たしてどれくらいあるだろう? 公園の片隅で震えている野良猫に餌をあげながら、彼と自分の違いを語ることにどれほどの意味があるだろう。恋人に逃げられ、仕事を失い、家族から勘当され、信頼していた友人から裏切られている自分に比べたら、野良猫のほうがずっと良識があり実直な猫生を歩んでいるかもしれないだろう?
僕たちは同じ空間に生き、同じひとつの生命として、呼吸し、水を飲み、時を重ねるだけだ。そこに違いなんてない。先に述べたように、共感では生易しい「共振」の電撃が、自らの存在を脅かすほどの威力を発揮するのはこの瞬間だ。年を重ねる中で培われた社会的属性が裸にされる瞬間。自分がただ生きているだけの存在だと知らしめられる瞬間。
僕がこの問いを投げかけるのも、「作品」というメディアを通して作家と鑑賞者(批評家)が向き合う構図を棄却し、ともに境界線の内側に立ち、共創するアートプロジェクトを奨励したいと考えているからでもある。まぎれもなく、レッツが取り組む「表現未満、」プロジェクトの射程はここにあると思う。結果ではなく、日々のプロセスに創造的な営みが詰まっている。毎日毎日の他者との出会いが、常に出会い直され、経験として蓄積されていく。そうした創造的な社会彫刻こそが、現代アートの可能性の中心である。間違っても、権威に認められるポジションを確保することがアートのゴールでは決してない。


だから「表現未満、」に向き合う時に求められるのは、ただ、一緒にいることだ。目的なき行為なのだから、それを鑑賞する、あるいは体験する、目撃する人も目的を持ってはいけない。ただ、一緒にいて、面白がってみればいい。面白い、というポジティブな意味が含まれることで、その行為は「面白いもの」として社会に漏れ出し、そこに関わってくれる人を作りだす。――小松理虔
どんなアート作品を鑑賞するよりも、レッツが取り組んでいる「タイムトラベル100時間ツアー」に参加した方が、人生の価値観を変える特別な体験ができることだろう。高尚な、難解なレトリックを解読できるエリートたちのためだったアートを、境界線のこちら側に取り戻していこう。不可解なこと、自分と一見違う他者との共通点を探り、「共振」することこそが、分断されたこの社会を没落から救う唯一の模範解答だ。
生命維持のための活動と、他者に想いを伝える表現の間で。「表現未満、」のグラデーションをくまなく記述し、他者理解のリテラシーを上げていくことこそが、アートが持つ本来の価値を発動させるのだと思う。そんなアートプロジェクトの価値をこの日本社会に実装させていく手立てを編み出していきたいと思った滞在だった。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

Disability and Welfare as Personal Experiences
I’m exploring LET’S again for the first time in a while, continuing t…








この記事へのコメントはありません。