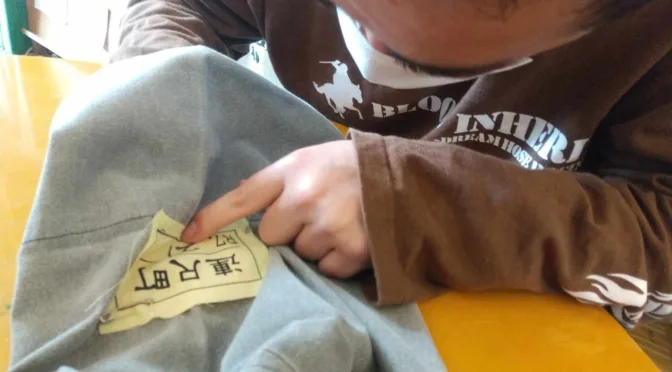![《寄稿》伊藤亜紗さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/48da1e8ea2454f7761e591f75106b6fe-scaled.webp)
《寄稿》伊藤亜紗さん [ひとインれじでんす2024]
レッツ滞在記
文:伊藤亜紗
2024年11月8日―9日、一泊二日でレッツに滞在させていただいた。正直、そのときのことを文章にするのはとても気が重い。ふだん、いかに言葉にすがって生きているか。そのことを思い知らされたからだ。言葉という病にかかっている?なんだか、自分がとても臆病に感じた。この病から一刻も早く離れないとまずいなと危機感すら持ったのだけど、その経験を記録に残すために言葉に頼らざるを得ない。矛盾している。
1日目のお昼過ぎ、2階でりょうがさんがマイクを持って歌い始めた。曲はアンパンマンのマーチ。「何のために生まれて 何をして生きるのか 答えられないなんて…」聞き覚えのある歌詞が、波間に見え隠れする岩肌みたいに、聞こえたり聞こえなかったりする。ポロンポロンとギターを弾きながら、背中で応える佐藤さん。と、りょうがさんがシャウト「うーぱんで!」を発し(元歌詞の「そんなのは嫌だ!」)、これに番頭さん(みたいにみんなを見渡す机に座っていたるうなさん)がにやにや〜と笑いながら長いリボンがついた棒で太鼓をダンダンダンとたたいて応る。その絶妙のタイミングに驚いていると、りょうがさんがもう一度「うーぱんで!」と叫び、再び番頭さんによる太鼓のレスポンス、しかしりょうがさんのダメ押し3回目「うーぱんで!」では番頭さんスルー、何事もなかったように
叫びが波間に消えていく。その間、たけしくんはちぎったチラシの山をかき分けながら、何が起こるんだろうと期待するような様子で佐藤さんの近くで耳を傾けている。床にしゃがみ、大福のように柔らかい体をヘッドバンギングするように繰り返し折り曲げるさとみさん。Tさんは配達員のようにフロアのあっちとこっちを嬉しそうに往復している。
奇跡のようなセッションだった。どこまでが音楽でどこまでが生活なのか分からない空間で、体の動きや、表情や、チラシや、床や、となりの家の騒音が、いろんなリズムで呼応しあっていた。レッツは「ひとりひとりの利用者さんが自分のこだわりを思う存分表現している場所」というイメージが強かったから、こんなふうに、利用者さんのあいだに張り巡らされた繊細な関係を目撃することになるとは思っていなかった。もちろん、それは一般的にいう「人間関係」とは少し違う。「私とあなたはいまコミュニケーションをしています」という同意がないままコミュニケーションが続く感じというか、電話をかけないで電話をする感じというか。うまく言えないのだけど、要するに、関わりのON/OFFがないがゆえに、結果的にバラバラであるからこそずっとつながっているような印象を受けた。
なぜそんなことが可能なのか。二日間ではなぞは解けなかったけれど、面白かったのは、スタッフさんたちの感覚である。私に3階の宿泊設備を案内しているあいだ、スタッフさんたちは、足元から聞こえる音を手がかりに、一階下の2階にいる利用者さんが今何をしているのかについて話していた。つまり、3階にいながら2階をケアしているのである。普通、3階にいると2階の存在は意識から消え、関わりはOFFになってしまうものだと思うが、スタッフさんたちはそうではない。鍋を火にかけた状態でベランダで洗濯物を干しているような感覚だろうか?もしかしたら、ケアの仕事のプロならではのこうした「OFFにしない感覚」が、利用者さんたちにも伝染し、「バラバラでありながら同時にずっとつながっているような関係」を作り出しているのかもしれない。夜、近くのコンビニまで買い物に行った利用者さんも、ずっと、そこにはいないTさんが今何をしているかばかり気にしていた。
言葉は、ON/ OFFを作り出すスイッチなのだと思う。目の前の出来事やものに言葉を与えることで、私たちは、それとの関係をOFFにすることができる。もちろん、OFFが必要な場合もある。謎の不調に苦しんでいる人は、病名が与えられることで病気から距離が取れるようになるかもしれないし、暴力の渦中にいて麻痺してしまっている人は、自分が受けている暴力に名前が与えられることによって、状況を変える力を得ることができるようになるかもしれない。でも、あまりに言葉に依存しすぎてしまうと、世界が制御可能なシステムのようなものでできていると勘違いしてしまう。先が読めない状況や整理がつかない状況を前にして「言葉を失う」という言い方がなされるが、これはOFFにできない、渦中から抜けないでそこにいる、ということだ。
ちなみに、2日目のトークイベントでのスタッフさんの話によれば、りょうがさんが歌を歌うのは、うんちを降ろすための儀式みたいなものかもしれないとのことだった。かなり早い段階からうんちの気配を感じることができるりょうがさんは、歌を歌いながら、排便のタイミングが来るのを待っている。りょうがさんは、「うーぱんで!」と叫んで番頭さんをけしかけながら、うんちの生成という体の中の出来事からも、自分をOFFしていなかったということだ。しかもその出来事を「うんちをする」と言葉で名付けてしまうのがまた罠で、本来ならそれに伴うはずの身体的快感から、私たちは自分の体を切り離してしまっている。目の前で起こっていることに言葉を与えて安心したいという誘惑と、それによっては何にも出会うことができないだろうという焦り。東京に帰ってからも、その余韻にしばらく取り憑かれていた。