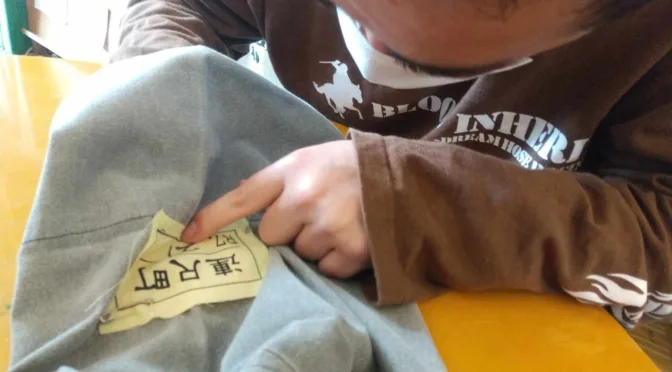![《寄稿》第9回 ゲスト:青田元さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/169A3257-scaled.webp)
《寄稿》第9回 ゲスト:青田元さん [ひとインれじでんす2024]
※本文は青田氏のnote(ノート)記事を、ご本人に許可をとって転載しています。
元記事はコチラ→https://note.com/jimaota/n/n29bacff7eda4
ひとインれじんでんすに参加して。
文=青田元
私が小学生のとき、クラスメイトに「Fちゃん」という子がいた。
当時、学校の中に養護学級というクラスもあって、Fちゃんはそこにいくオプションもあったけど、僕らと一緒に同じクラスルームで、同じ日常を過ごしていた。
通学も一緒。給食も一緒。
今回、たけし文化センターで過ごして、最初に思い出したのはFちゃんのことだった。
当時の自分が、なんらかの形で、レッツで時間を過ごした経験があれば、彼女との接し方は違っていたかもしれない。あまりにも自分に理解がなく、あまりにも幼稚だったかもしれない、と。
時間は戻せないので、今思ったことをしっかり記録して、次の時に活かせれば、そう思った。なので、この記録を残そう、と。
自分の中に体験が、ある間に。
■今回のイベント参加について
クリエィティブサポートレッツの活動は、改めて僕が説明する必要もないかな。引用するなら、ここ(https://cslets.net/wp/) かと。
元々、今回のお話をくれたのは、久保田瑛(あき)さん。このNext Local Leadersのイベント(https://forbesjapan.com/articles/detail/52685)審査員を私が務めていて、彼女がピッチする側だった、というのが知り合ったきっかけ。コロナの時期は、なかなか会えなかったけど、また改めて色々な話をしましょう、ということで、今回の「体験滞在」につながっている。
そう考えると、このNext Local Leadersから、伊達くんとか、中谷くんとかと関係が始まったという意味では、感慨深い。
▼ひとインれじでんす
様々な分野の専門家が、レッツの運営するたけし文化センター連尺町やちまた公民館に滞在します。知的障害のある人たちと過ごしたり、スタッフと話してみて、いったい何を思うのでしょうか。文化人類学者なら、劇作家なら、編集者なら、それらの風景はどんな風に見えるでしょうか!?滞在2日目に公開トークもあります。(レッツのチラシから抜粋)
ということで、様々な方々が宿泊し、経験を共有してきた「ひとインれじでんす」のゲスト最終回に招待してもらった。
レッツの活動をもう少し知りたい、という方は、同じnoteのプラットフォーム記事を参考に。
【note】たけしと生活研究会の記事一覧 https://note.com/takekatsu2019/all
私は、今回一緒に散歩の時間を過ごしたササキさんの「ウンチ奇談(https://note.com/takekatsu2019/n/n7b49a96d89fc)」がとてつもなく好きだ。僕らはマイクロバイオームも、腸内環境も、人間の体をまったく理解できていない、と気づかせてくれたEntry。感謝。
個人的には、このWiredの記事(https://x.com/wired_jp/status/1877188675068637461)も、このササキさんのEntryのおかげで、非常に解像度高く読めました。リアル・ファクトフルネス。多謝。
あるいは、Youtubeでも、雰囲気伝わります。
のヴぁてれび https://www.youtube.com/@NovaTVlets
私のバックグラウンドは、他の参加者とはちょっと毛色が違う。
社会学、哲学、文化人類学など、福祉のテーマに少し関わりがある世界に比較すると、「同じ地域」の「グローバル企業(になりたい)」会社のCSOでは、だいぶ距離が、あるなあ、と。当初から持っている差異。
その1:体験滞在の振り返り
いろんな経験をさせてもらったのだけど、ちょっとそれらの気づきを以下の通りまとめてみた。
アクションごとに生じる(受け手の)ルーティーン:
①案外ほったらかしで、観察から入る。
②おかまいなしで、絡まれる、巻き込まれる。
③自分の想像力で相手を理解しようとして、理解した気になる。
④自分の行動が相手に与えるインパクトが皆無ということを認識。
⑤時々なされるフィードバックに喜び、小さい裏切りに愕然とする。
(キャプション:青田の似顔絵を描いてくれているところ。)
上記のルーティーンは、感覚的に5分に1度位発生する。
イベント発生時における確変
散歩、食事、演奏、ダンス、買い物などの、ビッグイベント発生に、適宜参加を問われる。その際に、大きなインシデントを目撃したり、加担したり、傍観したりして、距離感が狭まる。
時々、確変が入ったりする。
キャプション:買い物の帰り道に、確変イベントが発生したところ(終盤)
キャプション:サイズで圧倒してくる書に負けじと歩く散歩チーム(龍雲寺)
その2: トークイベントで話したこと
3Fで一泊させていただき、翌日も施設内で時間を過ごす。土曜日も仕事をしている私としては、かなりのんびりとした土曜日の午前。午後からトークイベント。知り合いの顔もちらほら。ありがたい。
私の話は、自己紹介、体験の気付きの共有、現在の組織の課題、自分の行っている「共創活動」への想い等。
今回のイベント、あるいは福祉と企業という視点での対話項目として、いくつかMemoを残すとすれば、こんなところだろうか。
①一見関係のない人的資本経営と、「共創活動」の関係性
日本の上場企業のCEOは、80%が初めてCEOを務める。ある企業に入社して、のぼりつめてCEOになる。最初にして、最後のCEO経験がほとんど。対して、海外ではプロ経営者と呼ばれるCEO専門職が存在していて、20%しか初めてCEOになる人が生まれない。
F1ドライバーで考えるとわかりやすい。多くの場合、他チームから移籍してくる(=他社のCEO経験者が別の会社のCEOに任命される)。なかなか下のClassからのステップアップは狭き門(=同じ会社の下の役職からCEOに昇進する)。日本の事例は、全ドライバーが、他チームに移籍せず引退、新しい若い世代に総入れ替えするような感じ。
だとすれば、CEOになる人達には、圧倒的な経験をしておく必要がある。そのために、機能で分化された組織で上り詰めるだけではなく、新規事業などで、小さな失敗をする経験、あるいは小さな会社の財務諸表の管理、それに加えて他社と何か一緒に仕事をすることで、「共感性」を身につける必要があると思う。
よく使うけど、「Put her/his shoes on」という共感を身につけるための体験。このために、新規事業開発というフィールドを使うことを最近考え、形にしていきたいと思っているという話。
レッツにいることで同様の経験ができるような気がする。
今の世界は、「感覚知」「身体知」よりも、「論理性」「言語性」が重要視される時代。羽柴秀吉なら、口が達者な私より、敵の侵入に対する感度が高いたけし君を雇うのでは?と。
求められるものが変わってきた世界により、評価される知恵も変わってくる。
②Noと言われるまでやめない企業文化における仕事の進め方
この企業文化に沿った人材が育つ、あるいは仕事の進め方が異なる、というのは、組織で仕事をした人間には理解できると思う。ただ、自分がどういう会社で働いているのか、他社との対話がなかりせば、自分の立ち位置を理解することもままならない。
どのような企業文化であるかによって、仕事の進め方、人材育成の方針は大きく変わる。
私は自分のやっていることが、他社でそのまま通用すると思っていない。いつも、その注釈をつけながら、公共の場所で話すことにしている。
他社と様々な会話をすることで、改めて自分の組織の特徴に気づくことができる。
よくネクタイの例えを出すが、自分で自分のネクタイを選ぶと似たようなデザインと色になる。それは好きな色だから。友人に選んでもらうネクタイは、思いの外、自分がいいと思わないものが選ばれるが、そのネクタイをしているとよく褒められる。それは第三者の視点から見た自分に似合うものだからだ。
福祉の領域で、レッツが進める自由度が高い組織は、必ずしも今の福祉の現場と現実では、マジョリティ側ではなく、異端と受け止められかもしれない。ただ、現場にいる人であればあるほど、この活動に賞賛と拍手を、そしてそこに踏み込めない自分の現状に対するやるせなさを感じることが多いようにも思った。
③組織運営における「評価制度」について
あんまり、この点は深く考えずに発言したのだけど、「職場」である以上、その人のパフォーマンスに対するフィードバック、即ち評価という仕組みが存在している。
常に課題を感じていることだけど、福祉施設で働く方々を評価するというのは、非常に難しいのではないか、と思った(実際には、そんなに大きい課題ではないのかもしれないけど、営利集団の我々にとって、このトピックは大きな課題)。
④課題解決よりも、「課題発見」する力
AIを使っていて思うことだけど、課題を解決するということの一般化がものすごい速度で進んでいる。
どうでもいい課題に気づけるか、しかも、そんなに大仰なものではなく、小さい課題(得てして、課題は小さい、どうでもいいことが多い)を取り上げることができるのか。
連続起業家のけんすうさんが、「めんどくさい」を解消する話をしていて、そこで、Backspace Keyを押すのに、一体年間でどのくらいの距離を小指が移動しているか、定量化して(3km/年)、ソリューションを出した話が面白い。
これこそ、課題を発見する力だと思うし、思いの外、この能力は皆が持っている訳ではない、と思う。
⑤アートの役割とこれから
「何かに新しい気づき」あるいは、代表の翠さんの言葉を使えば「違和感」を独特の形で与えてきた「アート」の役割を、他の方法で提示しようとしているのを目にする機会が増えた(株式会社コテンに代表されるようなSocial Venture、田淵さんのZebra企業など)。
社会に対してアートが提示してきた方法論は、企業というフィールドでも有効なのではないか、と思う部分も対話した。
反対に、実行フェイズまでもアートが担当しなければ、不十分な方法論と感じる人も出てくるかもしれない。
例えば、かしだしたけし(https://kubotamidori.hamazo.tv/e8596509.html)は企業内でも機能するようにも思うし、企業の研修として、レッツを活用することも想定できる。
違和感を与えること、下の⑦にも通じるけど、企業内の弱い部分の気づきになれば、と思うところもあり。
⑥Win/Winと、ゼロサムゲーム
共創活動は、お互いにメリットがないと続かない。
これをWin/Winの関係と置き換えても良い。特に企業が行うジョイントベンチャーなど、この権化。
一方で、夫婦の子育ては、何故か、Win/Winとは言わない。なんとなく、共通のパイを取り合うゼロサムゲーム、2人の間に引かれる役割分担の線の位置を、どれだけ自分に寄せれるか、ここの議論をしているように思う。
今後は、ビジネスの世界で行われている「成長に基づいて得られた利益を分担し合う」文脈で語られることを福祉や、子育てというような家庭生活に下せないだろうか。
あるいは、成長しない世界でも、Win/Winの関係を話し合う方向性の議論、もしくは、全く別の視点で家庭というものを再定義する(コミュニティでの子育て)等、可処分時間の再配分など、選択肢は色々とあると思った。
https://x.gd/Porul がヒントになれば、と。
⑦組織の中で、「弱さ」「できなさ」を認める意義、その仕組
これは難しい判断かもしれないが、案外面白いと思った気づき。
企業はこれまで、マッチョで、明晰で、自分自身の犠牲を厭わない人になれ、と言われて人材育成をしてきた。いわば、会社にとって都合のいい人材。少し高い報酬だったり、出世だったり、研修だったり。
でも、価値観の変化で、管理職になりたくない、という人も出てきている。
本来、組織が持っている力を最大化しようとすれば、弱い部分、できないこと、を褒め称える文化を醸成し、全体の力を結集できれば、強い組織になり得るのではないか。
その弱さを認める作業に、翠さんの言う、障がいのある方々が普通にフロアにいる違和感、そこから生まれる対話をベースに、個々人の弱さに組織として向き合う力を獲得していくのは、面白い。
できるかどうか別にして、ここにも可能性がある。
まとめ
昨年のNatural Leadership研修でも、感覚知を学び、今回も感覚知を鍛えるシリーズだった。言語値でやってきた自分が、改めて自分の感覚知に向き合うことで、言語知にあまり依存しない自分になっていきたい。
【note】Natural Leadership研修の振り返り。
https://note.com/jimaota/n/n29f054309985
最後に。
このような機会を与えてくれたあきちゃん、お忙しい時間をなんとかやりくりしてくれて、少しでも対話の時間を作ってくださった翠さん、また我々を受け入れてくださったスタッフの皆さん。
そして、我々に気付きと、成長の機会を与えてくださった利用者の皆さん。
心からの感謝を。