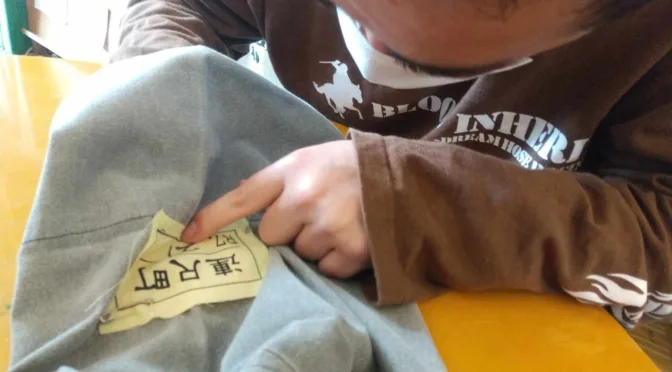コラムテーマ「食」〜料理とだるまと木材(仮)〜

実は、たけし文化センターとちまた公民館にはキッチンがあります。ただこれまでほとんど活用されてこなかったのでその存在は忘れ去られ、今ではただの物置同然の扱いになっています。
最近、私はその忘れ去られたキッチンで料理をする機会が何回かありました。意外とレッツで「食」について触れられる機会は少ないと思うので、これを機に最近レッツで料理をした経験から感じたことをコラムにしていこうと思います。
元々私は料理が好きな方で、お菓子も母親の影響で昔から作っていました。ただ最近は日々の忙しさや、特にお菓子は一回作るとたくさん出来ることが多く一人分だけ作るのが難しいこともあり、以前と比べると料理もお菓子作りもする機会が減っていました。
それが最近になって趣味を仕事で活かす機会に恵まれ、たけし文化センターでは利用者さんの昼食に本格的なスパイスカレーを作り、ちまた公民館では月一回お菓子作りワークショップを開催して、これまでにクレープ&いちごジャムや桜餅を作りました。
私がレッツで進んで料理をする理由、それは「私が好きだから」の一言に尽きると思います。皆においしい料理を振る舞って喜んでもらいたいという、利他的な思いもなくはないのですが、それより遥かにエゴイスティックに自分が好きなことをやりたい思いが強いのです。
全然料理とは関係ないのですが、以前私はレッツに入職して間もない頃にたけし文化センターで利用者さんと一緒にだるま作りをしようとしたことがありました。だるまが特に好きなわけでもない私がなぜ、だるまを作ろうとしたのかというと、レッツは工作が好きな人が多いので一緒に作ったら楽しそうだと思ったこと、ちょうど時期がお正月だったこと、そしてだるまが我が故郷、群馬県の伝統工芸品であることがきっかけでした。
当時ははっきりと意識していませんでしたが今振り返ると、福祉施設で働いているのだから何かしら目に見える形で利用者さんと一緒に活動をせねばならないという、ある種の強迫観念も背景にあったと思います。
何しろ普段のレッツは利用者さんたちが好き勝手に寝たり歩いたり踊ったり歌ったりしているものですから、別に私がいなくても場は成り立つのです。毎日決まったプログラムがあるわけでもないので、スタッフにわかりやすい役割や決まった業務が基本的にはありません。
しかし仕事としてお給料をもらっている手前、わかりやすく目にみえる「仕事」がないことには、どこか後ろめたさに似た感覚を覚えていました。そこで、その頃の私はだるま作りを企画することで「何もしてない」から逃げ、「何かしている」ことにして、何もしていない(と感じることの)居心地の悪さから目を背けようとしたのだと思います。
しかし、結果として誰もだるま作りには誰も参加せず、当初の目論見通りにはいきませんでした。
だるま作りは意図しすぎて上手くいかなかったケースですが、逆に意図していなかったことが予想外の広がりを見せることもありました。
ある日、たけし文化センターの隅で木材の端材を見つけた私は、その角ばった木材を無性に丸くしたい衝動に駆られました。気づいたら私は工作用のカッターを握り、一心に仏像を掘る僧侶のように端材の角を削り続けました。
初めは私が一人で勝手に木を削り続けていただけだったのですが、気づいたら周りに利用者さんが一人二人と集まってきて、各々が木材を使って謎のオブジェクトを作ったり、僕が削った木材をさらに加工したり、木材に色を塗って人形みたいにして遊んでいました。
この出来事から私が学んだのは、意図は伝わらないが意思は伝わるということです。私の経験上、支援をする際にある目標を立ててそこへ至る過程を考えても、レッツでは大抵思い通りにいかず期待する結果が得られないことが多いです。それよりも先のことや効果など考えずに利用者さんやスタッフの中にある熱意を広げて行動に移す方が不思議と面白い結果が生まれます。そこから私が感じるのは、楽しむことや面白がることから生まれる熱は他人に伝播し、何かしらの影響を与えるのではないかということです。
だるま作りとただ木を削る行為の周囲への広がりを生むか生まないかの差は、その行動に対する熱意の有無によるところが大きいのではないかと考えています。だるま作りは自分の外から生じる必要に迫られて起こした行動であり、木を削る行為は自分の内から湧く欲求から生まれた行動でした。考えすぎかもしれませんが、その差が周囲への影響の有無を分けているような気がするのです。
レッツメンバーは重度知的障害を抱えた方が多いので、言語でコミュニケーションを取るのが難しい方も多くいます。そういう人たちと何か共有し一緒に活動するのは、言語的なコミュニケーションに慣れていれば慣れている人ほど難しさを感じると思います。
そこで言葉以外で関係を築くのに必要なのが「感情」なのだと思います。レッツはそんな非言語コキュニケーションが溢れる現場なので、私はレッツで働くようになってから感情を扱うことへの苦手感が減ったというか、自分に正直に生きることが少しずつ上手になってきた感じがしています。
余談が長くなりましたが、私がレッツで進んで料理をするのは、私が料理を面白がる様が誰かに影響を与えると私自身が信じていることが軸にあります。
カレーを作るときに感じるスパイスや食材の色や香りの変化から感じるときめきや、いちごジャムを作っているときの鼻から脳にまで満ちるようなイチゴの多幸感あふれる甘い香りを、まず自分が感じたい。そしてせっかくなら他の人にも同じように感じてもらいたいし、それを共有した方が楽しいだろうとそんなスタンスなのです。
そして「食」は生きている限り誰もが行うことなので共有しやすい。さらに作ることや食べることからは様々な感情が喚起されるので、健常者の方はもちろん、重度知的障害を抱えた人たちと場を共有して共に楽しさを感じるには、料理はうってつけなのではないかと思います。
私は料理は好きですが決して上手なわけでないので、皆で料理を作るときも美味しいものが食べられればそれに越したことはないですが、どこか失敗しても良いと気楽に考えている自分もいます。
幸い、まだ大きな失敗はしたことがないですが、きっと参加する方達と一緒に何かを作って黒焦げの失敗作が出来上がっても、それを皆で「まずい!」といって笑いながら食べるのも面白いのではないかと思うのです。
それに私は忘れっぽいので、よく失敗もします。この間桜餅を作っているときも、餅生地に入れる水の量を間違えて参加者の小学生の男の子に怒られてしまいました。
開き直りではないですが、グループの中心にいる人はおっちょこちょいなくらいが丁度良いのではないかと思っています。しっかりした人がリーダーになって失敗しないようレシピ通りに指示を出すよりは、おっちょこちょいで頼りないリーダーを周りの人が支えるように料理をした方が、それぞれの主体性が発揮されるような気がしますし、何よりその方が楽しいと思うのです。
気づいたら料理の話を書くはずが、ほとんど料理と関係ない話になってしまいました。でも、この脱線して最後に想定外のサムシングが生まれるのがレッツイズム、ということでご容赦ください。
毎月、私はちまた公民館で「ちまちまクッキング」というお料理プログラムを実施していますので、このコラムを読んでもし興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。毎回おいしいものが食べられるとは限りませんが…。(内田 翔太郎)