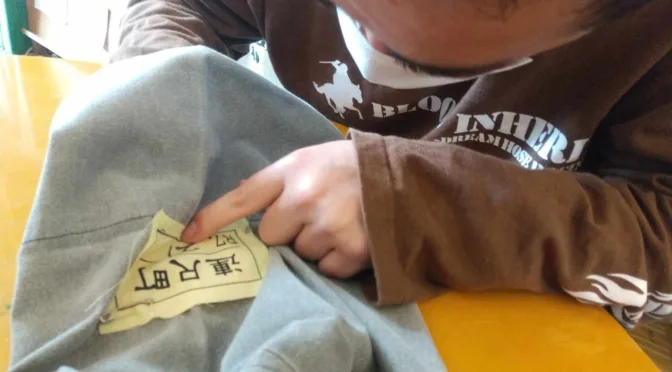![〈トークまとめ〉第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1458-scaled.webp)
〈トークまとめ〉第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]
◉理虔さんと『ただそこにいる人たち』の紹介
久保田:今日のゲストは小松理虔さんです。小松さんには、コロナの前の2019年の5月〜3月くらいまで毎月1回レッツに滞在していただいて、「表現未満、」について考えていただくというお題で寄稿文を書いていただきました。それをまとめたのが『ただそこにいる人たち』という本です。2020年11月の、コロナのまっただ中に出た本だったので、トークイベントはできませんでした。だから、劇的に売れてる本ではないんですが、観光事業のツアーで必ずこの本を読んだという方がいらっしゃるんです。この本を読んでレッツのことを知って、興味を持って、それで来てくれた。だからすごい本で、本当にありがたい本なんです。売れる売れないではなく、私たちにとってもとても大切な本です。
◉レッツを知るのにはまず『ただそこ』
久保田:レッツは毎年分厚い報告書をたくさん出すんですが、決して読みやすいものじゃないんです。今、レッツには正社員が20名弱いて、アート系・文化系いろんなところからやってきて、障害のある人と共に過ごしています。その中から感じている共生社会とかアートとか文化とかをプロジェクト化して毎年報告書を作っています。自分の思いを詰め込むような書き方をするので、報告書は非常に読みにくいんです。その中で、『ただそこにいる人たち』が唯一読みやすい。レッツのことを知っていただくのに一番読みやすいものだと思います。
◉久保田さんのお母さま
久保田:私の母がレッツ設立からずっと応援してくれていて、会員にもなってくれているんですが、彼女が言うんです、報告書を一生懸命読んでも、全くわからない、と。だけど『ただそこ』が出て、この本を読んでくれた時に「あんたがやってることがやっとわかった」って言ってくれたんです。この本は一人一人いろんな方々にわかりやすくレッツのことや「表現未満、」のことを伝えてくれたと思っています。
◉理虔さんを知ったきっかけ
久保田:私が小松さんを知ったのは、新復興論を読んだことがきっかけです。大佛次郎論壇賞を受賞された本なので、そんなに読みやすい本ではないんですが、アートの項目がすごく分かりやすかった。アートというものを入れて事業をやって、そこからどうなったかと言うのをわかりやすく書いていて。いろんな人たちがちょっとだけ幸せになっていくという状況が具に書かれていた。福島と原発の問題でアートというものを入れてみたという部分があって、これこそがアートができることだと、いろんな人たちが癒されていく過程にすごく感動しました。それでこの方にレッツにもきていただいて紀行文を書いてもらいたいなと思ったんです。
◉なぜ理虔さんをお呼びしたのか
久保田:小松さんは作家ではなくて地域活動家として活動しています。福島の原発の問題がなかったら活動しなかったとおっしゃっていて、私も1人の国民として非常に痛みを感じました。忘れられない土地です。そうした時代の中の変化、コロナ、震災、福島の問題を通り越しながら世の中はどうなっているのか、障害の人と共に生きる中でのずれ、これから生き延びるためにはどうしていったらいいのか、みなさんと議論したくて今日は開きました。
◉小松さん自己紹介
小松:東北の南端にあるいわき市からきました。こんなふうに紹介していただくとちょっと恥ずかしくなるような気がします。普段いわきでは地域活動家という肩書きで、活動が溜まると本にまとめるような活動をしています。今新刊の本がもうすぐ出るんですけど、九州の里山社さんからのオーダーで、『ただそこ』みたいなタッチで書いてくださいと言われたんです。新復興論はかための社会評論で、新しい本もそれを求められていると思ったんですが、『ただそこ』みたいに書いて欲しいと言われました。『ただそこ』みたいに登場人物が生き生きしていて、小松さんが考えたことを書いて欲しいと言われたんです。身の回りの人たちも、『ただそこ』の文体は理虔さんらしいと言ってくださる人が多いです。
『ただそこ』を書いているときは、大体いつも、たけぶんに遊びに来て、一階でぼんやりして、夜に3階で書いていました。
いわきでは独立して10年目になります。元々テレビ局の記者をしていました。普段は、WEB、パンフレットを作るみたいなことをお願いされることが多いです。たまに取材や長期的に関わらせていただく仕事もやってきます。中小企業の取材をすることが多くて、今でも企業のSNSアカウントをいくつも管理しています。WEBを作るっていうことは、いいところだけを100倍増しくらいで書くことなんです。でも、実際現場の人たちに話を聞くと、単純に魅力だけでは済まない、様々な問題とか悩みとかが聞こえてきます。取材者としてはそっちも黙ってられない。良く書くのは結構簡単なんですが、ネガティブな話は仕事として、別の原稿に書くことにしています。そんなふうに、いいことも悪いことも書かせてもらってきました。
漁業に関わっていた時、表ではWEBサイトやオンラインショップで魅力発信をして、別のところでは原発に溜まっている処理水の放出などに苦労する現場の声を伝えていく、っていうことをしていました。
◉ぐるぐるしながら目的地にたどり着く
小松:マーケティングの技術が発達してきていて、AIの力を借りると最適解が出てきます。専門家がこうしなさいと言い、成果の出やすいやり方が決まっているように感じます。でも福祉の現場は違ってて、少しずつ対象に近づいているみたいなやり方がある。ある方が、こんな話をしていました。アマゾンの原住民は、Aという地点から、少しずつぐるぐる周りながらBという地点に近づいていくんですね。でもAからBにつく最短距離を今の世の中は求めるんだと。ぼくも、最適解がすぐに出てしまう世の中だと思っています。だからこそ、そういう時間をかけて何かにたどり着いていくみたいな方法、アプローチの仕方や価値が認められていったらいいなと、久々にたけぶんに来て思いました。僕自身は、広告代理店的なアプローチもしつつ、ぐるぐるしていかないとわからないよねというアプローチも大事にしつつ、口に糊をしてきた数年間だったなと思います。レッツはぐるぐるの方の価値観を学べる場所だなと思います。
久保田:それとの戦いだったなと思うんです。レッツは分からないことをとても大切にしている。分かりたいけどわからない、だから一生懸命やる、これがずっとやってきたことでした。私は元々建築系の仕事をしていて、アートの教育を受けているので、もやもやぐるぐる、すぐ答えが出ないことを悪いと思っていなかったんです。世間一般にはそれは嫌われます。答えはなんなの?あなたは何がしたいの?費用対効果は?と言われる。それに嘘をつく。現実はそんな簡単にできない。
たけしを産んで障害者の世界に入った時に、嘘つくのが馬鹿馬鹿しくなっちゃいました。わかんないものはずっと「わかんない」でもいいんじゃないのと。一般受けしないことを言い始めていったんです。常にわかってもらえない経験を今でも続けています。
小松:テレビ局で仕事していた時、僕は数字の住人でした。何の意味があるのか、説明する必要があった。自分が今受けている仕事とか悩みには、自分の仕事・悩みである以上に、必ず社会性が帯びるはずだと思っています。
◉医学部生向けの講座・全人的医療
小松:今、医学部生の教育プログラムを考える仕事をしています。医学部生に向けた講座を持っているんです。医学の勉強もしたことないのになんで俺が、何か理由があるはずだ、と思いながらやっています。現場の先生によると、医学部生は今は限られた大学・病院の現場の中で勉強しているけど、病床がどんどん減っていく中で、これから医療の現場は、病院から自宅になっていく時代がくるそうなんです。その時患者さんがどういうライフスタイルで生活しているか想像できないと、家でケアしていくための方針が立てられない。これからの医師はアウェイの場所、つまり人々の暮らしの場所に行かなければならない。最後の看取りまで考える必要がある。ケアの柱となるのが「全人的医療」と言って、症状だけでなくトータルで人を見なさい、という医療です。どう言うライフスタイルなのか、社会環境、孤立してないか、農村なのかどんな暮らしの場所なのか、家族性の疾患など、本人の背後にあるものを見なきゃいけない。つまり、人がどんな風景の中で、何に生きがいを感じているのか想像できるような医療でなきゃいけない。そう言うカリキュラムを作ろうとなったとき、でも医学部の先生にはそれは教えられない。だから自分が医学部の学生を連れて街歩きをしながら街の背景を学ぶ、ということをやっているんです。
◉専門性が揺らぐ時代
小松:そういう意味で、今は専門性が揺らいでいる時代なのかなと思っています。専門性は突き詰めて考えていくけど、そこに正しさが生まれて、最短距離があって、最短プロセスができていく。でも人間ってそう簡単にプロセス通りに動かない。それが通用しない現場に行った時に戸惑ってしまう。そういう専門的なものを高める人が必要な一方、試行錯誤しながらよりベターな回答を、実践的にプラグマティックにやっていくことが必要とされている時代かもしれません。医療でも、その人全体を見て、ケアプランを考えていかなきゃいけないよ、と言うのは、いろんな人たちがそれぞれケアし合わねければいけない時代に入ってきたっていうことだと思っています。これはレッツに通って学んできたことと重なるんです。合理的ですぐに成果を求められる、というのではない価値観も認められ始めてきているのかな、と感じています。
久保田:私はクリストファー大学の看護の先生、福祉系の先生にも毎年2回呼ばれています。私だけが行くのではなく、その場所に利用者みんなを連れていくんです。私が喋っている間に利用者が色々バンバンやって授業が崩壊するような授業をします。授業を断られても困らないと思ってやっているんですが、でも毎年呼ばれています。コロナ禍後にクリストファー大学に呼ばれるようになって、それまでお互い知らなかったんです。彼らが行ってどんちゃんワーきゃーやって授業を崩壊させている。学生には戸惑って固まっている子もいる。先生たちが何を気に入っているのかわからない部分があるんですけど、でもこんなことでも許されるんだなと言うのはあります。看護学生にも、答えがはっきりしない名付けられない変な人たちが存在していることを知ってもらいたいと思って呼ばれていると思います。世の中のほとんどの人はまだそう言うことに対してアレルギーがあるんです。まだそういう社会だと思っています。
小松:『ただそこ』を読んでくれた長野県の精神科医の先生が、式典で話をしてほしいとオファーをくれたんです。久保田さんの発言とかをプレゼンの中に入れて、レッツに来る利用者さんが散歩に出かける、ハプニングが起きる、でもそうしないと世の中変わらないじゃん、ということを紹介しました。まず知っていくことで状況が少しずつ変わっていく。でないと健常者が当たり前のように道を闊歩するところから何も変わらない。それでも、その場(精神科の先生、職員やご家族100人くらい)からは久保田さんの発言は過激だというリアクションもありました。トラブルになったら、何かあったらどうするんだと。
◉「ただいる」ことが育むこと
小松:レッツに来てる時に、ただいる、と言うことをしたんです。いわきに帰ってから、地元の障害福祉事業所に「ただいさせてください」とお願いしたんだけど、それが難しい。視察ですか?とか言われちゃうんです。結局理事長の部屋でお茶とか出されちゃう。誰もが自分らしくいられる時間を私たちも作っています、と社会福祉法人は理念に掲げますが、僕はいられないんですよ。ただいるってことがなんでこんなに難しいんでしょう。誰かが来ることで、利用者さんが驚いたら、とか、リズムが変わっちゃう、とか、そうなったらそうなったで考えればいい。
僕らもただいるだけでいい、っていう価値観を取り戻さなきゃいけないと思います。福祉の事業者のみなさんも、自分らしくとは思っても、制度の問題とか、(就労継続)B型とかA型とか成果出さなきゃいけないとか、福祉の中でも難しいんだなと思いました。福祉事業に関わっている人も窮屈で余白のない状態で仕事していたりします。ハプニングから学ぶと言うふうに考えられていなくて、若い人も失敗できない、迷惑かけたくない、波風立てたくない、間違えたくないというマインドがあると思います。追い詰められているように感じている人が多いから間違えたくないし、転落したくないし、成果主義的だし、すごく窮屈だと思います。福祉の職員は、誰もが自分らしく生きられるはずだよね、と思って福祉の現場に行くけど、大きな法人に行くと、やらなきゃいけないことを少人数でしなきゃいけなくて、なんでこうなっちゃったのか、という状況になる。もちろん政治の問題もあるけど、株価はあんなに好調なのに、余裕がない世の中になっている。もう少し間違ってもいいし、トラブルとかハプニングとかが文化とかクリエイティビティを育むんだ、という考えがあると、寛容であることが増していくと思います。
◉障害の子どもを持ったことを面白がりたかった/創造性=変革
久保田:一応福祉事業をやっているんですけど、元々すごい違和感があったんです。もともと福祉事業がやりたかったんじゃなくて、たまたま障害の子どもを産んじゃって、大変だ大変だって周りは言うんですけど、実際大変なんだけど、こちらは面白いとしか思えないんですよ。わけわかんないんだけど、面白いじゃんこの子って。どこかワクワクしてしまっている。このワクワク感は誰にもわかってもらえない。福祉の人に聞くと可哀想だね哀れだねみたいな対応の仕方をされる。楽しくないんですよ、話してても。困ったことだけが目の前に突きつけられるんです。私は普通に子育てしたいのに、なんでさせてもらえないのと思ったし、療育施設に行ってもお母さんたちがメソメソ泣くんですよ。家族に許してもらえないとか、こんな子供産んじゃってこれからどうしようとか、ずっとみなさん言っているのが、それがすごく嫌だった、耐えられなかったんです。自分がその世界に入ってしまったってことが耐えられない。そんなこと考えながら人生を送っていいのか、どうせ大変なんだったら面白がればいいじゃん、人はずっと不幸な気持ちを抱えながら生きるなんてできないんだから。自分達が幸せに生きられる場所を作ろうとするしかなくて、それがレッツになりました。
小松:既存の福祉は翠さんとたけちゃんを包摂できなかったっていうことなんでしょうね。
久保田:今でも福祉の業界をすごく信用しているところがあります。そこで働いている方は誠実だし真面目だし、勤勉できちんとした優しい人が多いです。いい業界だと思う。でも創造性を信じてない人たちが多い。要するに創造性というのは、変革ですよね。自分が変わる、子供が変わる、それは痛みも伴う、だけどやっちゃえみたいな。でも福祉は、そういうチャレンジングなことは、あんまり受け入れられない世界なんだなと思いました。
◉「色々な人たち」には「自分」も含まれている
小松:創造性は変化していくことだというお話が今ありましたけど、本当にそうだなと思うことがあって。最近県外で、福祉を学ぶ学生と、社会福祉法人の人たちの話を聞きに行って、そこで社会福祉法人の課題とか魅力みたいなものを社会に実装していくという「ふくしデザインゼミ」という取り組みに関わっています。福祉とかまちづくり、デザインに関心のある学生がいっぱい集まってくるんです。ただ、学生本人は福祉を目指して関心があると思っているんだけど、自分は何も変わらないで、同じ場所に居続けて、「こんなことを提案したらポジティブなことが起こると思います」というふうに、自分を変化する対象においてない、というパターンが多いように思います。創造することで変わっていくんではなくて、自分を確固とした立場に固定した状態で関わろうとする方が結構いらっしゃる、障害の人はかわいそう、何か支援しなきゃというマインドで固まってしまっている人も少なくないように思います。他者のために何かをしてあげたいと思う、それはとっても大事なことなんだけど、そこに創造性っていうスイッチが入っていなかったり、変化に対する怯えがあるのかもしれないけど、自分が他者に対して開かれていないんです。
レッツの夏目さんが、「世の中に色々な人たちがいる、その人と一緒に生活していくんだよと多くの人たちが語るけど、色々な人たちの中に自分を入れていない人が多いんじゃないか。本当は自分も色々な人たちの中にいるはずなのに、自分は色々な人たちの中に含まずに、自分は高い位置に固定して、色々な人たちと仲良くするのがこれからの時代必要だよねって言っているって嘘くさいじゃん」みたいなことをおっしゃってて、本当にそうだなって。自分たちは恵まれている人たちだから、かわいそうな人たちを支援しなきゃいけない、施しをしなきゃいけないみたいな、それも何もしないよりは全然いいんだけど、自分の中にある弱さとか生きにくさみたいなものを開かずに、高いところからそういうことを考えている人たちの嘘くささみたいなものが、逆回転してアメリカのトランプ現象みたいなものに繋がっているのかなと。
◉「かわいそう」の傲慢さ
小松:震災後、東京で講演すると「被災されてかわいそうですね」とばかり言われる時期が続きました。地元で夜な夜なクラブイベントとかをやっていても、メディアが来ると、被災者の復興のためのイベントですよねと言われる。被災した人たちを私たちは見守っていますよ感をすごく感じるんですよ。すごい違和感があって、ある種、未開の人たち、かわいそうな人たちが何か克服するために努力しているのをみているというような傲慢な視線を感じたんです。今のこの時代に、かわいそうだなというだけじゃなく、逆に魅力だって、面白さだって、突き抜けた価値だってあるだろうし、「かわいそう」だけでは勿体無い、時に傲慢になってしまうなと思います。認知症、障害者、被災者、それらの言葉をただ知っているだけだと、認知症って不幸な終わり方をするんですよねとか、自分を、障害とか福祉の世界から外れたところで、高いところから綺麗事を言っているということになってしまうんですよね。
◉「共事者」
久保田:この本で小松さんが名付けた「共事者」という言葉があるんです。なんとなくそばにいる人、そういうつもりでレッツにいたと言っていて、やっぱりそういう人がいる場といない場はものすごく違う。人は、上から見たいわけではなくて、見方がわからないのだと思うんです。中には偽善でやっている人もいるけれど、部外者だけど気にはしているよという人がいて、興味はあるけどどうしたらいいかわからない人が居られる場所、観光もそう。共事者という言葉の発明で、その言葉で活動が広がった、豊かになったと思うんです。「なんかいる人」そういう振る舞いを多くの人ができるようになったら、上から目線がなくなって、もっと関われる人が増えていくのかもしれないですよね。
◉共事者のトリガー:偶然に受け取ること
小松:夏目さんと竹内さんが話してくれたことを思い出しました。小学生が見学に来る「ゴーゴーたけぶん探検隊」という企画には、「もくげきシート」「これやってみたシート」の二つあって、それを記入することが小学生のミッションとして課せられるらしいんですけど、それめっちゃ共事者的だなと思うんですよ。「ちゃう」「てしまう」って、共事者には大事だなと思っていて。東浩紀さんの「誤配」という概念を自分なりに解釈すると、意図せずに見てしまった、やってしまったというのが大事。目的と違う、偶然的に立ち会ってしまったり受け取ってしまったのが共事者のトリガーとなるんです。
「共事者」には、社会運動する人が、外から関わっていいんだという、動員のための時の言葉として活用されるパターンがある。男性だけどフェミニズムとかジェンダーとかの問題に関わるとか。自分は社会問題の一員だとするときの言葉として用いられるということがあるんです。だけれど、実は共事者は「想像してなかったんだけどやってしまった」みたいな含意があることが大事だと思うんです。例えば、特別養護老人ホームで、麻雀のボランティアを募集するとします。実際にやっているところも取材したことがあるのですが、麻雀打ちたいおじさんは地域の中にいて、麻雀したい利用者を図らずもケアしながら麻雀を打ってしまうということが起きる。「目的外ケア」みたいなのが大事で。よもや利用者をケアしていたなんて考えないで、後から気づくことが大事なんです。
これに近いことが、『介護民俗学』を提唱した六車由美さんにも言えます。六車さんは、おばあさんたちの調査をしていて、聞き書きしているんです。ケアではなく調査しているんだけど、おばあさんたちにとっては昔を思い出しておしゃべりする時間になりうる。豊かなケアの時間になっているっていうのがまさに共事者的だなと。自分の興味本位で関わっちゃったんだけど、豊かなケアを作っていく、誤配されていく感じだなと思います。西川勝先生が語っている「パッチングケア」もそう。そこにたまたま立ち会った専門的な知識がない人でも、弱さを抱えた人が来たとき、椅子を引いてあげる、声を掛ける、お茶を振る舞う、こういうとるにたらない日常の振る舞い、つまり小さなケアのかけらが、パッチングケアを作っているんだと。これに僕は共感したんです。僕らは100%のケアを作ることはできないけど、5ぐらい、10ぐらいならできるかもしれない。僕らも5人10人集まれば、プロの一人分くらいになれるかもしれない。素人でも一部分だけでもいいから関われる、興味でつながっちゃうみたいな偶然性を込めた言葉だと思っています。
◉外側にいる人が気軽に提案できるようになることで、関わりが増える
小松:オガちゃんが固まっちゃう話が 『ただそこ』に出てきます。僕は職員じゃないので、オガちゃんは僕にとって利用者ではないんです。プロは強度行動障害について考えるだろうけど、僕にはわかんないんだから、普通にしているしかない。普通にゲームしてたら普通に楽しいじゃんと、それでいいと思うんです。正しい振る舞いを頭に思い描きすぎて行動できない人も結構いるんじゃないかな。
そういう障害とかケアの場をもっと開いていって欲しいと思ったときに、レッツの面白いところは観光だったり、こういう場で一般の人に、ケアとか障害について考えるチャンネルが開かれている場がありますよね。障害者と家族と支援者だけでよろしくやっていてください、というのは無責任だと思うんです。正しい知識を持った人だけで、っていうのは決まりきった人たちしか来ない。障害とか復興とか、決まりきった人たちしか関わっていないのと同じです。「健常者の皆さん、障害のある人に関わってください」とか言っても、優等生の言説として受け止められちゃう。ちょっと悪ノリでこんなことやってたらケアに繋がっちゃったみたいなことにもう少し価値を認めたらいいと思うんです。100頑張っている人の目線で10しかやってないというよりも、10でいいよね、と言える勇気が必要だと思う。僕みたいなノリで、10でもいいじゃんて語れる人が増えていけばいいなと思います。それは実は、福祉に関わっていない人の役割だと思っています。例えば水越さんが職員として言ってもだめ。「とはいえ福祉事業所の職員さんですよね」と見られちゃう。僕みたいな人間が、新しい関わり方を世の中に提案してみる。それで関わりが増えればいいなと。福祉の外側にどういう言語で伝えていくのかを考えないといけない。久保田さんが言っても、理事長として、ある種の正しさをまとった人に見えてしまう。そうじゃない福祉の内側にいない人が言っていけると、当事者の人たちが楽になっていくのかなと思うんです。
それは福島の問題でも同じかもしれません。大熊町と双葉町に、除染で出た土を30年間保管する場所があるんです。でも外部の人は「僕は原発とか放射能についても意見ないし、福島の皆さんの良きに計らってください」みたいな感じになってしまう。「それは福島の問題ですよね、福島で考えてください」っていうのは責任放棄のような気もしちゃっていて。そもそも電気を使っている人としての当事者性もあるよね、というふうになってもらえないといけない。外側の人が、俺も関わっていいんだな、と、気軽に、他人の顔色を見ることなく福祉でこんなことしたら面白そうだな、ということが言えることは大事だなと思って、「共事者」という言葉を言い始めました。
◉専門性を問い直す必要
久保田:一方で専門性がある。専門性をもう一回問い直した方がいいかもしれないですよね。福祉に関しては、保育、高齢者、障害にしても、専門家が当事者を見るとなっているんだけど、それは要するに、その人たちに押し付けているのと同じなんですね。家族だけではどうにもならないから、なんとかしてくださいということで施設を作った。そもそもの問題を誰かに委託して行ったと思うんですよ。専門家に押し付けてしまうことで、関係ない人が生まれる。福島の問題もそうだと思うんです。専門家や地元の人に押し付けてしまう。沖縄の基地の問題も同じ。その人たちの問題としてすり替えてしまうっていうのはすごくあるなって思って。なんとなくふわっと関わるんじゃなくて、自分ごととして一回受け入れて関わる、そういう体・マインドを作っていかないといけないのではないかなと思います。専門家に渡してしまうと、まずその人たちが疲弊する、そして社会から障害者や高齢者がいなくなることで、なかったことにされてしまう。高齢者施設があります、障害者施設があります、福島の問題があります、でも私の周りはクリーンです、となってしまう。このクリーンですと言っている社会がいかにダメな社会か、コロナの後みんな気づき始めた。つまり、なんの問題も起こらない、なんの問題も考えなくていい社会を作ったために、いろんなことを人間が考えなくて良くなっちゃったんですよね。人間が身体的感覚を失っちゃったと思うんですよ。いろんなことを自分ごととして考える、そして首を突っ込んでいくことは大事だと思う。それには、物見遊山というか、気楽に関われることは大事だなと思います。これからは専門性との戦いかもしれない。福祉の人たちに専門性を捨ててど素人になりましょうと言っても、多分また怒られてしまうけど、でも、そうしないと共生社会は実現しない感じがするんですよね。専門性に分かれていくと、その人たちしかいない世界を作っていく。
◉「身体性」について
小松:専門性があるからこそ、それを段階的にマニュアルにしてアウトソーシングしやすくなっちゃったということですよね。障害などで苦しんでいる人がいるけど、専門家でやってください、そして自分の周りは穏やかで、自分の暮らしは揺るがない、それがいいと。それで効率良く回っていたんだけど、コロナ禍で誰もが飛沫に晒されてリスクが可視化されて、アウトソーシングするだけじゃダメだよねと気づいた人が増えている気がして。人間はツルツルしたスマホの画面をなぞるだけじゃない。人間は自分達で土を掘り返し、自分達で食器を作り、さまざまな身体的スキルで自分の暮らしを作り上げてきた。かたや危機の時代に、身体的なものを取り戻していくことは絶対に必要だと思います。ケアの現場で、人ってこんなに重いんだとか、人のうんこってこんなに臭いんだとか、そういうわかったつもりになっている自分を疑って一から確認していくこと。
レッツで佐藤さんが「佐藤は見た!!!!!!」の振り返りをやってて、佐藤さんが利用者と後出しじゃんけんでいつも勝っているのを録画していて。そこに細馬先生がいらっしゃって、人間にとってじゃんけんとはそもそも何か、みたいなところから議論がはじまったことがあったんですよ。レッツがやっていることって、当たり前のことを当たり前にしないで、それってそもそもなんだったっけ、っていうところから始めること。そういう局面でこそ専門家が生きてきて、専門家が結論とか正しさを導き出すんじゃなく、みんなで考える場をファシリテートしているんです。
知的障害のある人がじゃんけんに勝てずにもやもやしている動画から、人にとってじゃんけんとは何かとか、知的好奇心をそそりながら、身体を考えるというチャンネルになっていた。なんでもアウトソーシングできる時代に、食べるとか掴むとか当たり前に使ってしまうフレーズをもう一度考え直してみるという動きがないといけない。便利さや快適さを疑って、失ったもの、福祉や、エッセンシャルワークと言われるものなど、見ずに済んでいるものをもう少し取り戻していくこと。世の中が進んでいくときに、直線距離ではなく、一瞬戻ってくる動きが重要だと思う。そういう身体性を取り戻していくことが多分面白くて、共事者を育てていく上で一役買ってくれるんじゃないかと思いますし、レッツのような、ケアの現場が生々しく残っている場所でそういうことができるといいのかなという気がずっとしています。
専門家に判断を丸投げせずに、自分達の暮らしや生きていくことの時間や行為を自分の方に取り戻す必要があると思うんです。立ち返ってくると、レッツにはそういうものがいっぱいあるじゃないですか。人と散歩しに出かけることとか、紙をちぎる行為の、表現の身体的心地よさとか、原点みたいなものがこういう場所には転がっている気がして。生身のミニマムな表現、まさに「表現未満、」もこの戻ってくる動きに入っているのかなって気がします。
久保田:私の感じている身体感覚は小松さんのとはちょっと違うかもしれないです。言葉で名付けようとしないこと、ですね。ここの現場って言葉がない人がほとんどだし、言葉のやりとりができないんですよ。突然飛び出したり、叫んでいるくらいはいいが、飛び出していくとスタッフが止めに入らなければいけない。言葉で言ったところで何もならない。こちらが五感で動かなきゃいけない。ヒュってやったら手を出すとか。そういう身体感覚、それも一つのコミュニケーションだなと。言葉に頼るのではなく、体で呼応していくというか。そういう応答をもう少し信じたり大切にした方がいい。
今の若い人はそれができるんじゃないかと思っています。今の学校ではいじめとか色々あるなかで、空気を読む必要があって、みんな繊細なんですよ。そういう意味での感覚が高い気がします。スマホをいじっているから身体感覚がダメ、じゃなく、言葉じゃない空気を読むってことにものすごく注力する感覚が研ぎ澄まされていると思うんです。そういう人たちが作る世界は、私たちの世界とは確実に変わっていくだろうと期待しているんです。私たちが作ってきた世界は言葉で支配する世界で、感覚を鈍感にさせてきた世界だったと思うんです。お金持ちになる人、功績を作った人が評価される、病気になることは挫折、とか、ものすごく軸がはっきりしてわかりやすかった。でも今までの価値観が通じない世の中になると思うんです。だから身体性が大事なんじゃないか。今の世代の作る世界は、我々が作ってきた世界とは違うものになると期待しています。
小松:うちの小4の娘も空気読んでますね。所属するコミュニティによってキャラを変えながら。大変そうです。
久保田:ほぼそういう人たちが育っていくわけですよね。中には体も丈夫で頭脳明晰でお金もあるようなエリートもいるけど、それは氷山の一角で、ほとんどの人はとにかく生き延びる力を自分なりに蓄えていかなければいけない時代になった。その時代の方が私たちはありがたい。前へ前への時代だと、障害者は生まれた時から負け組みたいな言われ方をします。
そうじゃない。どんな人も生きづらい時代は、我々にとってはいい時代になったなと思うんです。共感してくれる人が増えました。
小松:言葉に頼らないってことで思い出したんですが、「共事者」はしっかりと定義してはいけないんだと思っているんです。正しい共事者が生まれると結局また同じことになる。あなたは共事者じゃないねとか、あなたのやり方は共事的ではないとか、正しさを突き詰めてしまう。共事者ははっきりさせてはいけない、正しい共事者像を作ってしまってはいけないと個人的には思っています。言葉で定義することは悪ではないんですが。言葉づかいとか空気感を変えて付き合っていかなければいけないみたいなケアの感覚を持っている世代は、新しい地平を見せてくれると思います。3、4年くらい前に、演劇とか芸術に関わっている若者に、僕の活動を説明するようなレクチャーに呼ばれたんですけど、質問ありますかって聞いたら、「小松さんはなぜそんなにいつも怒っているんですか」と聞かれたんです。そりゃそうだろと思いました。原発事故に対して怒ってるから、その怒りを忘れたら本当の復興には辿り着けないのでは?むしろ、怒りをみなさんが受け取って表現に落とし込んでほしい、ということを言ったんですけど、この10年で僕らが感じた復興観みたいなものが変わって来ていて。
僕ら第一世代は東電に冷静に話を聞きにいけない、でも若い世代は東電にも話聞きにいくし、いろんな人たちから声を聞きたいっていうマインドを持っているんです。加害側に話を聞きにいくってことは、彼らが次の世代で、共事者だからできること。僕らは当事者だから、東電の幹部とはまともに対話できないと思う。でも彼らは、僕らが越えられなかった壁をするりと越えていく。当事者だからこそ少し寂しい部分もあるけど、むしろ僕らのように怒りを受け止めていないからこそ、これまでにない新しい復興の形を作れるのかもしれないなと。これを感じるのに13年くらいかかったんです。許さない気持ちを持ち続けるというのが新復興論に書かれていることなんですよ。でも若い人はあっちの話も気になるなと、原発推進側の話も聞いてみる。若い人たちを否定せずに、彼らが作る未来を見てみたいなと思えるんです。
久保田:それがやっぱり文化だと思うんです。問題に対する活動が長く語り継がれていくようにするときに、文化が力を発揮していくんですね。
<質疑応答>
◉発信の仕方
来場者A:SNSで企業のアカウントを管理してらっしゃって、一方で漁業関係での課題も発信しているとおっしゃっていたんですが、課題を抱えているものの発信の仕方って難しいですよね。具体的にどうやっていますか?
小松:魚屋さんや加工屋さんの公式アカウントを仕事でお預かりしているんです。福島の問題は複雑で、処理水について反対している水産業者が多い印象なんですけど、公式アカウントで反対というのを投稿してしまうと、「賠償金が欲しいんですよね?」とか「復興したくないの?」というアンチっぽいコメントが来てしまうんです。公式アカウントはこういう状況だけど頑張ってます、ということしかなかなか発信できないんです。仕事としてはそういう公式アカウントを預かっているので、それとは別の媒体、noteとかで、自分の名前で課題や問題を書いています。あとは、取材された時に、漁業者の本音が外からは見えないということになってしまっているので、直接的に反対の声を上げることも難しい状況だし、僕が聞いている状況など、知っている範囲のことを書くようにしています。
◉レッツという場に感謝
来場者B:僕はメンタルの障害者で、当事者なんです。感謝を久保田さんと小松さんに申し上げたいと思いました。20歳の時に統合失調症になりまして。幻聴幻覚はなかったんだけど妄想はあって、一時期閉鎖病棟に入りました。今は49歳ですが、最近座禅を知って、A型にいけるくらいには復帰しました。福島でも精神の病院で入院している方々が必要ないのに長期入院を強いられていることもありますよね。
20何年間も障害者をやってきて何が辛かったかというと、とにかく寂しいんですよ。社会の外側に置かれる、別のカテゴリーに入れられるんです。統合失調症を隠すのは嫌だけど、みんなに言えば、友達だって離れていく。怖がって近づかない。そういう現状の時に、共事者という存在のありがたさ、レッツのような自由な居場所に可能性を見出してくれたことに、感謝申し上げます。
来場者C:沖縄の問題と福島の問題は瓜二つなんですよ。パレスチナ問題は、アラブ人とユダヤ人が仲が良かったのが、イギリスの3枚舌外交で喧嘩状態になってしまった。朝鮮戦争でも同じ民族が分断されちゃうんですね。精神医学でも強制入院させられてしまうでしょう。20年とか拘束されてしまう。精神病院は巨大な牢屋。僕も病院に行った時9割くらいの人は普通なんですよ。本当は1年くらいで治るんですけど、10年もいるっていうのはおかしいんですよ。これらの問題は他人事じゃなくて自分ごと、繋がっているんですよ。全体を見ることが大切だと思います。レッツはイメージで考える人が多い。
小松:浪江町に研究施設ができることになって、どういう研究が必要なのかをリサーチするために精神障害のある人にも話を聞いたら、「復興する地域に障害のある自分たちは必要とされていない存在だと感じていた」とおっしゃっていました。もっと右肩上がりにしなきゃいけないのが復興だったんですよね。障害があって動けないとか、ちょっと具合が悪くてしばらく寝てないといけないという人は必要とされていないんですよ。だから、弱さを抱えている人たちには、居場所、帰る場所がない。そこまでの余裕がなかったのかもしれないけど、それが復興でいいのかと問われなきゃいけない。強さを持っている人たちがバリバリやっていく段階ではなく、弱さを抱えている人たちが誰かのサポートを受けられる段階になって初めて復興のステージになっていくということなんです。こういうことはようやくこの2年くらいで語られるようになってきたんです。障害のある人が帰ることができずにいた、疎外されてたんですね。
◉専門性について
スタッフ夏目:さっき紹介いただいたように、いろんな人の中に自分もいると言っているにもかかわらず、当事者っていうカテゴリーを作ってしまっているんじゃないかと思っているんです。佐藤さんと鶴見くんのじゃんけんの話、細馬さんが人の体とはこういうふうに動いて、など色々分析をしてくれたのは、そこでは福祉ではない世界に入っている。そこから福祉への興味ではなく、人間への興味になってほしいと思うんです。
施設を運営するのに、生活介護のデイサービスは無資格でできるんです。もちろん責任者は資格がいるんですけど、従業者は無資格でいいんです。専門性って何かという話なんですけど、専門性はあるように見えて、作っているのは壁だけじゃないか。今日は私はこうすけ君のヘルパーとして参加しているんですけど、ヘルパーとして居宅支援をするときに、たった2日の研修で入れてしまうんです。だから、専門性は外から見える架空の何かじゃないかと思うんですね。放課後等デイサービス、子供が使う分野はすごく厳しいんですけど、そうじゃない分野は、なり手が少ないということもあって、すごく緩いので。専門性と福祉の幻想を、私たちは人間に立ち返って関われたらいいなと思っています。
来場者D:広島県の高齢者介護事業所で介護をしています。私は新聞記者から介護へキャリアチェンジしています。私は逆に、専門性を軽んじられているんじゃないかと思うんです。介護はかなり専門性がいる分野だなって毎日感じていて。人の体は重いけど、技術さえあればやっていける部分がすごいあると日々感じています。福祉を開いていくとなった時に、開けるのは外の人じゃなくて中の人だと思っていて。現在、鞆町に住んでいて、認知症の方が徘徊ではなくて、平気で散歩できるエリアに住んでいるんですけど、よく高齢者の方がコケてることがあるんです。コケてる人をいち早く起こしてあげられるのは専門職だと思っています。でもいち早く見つけるのは地域の人にしかできない。私たち専門家は倒れた人を起こす仕事に集中したいから、倒れた人を見つける仕事は地域の人がやってくださいという積み重ねで、今うちの介護施設は回っているんだと思います。あと、私のバックグラウンドを知らない人に、介護の仕事やっているって言った時に、軽んじられているなと感じるんです。ケアは誰でもできることだけれど、私が1年半かけて積み上げてる技術を誰にもできることと思われたくない、っていうもやもやも感じています。
スタッフ水越:組織として、専門性という軸で習熟度があって、(固まって帰れなくなった人を)スムーズに早く帰らせることが利用者さんとの長い関係の上でできるようになったとしても、新しいスタッフがやると3時間くらいかかることが起こるんです。一回戻るんですね。スムーズな形ができてきた時に、戻る。理虔さんのぐるぐるの感じに近いと思います。どれがいいチームの在り方なのかなと思うんですが、怪我させないとか、利用者さんの何気ない一言の意味がわかるスタッフはわかる、語弊はあるけど長い関わり合いからスムーズなコミュニケーションがつくられていく、そのほうがいいのかと思ったりもしました。でも新しい人が来てぐるぐるする。スムーズなコミュニケーションを維持することが大事なわけではなくて、ずっと1対1でやっているわけでないので、いろんな人が混ざりながら、今回は通じないようなことが起こる方が、利用者さんにとっても、新たなチャクラが開くことがあるのかなと思います。例えば、理虔さんがきたから、オガちゃんが急にコーラで乾杯し出すことが起こったとか。専門性も道みたいに基準やルールがあってというよりは、これも専門性と呼んじゃっていいかしらみたいな、専門性のずれみたいなこともあるのではないかなと思います。
久保田:専門性の質にもよるんですけど、基本的には必要ないと思っています。母親だったから、たけしを25年間介護し続けたんですよね。一番たけしの介護をしたのは私だから、母親だけど、ある意味たけしの介護の専門家と言ってもいいかもしれない。だけど、つくづくダメだと思いました。知れば知るほどダメになる。人間が人間の専門家になっちゃいけないんですよ。人っていうのは、失敗も含めていろんな人と接して生きていくのが人間だと思う。その中に喜びとか悲しみとか呆れとかいろんなものが生まれるんですよね。福祉って、専門性で固められた時に、本当に面白くない人生しか待ってないんだろうなと思いました。ずっと私がいることが、私の幸せにもならないけれど、たけしの幸せにもならないだろうなと思った。私が専門家であるがゆえに、常に同じサービスを繰り返し繰り返し提供しているようなものですよね。それって彼にとっては、地獄でしかないなって思ったんですよね。だってそのサービスしか知らないことになっちゃうから。レッツはご飯の食べさせ方もトイレの介助もそれぞれがバラバラのやり方でやっているんですよ。たけしはどうしているかっていうと、ちゃんとその人に合わせているんですよ、あんなに重度で知的障害が重いって言われている人が。たけしはそれで不満に思っているかもしれないけど、でも、この人はこんな感じ、あの人はあんな感じ、っていうのが楽しいんだと思うんですね、人生って。専門性の質にもよるけど、人間を相手にする人に専門性はないと思っています。
小松:僕らは、原発事故があって放射性物質が飛散した時に、一部の専門家が「これぐらいの被曝で怖がっているのは中学生レベルの知識がないからだ」というような過激なことを言っていたんです。その時思ったのが、この人たちは放射能の専門家であって、コミュニケーションの専門家ではないんだなということでした。もちろん、コミュニケーション能力を犠牲にしても、専門性を追い求めることで、福島の汚染が解明できた面もあるのでしょう。そういう経験があったので、専門性とはなんだと考えるようにもなりました。地域の人たちって、専門性のない人間ではなくて、自分の暮らしの専門家なんだというふうに考えるようになったんです。暮らしの専門性と専門家の専門性が合わさって、ここはやっぱり危険だなとか、ここには暮らし続けていいんだなとか、手応えのあるデータが見えてくる。目の前にいる人たちにも何かの専門性があるんじゃないかなと、自分のもっている専門性は一部分で、相手の専門性をリスペクトした時に何かコラボレーションが考えられたらいいなと思いました。
専門家は専門性でバサバサ切らなければいけない時もあると今は思うんですよ。国際的な学会のデータとか見て、あなたの言っていることはおかしいよという人がいる、その上で、地域の人たちのバックボーンを考えて専門性の出し方を考えないとダメだよねと。つまり、専門家と、僕みたいな素人との緊張関係が必要なのかなと。全て専門性を持った人たちがいればいいのではなくて、専門家と非専門家がある種の緊張関係をもって、時に合意し、時に言い合える状況ができているといいのかなと思います。僕自身は、自分は何の専門家でもないというのを売りにしているんですよね。プロの素人でありたいと思っています。翠さんの言うように人に対する専門性はいらないっていう人もいつつ、Dさんのいう開かれる専門性もありつつ、専門知を一部の人たちが占有しない、専門性についてみんなが言葉を吐き出せる場があるといいなと思います。
スタッフ瑛:例えば、こうすけさんが何かしているのは彼が何かを知覚していて、私たちには知覚できない。専門性は能力と近接しているなと思うんです。私たちは言語能力に重きを置いているから、それが頭がいいと思っているけど、こうすけ君の知覚している能力と、ビジネスマンが3分間でプレゼンできるのも同じ能力だと思うんです。私たちが自分の暮らしのスペシャリストだよって言っているのも、一つ一つの専門性、能力が見出されたらいいし、そういう世界が広がっていったらいいなとお話を聞いてて思いました。
◉弱者/強者、被害/加害は入り組んでいる
スタッフ瑛:理虔さんの論説を読んで、自分の強者性、男性性も引き受けながら、自分の言葉で答えて語っていくのが共事者なんだと書かれているのが、自分自身にもつながるなと思いました。
小松:以前、ゲンロンでトークイベントをしたときに、いわゆる「弱者男性」の話題になったんです。コメント欄に、「とはいえ理虔さんは強者だよね、僕たちが苦しんでいることなんてわかんないじゃん、ゲンロンみたいな場にきてほしくない」というコメントが流れていったんです。まあわかるなという気がしつつ。それからこんなこともありました。いわきで仕事で一緒になっている40半ばの人たちと、おっさんになって辛いことあるよねとクダを巻いてインターネットで配信をしていたら、若い人から「ホモソーシャルすぎるし、さんざんいい目を見てきたお前らが弱さとか言ってんじゃねぇ、欺瞞じゃん」とコメントがついて。俺ら、弱さを吐露もできないのかと辛くなったんです。でも、この辛さにも意味があると思っていて。確かにそうだな、これまで自分は個人主義的、能力主義的に生きてきた部分もあったなと。地域のくだらないエリート意識もあったのかもしれないなみたいに思っていて。この話を、アメリカに結びつけてもいいかもしれないです。トランプを支持する人の中には、リベラルにとっての弱者の中に自分は入れてもらえないという疎外感があるんじゃないでしょうか。疎外ではなく、やっぱり包摂していくことが必要だと思います。自分の中には強さと、自分なりの弱さがある。どこかの部分では加害の立場だけど、福島にいるっていう意味で被害でもある。差別/被差別の立場は入り組んでいて、重なっていたり複雑になっていたり、被害者でもあり加害者でもあり、そういう複雑な状況を我慢していかないと、弱者競争、当事者競争になってしまうんです。「ネガティブケイパビリティー」の一言で片付けたくないという思いもあります。男であることによって考えずにすんできたこともあるなと思って。こういうことは、自分の中の弱さ、強さを客観視できて初めて思い至ったことでもあります。「きてほしくない」というコメントを引き受けて考えて、自分も楽になった感じがします。
スタッフ夏目:専門性もホモソーシャルも随時更新していけばいいんですよね。
小松:自分の専門性に閉じずに開かれているからこそ、専門性を更新していける。
スタッフ渡邊:今の話を聞いてて思ったのは「わかんねぇよってことを教える人」を意識して自分がいること。観光の時とかお客さんに、たけしさんのこれどういう状態?って聞かれて、わかんないよそんなの、みたいな。なんで答えがあると思っているんだろう。わかんないって胸をはることを知っていただくのがいいのかなと思います。
小松:答えを出すことを控えることで、専門性が更新されていくきっかけになるのかもと思います。
◉若い人の範囲
スタッフ律:若い人ってどの範囲なのか気になるんですけど。
小松:アンダー25の人たちかな。そのぐらいの感じです。
◉防災について
来場者E:震災のあと、何もやってこなかったなという反省なんですけど、防災に関心があるんです。私は本屋なので防災関連の本を並べたりしてるんですけど、全然反応がなくて。防災で自分の身を守るのっていうのがエゴイスティックな行為に思われるのかなと思っちゃったんです。防災で集めた本に、隣の人と挨拶をするっていうのも大切な防災です、って書いてあって。地域とかにも関心を持ったし、防災についても聞いてみたいです。
小松:防災とカテゴライズしなくても防災しちゃってる、みたいなのが、いわきでも実践されています。みんな、よもや自分の地域の中で災害が起こるとは思っていないんです。防災で前提となっているのがボランティアです。ボランティアが基盤になっている。いわきでは、ボランティアしたくなる「仕組み」を作ることが実践されているんですね。利他的な行為としてのボランティアをしたくなるのがスポーツだとされていて、そこからもしかしたら防災とかにつながっていくかもしれないと、いわきFCのスタジアムを議論する中で話になったこともありました。楽しくできる仕組みを作っていく。ちょっと捻っていかないと防災は広まらないです。災害は自分のところには来ないとみんな思っている。それを前提で啓蒙していくしかないです。図らずも防災しているみたいなことを続けていけるといいのかもしれない。
久保田:浜松市の特別支援学校が、海から600mしか離れていないところにあるんです。私がPTA会長をした時に移転を打診したんですけど、移転には至らなかったんです。今度、建て替え話が同じ場所で持ち上がっていて、反対運動が始まるんですけど難しくて。そこの南区の人を敵にしてしまうんです。南区は危ないよと言っているのと同じになってしまう。南区には福祉施設もあるから動かないでくれとも言われていて。だから、世の中そんなものなんですよ。ゲリラ戦しかないなと思っていて。怖がらずに、私はこうと言っていくしかないし、賛同してくれる人もいるし、反対意見があることは前提だと思うんですよね。私が反対運動するのは、自分の信条だと思うんですよ。やっぱりあんなところに学校があっちゃいけないと思うし、インクルーシブ教育というなら学校は街の中にあるべきだと信じているから。それを言うしかない。
来場者E:政治とか戦争の話をしちゃいけないとか、すると嫌われるとか、つながっていると思うんですよね。
小松:1ヶ月本屋の名前を防災のBにするとか。
久保田:そういう楽しさがないといけない。政治的な話をしても捕まる国ではないじゃないですか。それぞれの意見を言っていくしかないし、言っていいんだという雰囲気を作っていかなくちゃいけない。でないとこういう会をやっている意味もない。言っていきましょう。