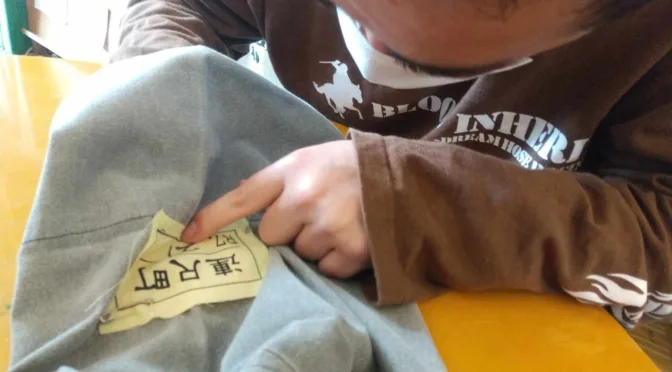![〈トークまとめ〉第5回 ゲスト:西川勝さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1369-2-scaled.webp)
〈トークまとめ〉第5回 ゲスト:西川勝さん [ひとインれじでんす2024]
Day 2
聞き手:尾張美途、ササキユーイチ、櫻井喜維智、夏目はるな
尾張 通常だったら、意思決定支援会議っているのは普段関わっているヘルパーさんや日中支援している福祉職員、親御さんなどが、これからどうしていくかっていうことを話し合ったり決めたりするんですけど、今回は外部の方と臨床哲学プレイヤーの西川さんも一緒に話し合って行きたいなと思っております。では、たけしさんの意思をどうやって決定していくのか、てんかん手術をどうするのかっていう切り口から始めていきたいと思います。
◼︎西川さん自己紹介
西川 西川勝です。大阪から来ました。小学校一年生の娘も一緒に来てて、僕の介助を手伝ってくれてます。
僕、もともと看護師なんです。精神病院の看護助手からスタートして、15年くらい現場で働きました。その後、血液透析の仕事や高齢者介護の仕事にも関わり、いろんな現場を経験しました。もともと哲学科に行ってたんですけど、看護の道に入ったらそっちが面白くて、哲学の方は中退してしまいました。でも40代になって「臨床哲学」って言葉に出会って、昔お世話になった鷲田清一さんの話を新聞で見て、大学に電話してみたんですよ。そしたら「あの西川か!」みたいな感じで話が進んで、結局大阪大学で社会人として学び直しました。その流れで、大学の教員にならないかって声がかかって、コミュニケーションデザインセンターってところで11年間教員をしました。58歳で仕事を辞めた後は、大阪の認知症の人と関わる活動をやったり、重度心身障害の訪問介護事業所の理事になったり、ヘルパーさんたちと「ケア塾」って勉強会を毎月やったりしてます。
看護師時代、ためらいのナースってことで、自信を持って看護するタイプじゃなくて、ずっとためらい続けていたんですよね。で、65歳になって、次々と病気が見つかりまして、腎不全、脳梗塞、肺がん…どれも結構シリアスな病気です。でもふと振り返ると、自分が看護師として関わってきた患者さんたちと同じ立場になってるんですよ。
で、実際に患者になって分かることは確かにあるんです。病気の辛さはある程度想像できたけど、「患者でいることの辛さ」がこんなにひどいものとは思ってなかった。外から見てるだけじゃ分からないことを今嫌ってほど味わってます。今年の3月に肺がんが見つかったとき、あと半年くらいと言われました。でももう10月です。今もう危篤状態でもおかしくないはずなんですけど。
もう一つ、宮沢賢治の「眼にて云ふ」という詩を紹介したいなと思います。すごく衝撃を受けた詩です。彼が出血がひどくて命が危ないって言われた時に書いた詩なんですけど、自分の体から血が湧き出てる状況で、「あなたから見たら私は惨憺たる状態でしょう。でも私から見えるのは、青い空と透き通った風なんです」っていう内容なんですよ。でもそのことをあなたに伝えられない、それが一番辛いっていう詩なんです。
僕も今のところ、治療法はなくて、医者から死ぬまでの期間を伸ばすだけって言われてます。でも僕にとっては、こうやってレッツに来て話をするというのはやっぱり刺激になるし、喜びなんです。だから、大阪からわざわざ来ました。途中で倒れるかもしれないけど、万全に治療を受けながら死を迎えるっていうより、自分が行きたいところに向かって倒れる方がいいって思ってるんですよね。
人の幸せとかケアを考えるとき、「生命」「暮らし」「人生」っていう3つの次元が必要です。皆さんはヘルパーとして、人の暮らしを支えてる。だから、医学的なことは医者に任せるとしても、暮らしや人生についてはしっかり考えられる立場にいると思います。
てんかんという病気や手術の医学的な側面にどうしても話が行きそうになるわけですけど、そこを一旦立ち止まってもらって、皆さん自身がたけしくんの暮らしと関わる中で、人の暮らしで大切にすべきものは何なのか、人が人と共に生きる時に人生において何が大切なのかを考えたいと思います。
◼︎たけしさんの紹介
尾張 たけしさんを簡単に紹介しますと、28歳男性、重度の知的障害、自閉症、大きい側湾もあります。そして大きなてんかん発作もあります。
◼︎てんかん手術の話が出てきた経緯
ササキ 今日、西川さんとたけしさんの意思決定支援について話そうとなったきっかけは、今年に入ってから、たけしさんのてんかんの治療の選択肢に手術が出てきたことです。しかも、その手術は開頭手術で、頭を開いて脳の一部を摘出するという一度やると元に戻すことが難しい手術でした。ですが、新しい薬を試したことで発作が落ち着いているので、医療の側から手術の必要性はないと言われているというのが現状です。だけれども、選ばないといけないとなっていた1-2ヶ月前に、自分たちがどのようなこと考えていたのか、考えようとしていたのかを、今だからこそ一歩引いて考えられるのではないかなと思っています。僕らは生活や暮らしに関するたけしさんの選択にはこれまで関わってきたし知見もあるんですけど、人生に関わる選択についてはまだ全然経験がないので、今後その選択に関わるための礎のようなものを今日探れたらいいかなと思っています。
◼︎たけしさんとてんかん
ササキ たけしさんのてんかんとの付き合いは10代から始まっています。20代の半ばまではテグレトールと〇〇という薬でてんかんが起こらない状態が続いていました。ただ、その薬の副作用が強かったんですね。当時は親元で暮らしていたので、薬の選択は主に家族がしていました。2019年から連尺町での一人暮らしをスタートしました。その暮らしが始まって2年ぐらいしてから、25歳の冬に数年ぶりの大きなてんかん発作がありました。薬の副作用による嘔吐も続いていました。そこで薬を切り変えて、てんかんも副作用の嘔吐もなくなっていたんだけども、眠れなくなったり、発作の形が変わって、痙攣しり発作ではなくて、急に体が硬直して後にバタンって倒れてしまうという発作がたくさん起こるようになってしまいました。それで去年6月、発作で転倒して骨折をしてしまいました。一時は歩けなくなるのではという心配もありました。その時そばにいた僕や野沢さんは冷静に対応したんですけど、もしそれ以外の人が関わっていたらどんな気持ちになっただろうとか、いろいろなことを考えました。
そういう発作がなかなかおさまらない状況が続いて、薬を調整してきたんですけど、家族とも相談して、今年の5月頃に、医者にてんかん治療のセカンドオピニオンを聞きたいとお願いをしました。それで6月に大きなてんかんセンターにかかったところ、「なんでこれまでしっかり検査をしてこなかったのか。彼の発作がどのようなものか、医療の専門家が診断名をつけないといけない。てんかん治療のガイドラインがあり、2年間2種類以上の薬を使って発作がおさまらない場合は、難治性脳てんかんと定義される。その場合、薬ではコントロールできず、おそらく手術である。」と言われました。そしてヘルパーが付き添って7月頭に検査入院したところ、やはり脳梁離断手術が効果的だという話でした。同時に新しい薬も試すことになって、眠気という副作用はあるんですが、発作自体はおさまっています。ヘルパーや家族で話し合いをして、一旦は手術はしないという選択をしました。
診断の時に、今後発作が進行していくかもしれない、そうすると今のような生活ができなくなってしまうかもしれない、だから医療としてはその前に食い止めることがしたいと言われて、未来を人質に取られているような感じがしました。
◼︎てんかんによる転倒への恐怖
夏目 発作がおさまる前は本当にいつ倒れるかわからないから、二人体制で、一人は倒れても必ず支えられる場所に常についていて。骨折や歩けなくなるかもしれないことへの恐怖が常にあった。手術をすることで、てんかんをなくならないけど、転倒を減らせるということが魅力的に聞こえた。
ササキ 骨折前のことを知っている身からすると、かつてのようにたけしさんとある程度距離を取ってゆったり過ごす関わり方ができなくなっていることのしんどさがあるよねという話をしていました。
◼︎手術について誰と考えようとしたのか
尾張 手術について考える時に誰を呼ぼうという候補は挙がってたんですか?
ササキ テンギョーさんとか、こうやくんとか、ヘルパーではない人たち。
◼︎周りの人の対応能力でてんかん発作が持つ意味が変わる
西川 精神科にいた時もてんかんの患者さんが何人もいましたけど、看護師は常に一緒に歩いたりはしません。てんかん発作が起きた時にどう対処するかは習得しておくんですけど、てんかん発作を起こさないように、というのは不可能なんです。てんかん発作があっても、それに対処できるかどうか。
要するに、周りの人の対応能力によって、てんかん発作が持つ意味、暮らしに及ぼす影響が変わってくるわけです。てんかん発作の後の事故で死ぬことはありうるんですけど、てんかん発作そのもので死ぬことはないです。事故を防ぐ方法はいくらでもあるんです。でも、てんかん発作をなくさないといけないと医者もついつい説明してしまうので、問題を医療化してしまうんですね。
◼︎医療者は介護的なセンスを、介護職(ヘルパーも)は医療的なセンスを
西川 医療と介護の専門領域をあまり分けすぎない方がいいと思っています。医療者も介護職的なセンス、つまり暮らしの視点を持つべきですし、介護職も医療的なセンスを持つべきなんですよ。医療者も介護者もそれぞれできることがあるわけで、そういうものをお互いがどれぐらい日常的に話し合っているかっていうことがすごい大切です。医療と介護をきっぱり分けてしまうと、その両者の間で患者さんがこぼれ落ちてしまう。例えば血液透析の時、機会の面倒を見る技師と患者の面倒を見る看護師って別れてしまうと、血液透析の様々な問題が両者の間に落っこちちゃうんです。だから両者は手を繋がないといけない。両方とも専門性の高いことですから同じようにはなれないですけど、お互いがセンスを持ちながら協力する、相手がやっていることを理解するということはできるはずです。
そして、医療者が介護のセンスを持つのは非常に難しいです。頭でっかちになって医療のことしか考えないように専門家として育成されていますから。医療者の意識改革も大切ですけど、本当は介護の人たちが医療的なセンスを持って、ちゃんと話をできるようにしなくちゃいけない。ヘルパーも、医療的な問題をヘルパーの領域じゃないと思うかもしれないけど、ちゃんと勉強する構えを持つことはすごく大切なこと。
夏目 医療は体の状態を良くするというゴールがあるけど、暮らしはゴールがなく、何が良い状態なのか分からない状態。だから思考回路が全然違いますよね。
◼︎一つの専門分野の知識で暮らし・人生に対応することはできない
西川 訪問介護だったら、訪問先の冷蔵庫の中にあるものでご飯を作らないといけない。愛での好きなものは何かとかも知っておかないと食事を提供するってことはできないんですよ。だから、訪問介護やヘルパーが関わる暮らしは一つの専門分野の知識でなんとかなるものではないんですよ。それこそ人生が入ってくると、人生は様々な困難とか経験を積んできた人にようやくぼやっと見えかけるみたいなものなので、医学の知識を頭に叩き込んだところで何の役にも立たない。
◼︎自分の人生への感覚を頼りに相手の人生を豊かに想像する感性
西川 たけしさんがたけしさんの人生についての1番の専門家なんですよ。彼は言葉や文章にはしないかもしれないけど、様々な影響と取り組みながら生きている。そういう人と関わっていく時に、相手が見ているはずの青空とか透き通った風があるかもしれないということ、てんかん発作ばかりの人生ではないということを、豊かに想像できる感性も大事だと僕は思います。
その時に一番頼りになるのは、自分が人生についてどう感じているかということじゃないですか。自分自身の人生にイエスと言えるのはどういう時か振り返る。僕も看護師として様々な患者さんのしと出会ってきて、助けられなかった悔しい思いもいっぱいありますけど、今自分が病気になって、あの人たちが残してくれていったものが自分の支えになってます。だから、ケアって相手に何かをするだけじゃなくて、実際は相手から本当に様々なもの、人生の贈り物をもらっているはずなんですよね。たけしさんと過ごすことで自分はどんなものをもらっているのかを考えることが、たけしさんの人生の意味を明らかにし、人に伝えられるものにしていくんじゃないかなと思います。
尾張 アルスノヴァで働いている人は自分のやりたいことしかやらない人が多いと思うんですけど、たけしさんもやりたいことをやり切る、やりたいことに真っ直ぐなところがあって、そこは共感するというか。自分のやりたいことができなかったら死んだも同然と思ってしまう。骨折した時に、たけしさんがいなくなってしまったらどうしようという恐怖がありました。
◼︎大変さのラベルをつけるのではなく、生きる力に感動する
西川 自分も末期だとわかって検査に対して恐怖や不安、将来に半ば絶望しかけた時もあったんですけど、とある看護師さんから「どんなふうにしても恐怖や不安は消えません。ただ時間は過ぎます。」とメールが来たんです。それを希望に眠りについたわけです。翌日、目が覚めたら、やはり息はしているし、脈は打ってる。この時、「俺の体は生きている。あんなに恐ろしかったのに、心臓は縮むのではなく打っている。」と、生きる力はすごいなと思った。その時から、余命告知など、医学が様々に語る予測値の悲惨さを、「生きている間は生きている」と受け入れられるようになったんです。
たけしさんも、外側から問題のラベルをつけることはいくらでもできるが、本人は石を鳴らして今日も生きている。その姿とか力に感動する。それを忘れて、てんかん発作をどうするのかということだけに焦点化して議論すると、大切なことを見落としてしまうかもしれない。
◼︎てんかん発作をダメとするのは優生思想ーてんかん発作があっても暮らしや人生を充実させることができる
西川 てんかん発作がダメだというのは優生思想です。てんかん発作と共に生きるという社会のあり方もよしとしないで、医学的に対処可能なものは対処すべきというのは、優生保護法的な考え方なんです。医者の言うことはどっかで優生保護法的な考えがあるかもしれない。医療的センスは必要ですけど、価値観や倫理は医師が必ずしも優れているわけではないです。下手すると、優生保護法的な圧政的な立場に変わるかもしれない。だから、てんかん発作があっても暮らしや人生を充実させることができることを、医学とは違う方策で、ヘルパーの世界で作り上げていくことが大切かなと思います。
◼︎ご飯を食べることにまつわる困難・悩み
櫻井 脳梁離断の話が出た時に、僕はたけしさんの発作のことは知ってはいた。ご飯を食べないと薬が飲めないことに、ご家族も先輩スタッフも悩んできていて、僕もそれにすごく縛られてしまっていた。たけしさんに「食べないといけないんだよ」と強いているところはすごくあって、ウルトラを始めた当初、3年くらい苦しかった。でも、やっぱりご家族の言葉は最強。薬が変わって、ご飯を絶対食べないといけないという縛りがちょっと緩くなった。関わりは…まあまだ2割くらいしか楽にはなってないけど。結局、まだ食べないといけない。
西川 食べることに関しては認知症の場合でもよくある話。胃瘻にすると口から食べることが終わってしまうんですね。食べる能力が落ちると食べることができなくなるんで、命のために胃瘻にするかどうかは家族が判断するんですけど、みんな悩むんですね。それで胃瘻をしたとしても、あれで本当に良かったのかと家族はずっと悩むんです。認知症の飲み込む機能が衰えた方の食事介助で目の前で窒息死ということもある。その場合は仕事を続ける自信がなくなってしまう。でも、医者はそうなる前に胃瘻をすべきと言うんですよね。
◼︎死んだら人生は終わりなのか
夏目 暮らしや人生のベースに健康があるのではと思いませんか?
西川 そうすると優生保護法的な考え方になっちゃう。
夏目 そうですよね。でも命が維持できなかったら人生がなくなってしまう。
西川 人生は死んだら終わりか。僕はその辺りの考え方が最近変わってきている。死とは何か。死は全てを無にするのか。死を避けるだけで人生は充実するのか。いや、多分違うんじゃないかな。死んだら人間は価値はなくなるのか。人生の価値って一体どこにあるのか。こういう人の命と関わる仕事って、やっぱり死生観に辿り着くわけですね。そういうところまで付き合わないと、ケアに付き合ったことにはならない。
尾張 自分は死んだって人生終わりじゃないって思えるかもしれないけど、それをたけしくんに勧めようとは思わない。健康じゃなくったっていいじゃんとは言えない。
西川 もう一つは、人為の世界に「死」が入っているかどうかなんですよね。人がコントロールできるところに生や死はあるのか。あるべき命のあり方が医療的な健康という話に行ってしまうとかなり危ない。障害や病気はない方がいいものになってしまう。
◼︎てんかんが医療の側にあって社会にないから恐怖の対象になる
来場者 てんかんを起こしたらダメなのかという話がありましたが、骨折などが予想されるのなら、コントロールできるなら絶対したいと支援者の方は思うだろうなと思うんです。てんかん、ダメじゃないんですか。安全ということを考えると、歩いている目の前にどんどんマットレスを引きたいみたいになっちゃう。
西川 そしたら、歩くな、動くな、ということになってしまう。
来場者 それにすごく葛藤しています。電車で目の前の女性がてんかんで倒れてびっくりしたことがあったんです。
西川 てんかんがそれだけ、医療の側にあって社会にないということです。てんかんに対する社会の人たちの理解がなく、単なる恐怖の対象になっちゃうんです。障害でもそうです。障害のある人と付き合いがない人は怖いから、なんとかコントロールして排除する方向になっちゃう。てんかん発作も慣れてきたら、なんてことはないわけです。
◼︎転倒の心配によって関わり方が制限されてしまうことへの葛藤
ササキ おっしゃられたように、発作は大丈夫なんですけど、でも転倒はしてほしくないよねという話し合いをして、転倒がなくなるなら手術はする意義があるかもしれないという話をしました。発作とか何でもかんでもコントロールしたいわけじゃなくて、転倒っていうところなんですけど。「座ってて」というのも言う側も言いたくて言っているわけではなくて、もっとお互いに自由になりたいはずなのに、転倒を心配するために関わり方が一様になってしまう。お互いにハッピーじゃない。関わる側とたけしさんがどうしたら一緒に幸せでいられるのかを考えたいねという話をしてました。
◼︎悪いことではなく、良い方向を考えて努力する
西川 安全を第一に考えたら、様々な制限が次から次へとやってくるわけです。不安は消えないんでね。悪いことを考えると悪いことばっかりになってしまう。そうではなくて、良いことを考える。良い方向に努力するのか、悪いことが起こらないようにビビりまくるのか。これは価値観というか、人生の生き方ですよ。だから、良い悪いはないのかもしれません。それぞれが決めること。でも、ついこれが正しいと言いたくなっちゃうんですよ。異なる意見の持ち主同士が話し合うべき。黙って我慢してしまうのが一番危ないんです。
◼︎管理責任よりも応答責任
来場者 お互いがハッピーになれないと思うのは、自分の側が責任を負おうとするからですよね。その責任は一体何なんだろうなと思いました。
西川 責任には、管理責任と応答責任の2つがあるんですよね。みんな管理責任の方を考えてしまうんですけど、本当に管理できるのかっていうことです。管理不可能なものを管理するのは、無理なことをしないといけないということ。
◼︎先見の明ではなく後知恵が評価されるべき
西川 もう一つ思うのは、先知恵というか、計画を立てろ、起こりうる事柄に対してあらかじめ対処しなさい、先見の明を持ってケアに当たれと言われるでしょ。医療でも、将来・未来を良くするために治療をする。未来を読み解く力を求められるわけです。でも、人生で大切なことは大体後になってわかる。その後知恵が高く評価されていない。先見の明は専門性が高いですけど、一旦計画を立てて決めたら安心しちゃう。工夫や努力が続かないです。一方で、後知恵が評価されれば、試行錯誤をして、失敗から学ぶことができるんです。でもその代わり安心し切ることはないです。
来場者 計画性の一つのポイントとしては、同じ方向を向くということはあった方がいいと思うんですよね。やってみたけどこうやった方がいいか、うまくいったから継続しようとか、いろいろと変えてみるのはその場での判断だと思うんですよ。そういうのは永遠に続くのではないかなと思います。
西川 計画は非常に専門知を要求すると思うんです。そしてその根拠を理論的に説明しないといけない。一方で、後知恵は実践知なんです。自分たちの経験の意味を検証していくことです。てんかん発作を起こさないためにはどうするかという未来予測に対する対処は専門的な知識でないと建てられない。でも、でんかん発作が起きた時にどうするかというのは、様々な工夫をしてみた実践や経験が少しずつ知識に変わっていくということ。
そういう意味で、介護は日々変わっていくものです。その中で大切なのは後知恵、試行錯誤や失敗から学ぶこと。実践が積み上がっていき、知恵が強くなるんです。先行知の場合は、評価はしますけど、うまくいかなかったときにもう一度計画を立て直すんです。やはり先知恵になる。計画ではずっと未来に対する対処に重点が置かれるということです。特に介護は後知恵を充実させるのが大切だと思います。
意思決定支援会議で前向きなプランを立てるという方向で議論をするのでは、やはり専門家優位になってしまう。専門家優位のガイドラインができ、専門家以外は入る余地がない現場になってしまう。
◼︎医療は科学的な問題解決技法、介護は問題解決ではなく課題達成型
来場者 先知恵は専門的というか、科学的というのかな。科学的実験のように再現が可能なもの。
西川 そうですね。法則のもとでやっている因果関係。
来場者 そういう科学的なものを前提にして人生や暮らしを設計するのはありえないことだなと思います。そのありえないことをやろうとしている気がする。
西川 その問題の原因になったものは何か、問題の因果関係をどこで介入して断ち切るのかというのが科学的な問題解決技法なんですね。介護は問題解決ではなく、課題達成型。どういう人生を送りたいか、どういう希望があるか。おそらく医療は問題解決がすごい強いと思います。でも介護の世界というのは、問題解決に走るより、人生を豊かにするにはどうしたらいいかという課題達成型のアプローチの方がいいんじゃないかと僕は思うんですけどね。
◼︎今回の会議の振り返りー身内だけではないからこそ意思決定ではない話に
尾張 今回の会議はこういうスタイルにして良かったです。昨日も「私の」ではなく「私たちの」という話をしたが、全然知らない人も話していくうちに「私たち」に入っていくというか。たけしさんの周りの人たちが広がっているような気がしました。意思決定を完全に身内だけでやらない。
西川 完全に身内だけでやったら、意思決定の話ばっかりになると思う。いつの間にかそういうことじゃなくなったのがいいよね。
尾張 たけしさんの意思決定だからこういう話題が出てきたのかなと思って。他の人だったら、またちょっと違う形になっただろうと思うので、他の人でもやってみたいと思いました。
来場者 意思決定支援会議ということでやってきたけど、意思決定の話じゃないなと思った。
支援する人たちが彼の人生にどう関わるのかという話。彼の意思をどう把握するのかという話はほとんどしていない。でも、結局そういうことなのではないかな。彼が自分事として何を考えているかは分かりっこないわけで、結局、関わる人たちの関係の中でできることしかできないですよね。
◼︎相手が見ている世界や自由の考え方
西川 今日考えたことは大切なことだと思うので、ぜひいろんな場所でいろんな人ともう一度考えてみてほしいです。僕たちは病気や障害を持つ人たちに対して変な哀れみや同情を持ってしまいがちですけど、相手はそんな世界を見ていないかもしれない。
夏目 誰と付き合うにしても、自分だったら大変だろうなぁ、嫌だろうなぁというところからしか話せない。
西川 「自分だったら」という価値観がいかに狭いか、いかに固いか。「自分だったら」という言葉は怪しいです。自分はそれほど大したものじゃない。
夏目 「一般的には」というよりはいいかなと思ってたのに。
尾張 そうしたら何を道筋にして判断していったらいいんだろう。
西川 それこそ自由というものは何か。セルフコントロールできることが自由。でもセルフコントロールをしないという自由もありますよ。全部人に預けてしまう。世界から全て享受する。他者と共に生きるというときに、自分をできるだけ開いて、できるだけ他者を歓待する。そういう生き方はセルフコントロールとは真逆になる。みたいなことを議論している哲学者もいるので面白いよね。でも片一方で、自分のことは自分でしなさいという、自立やセルフコントロールに価値があるとする価値観もあるわけです。見方を変えるだけで、どちらがどうだという議論ではないですね。
尾張 皆さん、すごいモヤモヤされたんじゃないかと思うんですけど、それをぜひ持って帰って考えていただけたらと思います。