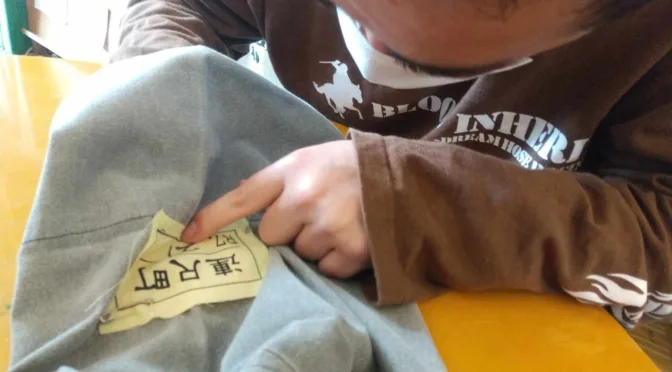![《寄稿》第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1458-scaled.webp)
《寄稿》第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]
福祉の担い手とは、いったいだれのことを指すのか
文:小松理虔
クリエリティブサポート・レッツが主催するダイアログのイベント「ひとインレジデンス」に参加するため、2024年11月、久しぶりにたけし文化センター連尺町を訪れた。浜松に来たのはいつ以来だろうか。少なくとも2年近く訪問していなかった気がする。みんなぼくのことを覚えてくれているだろうかと少し不安な気持ちで扉を開けたのだけれど、やっぱりたけぶんはたけぶん。久しぶりに会う人たちがみな「久しぶり!」と声をかけてくれた。中には初めて会う人もいた。あいさつを交わしたり、交わさなかったり、でも、ぼくがいるということはなんとなく受け入れてもらっているような気がして思わずうれしくなった。
ぼくにとって「たけぶん」は特別な場所だ。1年近くのあいだ定期的に通い、多くの時間を過ごした。そこで見聞きしたもの、感じたことを書き綴ったものは、『ただ、そこにいる人たち』という本にもなった。それを読んだ人からぽつりぽつり感想が寄せられることが増え、福祉に関するさまざまな仕事に関わらせてもらえるようになった。ぼく自身はまったく福祉の専門家ではない。知識もほとんどない。だから、これまでに経験したことを組み合わせていくほかないのだけれど、頭にあるのは、たけぶんに通っていたころに学んだこと。たけぶんで過ごした時間は、いまのぼくの「地域活動家」としてのさまざまなアクションにつながっている。だからこそ、久しぶりのたけぶんで、みなさんと、そして理事長の翠さんとじっくりとお話しできる機会は、これまでの自分の活動とレッツで学んできたものを重ね合わせながら振り返る、そんな時間になるだろうと思えた。
全人的に向き合うこと
ひとインれじでんすで、翠さんとひとしきり話したことが、レッツが目指してきたものが少しずつ認められ始めているのではないか、ということだ。たとえば、人の背景にあるものをぐるぐると遠回りしながら探っていくこと。明確な答えのない日々の現場に、おもしろく想像力を発揮して立ち向かっていくこと。現場からラディカルに専門性を問い直していくこと。
あえてレッツ以外の話をしてみたい。いまぼくは、自分の地元、いわき市のかしま病院というところで、医学部生が参加する地域医療実習に関わっている。かしま病院では週に1度、医師ではなく地域住民から地域医療を学ぶ時間を設けていて、そこで講師を務めているのだ。学生たちと、まちを歩く。鹿島町がどのような歴史や文化があるのか、どんな風景が広がっているのかを実際の目で見ながら、暮らしを想像する、そんなプログラムだ。
高齢化が進み、今後はますます訪問診療が増えていくと言われている。病院だけで事が済むわけではない。医師にとって医療の主戦場が、病院から地域、誰かの自宅へと移り変わっているのだ。患者がどのような家に、どのようなスタイルで暮らしているのか。「暮らし」への想像力がますます問われていくことになる。さらに、その患者の家族構成、近所づきあい、地域の特徴など環境・社会的な側面に加え、病気をどう恐れ、あるいは恐れていないのかという感情面にも関心を持つ必要もある。けれども、そうした目線は大学内や病院内だけでは獲得しにくい。だから地域に出ていこう、地域の人たちと一緒に学ぶ場をつくろう、というようなプロジェクトが始まったのだ。
こうした地域医療の現場で必要とされるのが「全人的医療」の考え方だ。特定の部位や疾患に限定することなく、患者の心理や社会的側面も含めて考慮し、個々人にあった総合的な予防・診断・治療を行うものである。こう書くとすごく医学的な言葉に聞こえるかもしれないが、要するに、「疾患の背景、個々人の背景を含めて診ていこう」、「その人をそうさせているものを探ろう」とする医療である。
かしま病院の医師から初めて全人的医療について話を聞いたとき、ぼくはすぐにレッツでの日々を思い出した。なにか突拍子もない行動をしてしまったとしても、その行動を責めるのではなく、一旦責任を棚上げして、その行動をせざるを得なかった理由、背景を探ろうとするのがレッツのスタッフだったからだ。レッツに通ってくる人たちは、その理由を口頭でうまく説明できない人がほとんどだ。だからこそ、スタッフがひとつひとつ行動を検証し、行動から読み取れる心理や状況をみんなで考察していく。そして、自分たちの振る舞いを省みながら、新しいアプローチを考えていく。そんなレッツの現場に何度か立ち会ったことがあったから、ぼくにとって「全人的医療」という概念は、とても「しっくりと」きた。
全人的という言葉を「全体性」と変換してもいいだろう。個々の疾患だけでなく、それを統合する「その人全体」を診るということだ。たとえば、複数の疾患を併発している高齢者の患者さんがいるとする。それぞれの専門医が役割分担して、高血圧症とか糖尿病とか脊柱管狭窄症とか、それぞれの病気を治そうとすると、結果的にその人が飲む薬が膨大になり、クリニックに通う回数も増えてしまう。治療そのものが「暮らし」や「その人らしさ」を傷つけてしまうということだ。
その患者を「全体的」に捉えていくと、個別の疾患ではなく、その人が、全体としてその人らしさを発揮できる状態を維持することが大事になってくる。薬をたくさん飲み、毎日のようにクリニックに通う日々を送るのでなく、疾患によっては薬を減らし、場合によっては病気とともに生きるという選択をとり、クリニックに通う時間を減らして、仲間と過ごすことができる場や趣味に没頭できる時間を処方しようとするのだ。疾患だけ診ていたら、その人がどういう人生を送りたいのかもわからない。だから、徹底して人に向き合い、その背景を慮って想像する力が必要になってくる。キュアだけでなく「ケア」を実践するための力を、これからの医療人は育んでいかなければならないということなのだ。
ケアの担い手はだれなのか
最近では、「社会的処方」という言葉もよく耳にするようになった。「孤立」や「孤独」がもたらす健康被害が、さまざまな領域で検証されつつある。孤立のもたらす健康被害は、1日にタバコを15本吸うのと同じくらいになるという試算もあるそうだ。社会的処方とは、医療的な処置だけでなく、地域活動など社会参加の機会を提供し、患者の健康や生活の質を向上させる取り組みのことを指す。こうした活動に関心を持つ医療従事者も多く、ぼくの関わっているかしま病院でも、具体的なアクションを生み出そうと、社会的処方を専門とする医師などを招いて学ぶ機会をつくっているところだ。
社会的処方をぼくなりに一言で言うと「仲間を処方すること」になる。人はつながりのなかで自分を癒し、生きていくもの。手術やリハビリ、薬も大事だけれど、人とのつながり、仲間との出会いも必要であり、仲間たちの存在が、その人らしさを発揮できる状態にする「土台」になっていくということだとぼくも思う。社会的処方があちこちで語られる今、ようやくそういう価値観が科学的にも認められつつあるということだろう。
社会的処方を実践していくには、医療や福祉の人間関係の外側にも患者のつながりがあることが重要だが、その前提として、そのつながりを処方できるネットワークを、医療や福祉の担い手自身が持っていることも欠かせない。これをレッツに当てはめると、レッツの施設に通ってくる利用者が、レッツの職員だけではなく、その外側にも出会いの場を広げられる場があること。そして、その場を法人自身がつくり、さまざまな担い手とつながるネットワークを保っていくことが大事だということになるのだが、レッツの皆さんは、もうやっていた。
そもそもぼくは、レッツの手がける「観光」の取り組みを通じて施設に通うようになって友人が何人もできたのだし、「ちまた会議」に参加して、法人内外の人たちと語り合い、地域と福祉のあり方に思い馳せた。駅前の空き地で壮大に開催された「オンラインクロスロード」では、みんなが混じり合う心地よさを感じることもできた。それらはまさにレッツによる社会的処方の取り組みだったといえなくもない。
全人的医療も、社会的処方も、当事者性や専門性の「外側」にある人が鍵を握る。だが、「外側」といっても、単に施設や病院の外側にいるだけで、多くの人たちに当事者性があり、皆それぞれに専門性を有しているとも思う。地域の専門家、おしゃべりの専門家、おせっかいの専門家や家庭菜園の専門家がいるし、それぞれに、なんらかの健康課題があったり、家族内の問題があったり、悩みがあったりする。その人ならではのさまざまな当事者性、専門性が発揮される場所がだれかの居場所になることで、社会的処方は成り立っているとぼくは考えている。
ひとインれじでんすでも、翠さんと「専門性」の話になった。翠さんはこう語っている。「専門性をもう一回問い直した方がいいかもしれないですよね。福祉に関しては、保育、高齢者、障害にしても、専門家が当事者を見るとなっているんだけど、それは要するに、その人たちに押し付けているのと同じなんです」。
詳しく知らないから、自分とは関係がないからと無視を決め込むパターンもあるだろうけれど、関心がある人にも「当事者に迷惑をかけてはいけない」「まちがったことをしてしまうかもしれない」「専門家や当事者のほうがいい」と関係を避けてしまうパターンが少なくない。「正しく関わりたい」と考えるほど、自由さが失われ、逆に関わりが狭くなってしまうのだ。これは、そのほかのさまざまな社会課題にも当てはまるかもしれない。
専門家と当事者にだけ任せておけばいいわけではない。専門家や当事者が語っていることだけが正しいわけでもない。専門性や当事者性を尊重しつつも、私たちが持つ専門性や当事者性も一緒にひらいていく。そこに、次の担い手も生まれていくはずだ。ぼくたちは、専門外ゆえ間違うかもしれないし、修正を余儀なくされるかもしれないけれど、そのたびに修正を図り、変化を受け入れていくことが大事だ。ワクワクしながら学び、実践を続ける。多様な人たちとともに「現場知」を積み重ねていくレッツに、これからも「共事」していきたい。