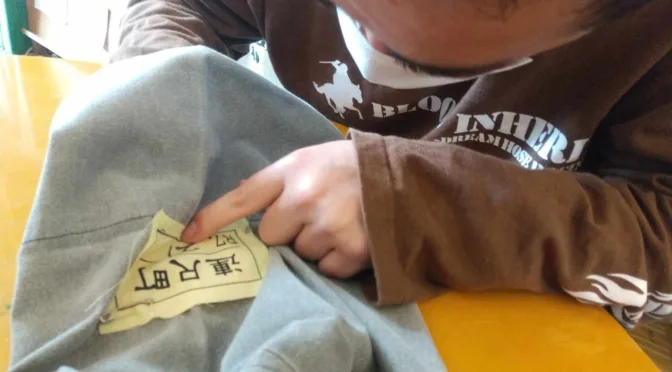![【スタッフ所感】第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1458-scaled.webp)
【スタッフ所感】第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]
第7回 ゲスト:小松理虔(地域活動家)
久保田翠(認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)
「ただそこにいる人たち」その後~共事者と専門性、そして共助
小松理虔さんとの出会いは2016年にさかのぼる。
小松さんが著した「新復興論」を読んで、震災・原発といったなかなかアンタッチャブルな課題に、一人の市民として書き進んでいる文章に感銘を受けた。特に最後の「アート」についての文章が、いわゆるアートプロジェクトと言われるものが何のためにやっているのかなかなかその意味を伝える難しさを感じていたが、理虔さんの自然なわかりやすい語り口は非常にわかりやすく、同時にアート関係者の視点とは違っていた。そして、ぜひこの人にレッツに来てもらいたいと思った。
それが実現したのは、丁度コロナ前の2018年6月頃。毎月1回、私たちの拠点である「たけし文化センター連尺町」や障害者施設アルス・ノヴァに来訪いただき、3階のゲストハウスに滞在してもらう。そして、「この場にある「表現未満、」を体感し、感じたままに文章にしてほしい」とオーダーした。コロナが始まりつつあった2019年3月に報告書としてまとめ、さらに2020年に「ただそこにいる人たち 小松理虔さんの表現未満、の旅」として現代書館か出版された。
それから理虔さんとは、レッツがコロナ禍後に始めた「浜松ちまた会議」や「まちづくりを考えたら福祉にたどりついた」と銘打ったシンポジウム、報告書、タブロイドの発行などにもご協力いただいている。
今回「新しい価値創造」というテーマの中で、障害のこと、原発のこと、コロナ禍のことを今一度理虔さんとじっくり話をしてみたいと思った。
障害と原発と文化
理虔さんが福島県いわき市に在住しながら、震災や原発を見続けながらそこに生きる人たちの機微や生活を通してずっと考え続けている姿と、重度障害者のたけしが生まれ、そこから、彼や障害の人たちとともに生きながら障害や地域、街、暮らしを考えている私とはとても似ていると思う。
生きていくことは生活していくことだ。人はいつまでも悲観にくれてはいられないし、現場にいればその厳しい現実を突きつけられる。しかし、私たちはそれでも、ご飯を食べ、働いて、寝て、活動して、そうやって生活は連綿と続いている。そうした中で、ずっと考え続けるといった行為をあきらめない。
もちろん運動や政治にしていく人もいる。しかし私は、白黒はっきりつけることもなく、わかりやすく要約することもなく、答えを請求に出すことをせず、わからないままに考え続けることも必要だと思っている
理虔さんは、その時々の事象を本に著すといった表現力がある。なるべく平易なことばにかみ砕き、優しい文章にしながらも、この根底にある「わからなさ」「危うさ」を引き取っているように思う。そしてこれが文化のできる技。文化はまさに私たちが生きのびるためにあるのだ。
自分の中の障害性
人はだれかが困っている時に助けたいと思うものだ。それは人間の良心でもある。しかし、その「助ける」といった行為には暴力性もはらんでいることを忘れてはいけない。助ける人と助けられる人が固定化した時に、それは暴力にもなる。小松さんは「自分が他者に対して開かれているかどうか」「世の中にいろいろな人たちがいる。その中に自分は含まれるのか」。そして、自分の中に誰もが抱える、生きにくさ、弱さに向き合うことでもある。そうした人たちと接しながら自分の中の障害性や弱さに気が付く、向き合う機会にもなる。一方的に施しを行う硬直した関係ではなく、均等に対峙した時に、そこから想像力が生まれる。そんな関係性を私たちは望んでいる。
共事者と専門性
「ただそこにいる人たち」の中でも提示された「共事者」について、小松さんは、「思わず〇〇しちゃった」といった、そうするつもりでかかわっていたのではないが、後から考えるとそれが支援にも、誰かを助ける行為にもなっている。といったある意味予想外の行為者として「共事者」をとらえている。それは寄り添うわけでもなく、何か目的をもってかかわるわけでもなく、「ただそこにいる」。それならば、専門家や家族といった人以外でもかかわれる。そうした余白みたいなものが社会全体にも必要だという話に及んだ。
福祉の現場において、支援者、施設長、専門スタッフ、看護師、医師といった肩書はもれなく専門性とフィックスしているしその役割も必要である。専門家が「共事者」的な感覚をもちながら仕事をする。あるいは専門職で固められた現場に全くそうではない人が入り込み、その人たちが自由にふるまうことで、支援自体が豊かになっていくといったトリガー的な存在としての共事者をとらえる。
しかし、一方で専門性とは何なのか。福祉の現場において専門性はより必要なのではないのかといった議論にも波及していった。
私は29年重度知的障害のある息子たけしの介護を続けてきた。彼がどのような状態なのか、今何が必要なのか、体調が悪い時どうしたらいいかなど今までの知識と経験で即座に対応できる力は育っている。ある意味、たけしの専門家であろう。しかし、たけしの人生は私のような専門家が寄り集まったところで、幸せはやってこないということも実感している。人は人と出会い、人とかかわることで生きている。
だからこそ、支援者がむしろ「共事者」となり、縦横無尽にいろいろな発想を提供するべきだと考えてきた。しかし、今回の議論を通して、果たしてそうだろうかと考えるようになった。
最近のたけしは、てんかん発作、薬の副作用による食欲不振、下痢、それに伴う体調不良と、ひと時も目が離せない状況にある。そうした中でやはりたけしの専門性はより必要になっていく。だからと言ってそうした健康を第一義とした支援は、味気ないものになる。その時にスタッフの振る舞いや心持として、この専門性と共事者的な発想両面を持ち合わせることは意外に難しい。
そうであるならばやはり、それぞれを切り分けて担っていくべきなのかもしれない。つまり常に共事者的な人びとを招き入れながら、スタッフはより専門性を高めていく。この両輪で支援を組み立てていくといった方法もあるのではないかと気づかされた。
とかく専門家が重宝されるし、専門性に対価が支払われる。しかし、ケアも、社会構造も人がかかわる以上は、エラーや誤配、勘違い、うっかりといった行為がないと本当に窮屈なものになってしまう。
これからの福祉、街づくり、社会づくりは、専門家にお任せすればいいのではなく、私たちが素人、共事者として気楽に、うっかり参画していくことが大切なのだろう。そしてそれが共助なのだと思う。