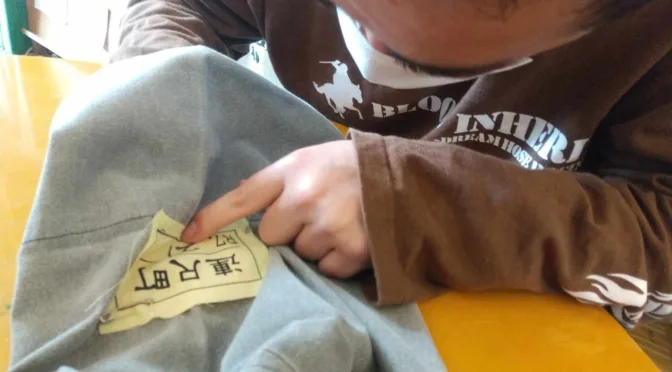![〈トークまとめ〉第1回 ゲスト:岸井大輔さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/05/IMG_0734-scaled.webp)
〈トークまとめ〉第1回 ゲスト:岸井大輔さん [ひとインれじでんす2024]
トークテーマ:「共有することは可能か?暮らすこと、共に居ること、」
レッツにあった高い椅子
瑛:「ひとインれじでんす」の第一弾として、劇作家の岸井さんをお呼びしました。岸井さんと初めて出会ったのは2010年頃だったと思います。15年近く、レッツの活動を定期的に観察しに来てくれる岸井さんに今日は、「共有」をテーマにお話いただこうかと思います。
岸井:僕が最初にレッツに出会ったのは、「たけし文化センターBUNSEND(2010)」の前を通りかかった時です。

なにか面白い場所があるなと思って入ったら、テニスの審判台とかの高いイスがやたら置いてあったんですね。で、ここは一体なにか、と、その場にいたメガネの男性スタッフに聞いたら、この場所は、たけし君(重度知的障害がある久保田壮さん)がみんなと一緒に居れる場所を作りたいと思ってこうなったんです、と言うんです。意味が分からない。
お客さんにお茶を出すと、たけし君はお茶を倒してしまう。そうするとたけしと一緒にいれない。じゃあ、お客さんがたけしの手が届かない高い椅子に座って、お茶を飲めるカフェを作ったらいいんじゃないかと考えて、あちこちに頼んで高い椅子を集めたそうなんです。ところが、集めた椅子にたけし君は登れるので、高いイスがあっても意味がない。じゃあどうしようと。彼がお茶を倒しにきたら、お客さんは自分のお茶は自分で持てばいいだけじゃないかといいうことに気がついた、というんですね。これでたけし君と一緒に居れるじゃないか、ということになった。集めた高い椅子はもういらない。だけど、面白いから椅子は取ってある、と。
僕は割と日本中の面白い所に行っているんですが、こんな面白い話はめったにないなあ、と思いました。高い椅子が10脚以上あって、でもそれは実は全て無駄ですっていう。頑張って椅子を集めたのに、使っていない。その椅子が普通においてあってその失敗が共有されるカフェ。
瑛:ちょうどたけし文化センターBUNSENDOって今空き地になっている場所なんですけど、看板だけ残ってますね。元本屋さんの跡地で、私たちがまだアートNPOで障害福祉サービス事業をやってなかった2010年代時に、スタッフのアーティストがオルタナティブスペースを作った一番最初のきっかけとなるような場所です。そこにきていただいたんですね。
岸井:面白い場所は偶然見つけます。
瑛:それから14年ですかね。今回は岸井さんをお呼びして、私たちが考える「共有」というのを考えたいなと思います。
共有は「やること」「話してもしょうがない」
岸井:共有をテーマにいただいて、少し困りました。というのは共有はやること。話すことじゃないんですよね。
例えば、自転車に乗ることを考えてください。自転車の乗り方について訳知り顔に話しても、自転車に乗れなかったら、自転車の乗り方についてわかっていない。じゃあ自転車に乗れる人は自転車の乗り方を説明できるかというと、そんなことはない。
共有はそんな感じです。まず「やること」。実践なので話しても上手くいかないことが多い。
他人と一緒に暮らすことを考えてみましょう。子供のころ、家を親と共有していた。個室はあっても水回りとかは共有されます。面白いのはピカピカな水回りが必ずしも共有が上手くいっているサインではないということです。使われてないのでピカピカということもある。ルールがちゃんと決まっている、というのも仲が悪いからということもある。共有が上手くいっている水回りは、散らかっていて、ルールも不明で、なんとなく嫌な思いはみんなしているけれど、あんまり困っていない、なんてことが多いです。
共有毎に、その共有の何がいい感じなのかは違います。一般化もできません。よい共有の方法が一般化できるなら戦争とかはもうないはずですから、正解が全くない。
私たちは何かしら「共有」している
岸井:共有は実践の問題というと、自分は共有をやったことがないので、今日の話は自分とは関係ないと思うかもしれません。ですが共有をしていないということもあり得ないんです。例えば道路とか空気とかを私たちは共有している。今日はトークイベントですからトークを共有できる前提でそこにいらっしゃいます。共有しているものは沢山ある。
じゃあどうやって共有しているの?なんであんまり困らずに共有できているの?といわれても上手く説明できないと思うんですよ。上手く説明はできないけどみんな何かしら「共有」はしています。
私たちは何かしら「共有」している。そして共有は個別的で、やることで、一般的に説明してもしょうがない。なら話す必要はないのかというとそうもいきません。
というのは、共有が上手くいかないときになされることこそ「話し合い」だからです。というか、よく考えてみると、人間がかかわる問題のほとんどは共有の問題です。なので「共有について話せ」といわれても困るわけです。あまりにでかく、具体的で、繊細。
ドラマとは共有の失敗
岸井:とはいえ僕は劇作家なので「共有」に興味があります。というのはドラマとは「共有」の失敗のことなんです。ドラマで良く描かれる、夫婦喧嘩とか殺人事件とかは全部共有のトラブルでしょ。共有がうまくいかない当事者には誰もなりたくないけど、他人の共有の失敗を見るのは楽しいんですよね。
瑛:リアリティショーとか複雑なドラマですよね。
岸井:共有がうまくいかない状態を作ればドラマになってしまうんです。劇作家である僕はいつも共有をリサーチしているといってもいい。しかも共有を、面白いかつまらないか、かっこいいかわるいかの観点で見ている。
ドラマの専門家はいろいろいます。演劇は、ドラマを身を寄せ集まって共有する。演劇は共有の失敗を共有するんです。
「装置」で考える
岸井:今日は、共有を「装置」で考えるというアイデアを提案します。舞台装置とかの装置ですね。装置は「共有をいじる」ときに便利なんです。
共有について、実践の中で考えようとすると、掃除が雑だとか、感謝がたりないとか、態度の話になりがちです。演劇でいうと、演技の良し悪しの話になる。そうすると人間から切り離せないので喧嘩のタネになってしまうし、変更が難しいんですよ。ところが装置は人間と切り離して考えることができます。装置で考えるとうまくいきやすい。
「装置」はいろんな意味で使われる言葉です。福祉施設の制度、法律とか仕組みも「装置」と呼ばれることもありますね。今日は「装置」を広く捉えてみます。
瑛:文化やルールに近いもの、あらゆるものが装置化されているってことですね。
岸井:そうです。装置は、どこかに何かが配置されることで誰かの振る舞いに影響を与えます。例えば今トークイベントを始めるときにイスを並べましたよね。で、皆さんが座る。特に共有について考えずにできたと思うのですが、だからこのトークは共有される。イメージを考えたりするより、設置されている装置を考えた方が実践的です。人間は、他人と共有する時、いろんなものを装置にします。福祉施設は装置でできているといっていいでしょう。
夏目:逆に装置じゃないものってあるんでしょうか?
岸井:基本、万物は装置であるでいいと考えていいと思います。私たちは全てを装置扱いして共有しようとしている、それが人間の条件でしょう。
ただ、装置と捉えると、一つ一つの共有を取り出して考えやすい。イスも部屋も浜松もレッツも法律も装置ですが、装置としてみることで一つ一つの共有を考えやすい。だから装置は実践的に使うとよい言葉だと僕は思う。
たけしは装置を認識できるのか
久保田:私たちは装置を認識できるけど、レッツの利用者さんやたけしとかはそもそも装置を認識できないと思うんですよ。
岸井:いえ、そう思いません。それが装置と捉えるよさです。
というのも、階段とかイスと認識していなくても、そこにモノがあればぶつかったりよじ登ったりしますよね。装置は共有されてしまう。むしろ、たけし文化センターは、装置で考えるよい例だと僕は思う。福祉施設が多様な人たちと、いろいろ経験してきた結果、モノが具体的な場所に配置され、利用者さんとも共有している。
久保田:こちらは心地いいかどうかは全然わからない。こちらが思っている装置を提供していっても、どんどん上書きされて、上書きされるとそれがそのまま残る。そしてまた上書きされます。残って欲しいかというとそうではありません。
岸井:装置は誰かが提供したものでもないし、誰かが納得したものでもない。ただの具体的なモノがなんとなくそこにあって共有されている。
久保田:誰にとって心地いいかもさっぱりわからないです。
岸井:共有されているかと、心地いいとは別ですよね。装置が共有されているのは結果論。特に誰もそれがいいかは考えていない。現状使い勝手がいいだけでしょう。
久保田:使い勝手が良いところに落ち着いてるのかどうかもよくわからないんです。
岸井:そうですね。落ち着いているかはよくわからない。それも「装置」のいいところじゃないでしょうか。建設とか施設と違って、装置には仮設というニュアンスがある。だから変更も比較的容易です。
心地よさとか残したいとかで共有を考えるとレッツでは使えないんじゃないか。でも装置ならどうか、というのが僕の提案です。装置は共有の現状をとらえるだけです。装置を見ることで、共有が思考可能になるんじゃないかと思うのです。
久保田:同意は取れてるのかとか。
岸井:同意は関係ないんですよ。装置には誰も同意していない。
久保田:みんなが困っていないだけ?
岸井:そうです。いいとも思っていない。共有されてそこにあるだけ。
共有されているものの一つに慣習があります。右側通行とか。同意した覚えがないですし、心地よくもない。なぜ日本で歩行者が右側通行かというとそれで誰も困っていないだけです。
ただ、慣習は変え難い。慣習に問題があったら修正がききません。明日右側通行をやめるといわれても困る。
ところが装置にはそれができます。動かしたり壊したりすればいい。共有を変更する可能性がある。共有を考えるために装置を提案したい理由です。
まず、共有を装置で考える。次に共有のトラブルを装置の変更で考える、ということですね。
共有を変える・1「揉める」
岸井:レッツはいつも新しい共有の形を探っていると思います。そこで今日は共有の変更に参考になりそうな思想を三つ紹介します。
一つ目はジュディス・バトラーの『ジェンダートラブル』から「揉めろ」というアイデア。障害は、何かトラブルが起きた時に「あれは障害だ」と言われることで決まる。つまり障害は共有の問題です。共有といっても、DNAや身体能力的とかの能力で定義されるのではなく、その都度のパフォーマンスにおける共有。そのように障害を考えるなら、障害の問題を解決したり変化させたりするなら、もう一度出会って共有しなおすしかない。これは、揉めた出会いをやり直すということですから、当然揉める可能性は高い。でもトラブルを避けては問題は先送りになる。だから、バトラーは「揉めろ」と言います。1990年代にこの本が出て、そうか揉めたらいいんだ、と大きな影響を与えました。
瑛:社会に出よう、みたいな。
岸井:そう。開かれた福祉のことですね。揉めることこそ重要。硬直した共有をどうにかしたい時、話し合いとかじゃなくて、揉めるとよいってことです。
瑛:どういう状態が揉めることですか?
岸井:僕の読みだと、関係者の変容・変身が避けられなくなるまでいくのがトラブルですね。
久保田:ああ、わかる。変身を強要される。揉めるってことですね。家族においてわたしは変身をいつも強要されていて、常に私が変わるしかないんだなって思います。
岸井:変身は自由の侵害ともいえます。でもバトラーは自由という代わりにトラブルと言っているとも解釈できます。というのは揉めるってことは互いに違うのに一緒にいるってことですからね。そこには自由がある。
共有を変える・2「ケア」
岸井:バトラーがジェンダートラブルを書いて30年。バトラーの提案は多くの人を救ったと思います。僕も救われました。でも揉め続けた結果単に共有が崩壊しただけのこともある。分断ですね。
それで、最近流行っているのはケアです。人間は存在している限りずっとケアしていると考えたのがハイデガー。他人とともにある世界をケアしているわけです。心を配る。
ハイデガーは世界を配慮されたものである道具の連なりで見ています。そしてどの道具も他人もケアしている。この考えだと世界を変えるのはとても困難ということになりますが、共有されているものを丁寧に扱うことができます。ケアすることで共有されているものが芸術にさえなる。
共有を変える思考・3「装置の芸術」
岸井:ボリス・グロイスという影響力の大きい美術批評家が最近『ケアの哲学』という本を書きました。ケアでアートと哲学の歴史を語りなおそうという野心的な本です。そこにはいくつかの提案がありますが、ケアを変容させるものこそが芸術と言っていると僕は読みました。
で、最近芸術では装置がはやっています。インスタレーションとかリアル脱出ゲームとかARとかVRとか。装置を改変する芸術。そうすることで変な共有、面白い共有を作り出せるし、共有の失敗さえ楽しめる。
現状共有を変えたい場合、揉めて変身するか、ルールや仕組みをケアするか、アートとして装置をつくるかがあるんじゃないか。
瑛:レッツが行っているプロジェクト「かしだしたけし」は集団で全くお互い知らないような場所に行ってみて、そこで起きるトラブルを、お互い楽しんでみるみたいなことはなんとなくトラブルと変身の話に近いのかなと。そしてどちらかというと、相手が変身してもらうことを願っている。観光もそれに近いかなと思います。
<対談>
ケアの詩・トラブルの批評
来場者A:ケアは、装置を変えられるんでしょうか?トラブルがあった時に結局ケアをするというのはトラブルの前に戻るだけじゃないでしょうか?
岸井:そうですね。ただ、ちゃんとケアすると、共有されている装置に触れていきます。そのとき、共有はルールでなく詩になるとハイデガーは考えていると思います。ケアによって、共有を芸術として捉えるという変更はかけられるかもしれない。
来場者B:個人的なことなんですが、実際トラブルが大事と思う気持ちと、でもトラブルばかりだと疲れて戦いたくないという気持ちがあります。体力がないから戦いたくないけど、ケアの気持ちを持ちうる限り日々起こる戦いがあって辛いことがあります。
岸井:バトラーで重要なのはトラブルを抱えた同士の連帯ではないでしょうか。各自のトラブルは異なるんですが、世の中から排除されて傷ついているという意味では連帯してしまう。連帯しなくても、それぞれが揉めていくことで世の中が変わっていく。
また、トラブルで考えるときに、批評は不可欠だと僕は思う。
僕は渋谷ハロウィンを見て、バトラーを思い出しました。ハロウィンってキリスト教によって抑圧された妖怪たちのパーティですよ。参加者は顔に傷をつけたりして、バラバラに街にでていく。それぞれが勝手に集まるし、中心になるメッセージもない。でもおそらく、世の中に居場所がない人が多く集まっているんじゃないでしょうか。トラブルが集まる。あれこど開かれた福祉であり、無為の共同体でしょう。
僕の知る限り、バトラーの専門家が誰も渋谷ハロインに言及していないと思います。これは僕の見立てが的外れなのか、トラブルをキャッチできる批評が機能していないかのいずれかだとおもう。
日本でトラブルが大事という活動をしていったときに、重要なことだと指摘する人が不足しているのかもと思います。
自分なりの装置に変えていく
久保田:傷ついたことを誰とも共有できないけれど自分なりの装置に変えちゃうって言うのは方法としてはありますよね?私のやってることはそういう活動だと思っている。怒りからしか活動は生まれないなって常に思っている。怒りを怒りのまま表出したところで、誰も幸せになれないし、批判されて終わるのであれば、装置というか、違う形にして出しちゃう。それを今まではアートって呼んでたけれど、でも今日の話では装置ですよね。
岸井:アートでいいと思います。ただ装置の方が広く考えられると思いました。つまりアートっていわなくてもいい。変な装置とかおもろい装置でよいかな、と。
久保田:個人的に頑張って装置化し続けているだけな気がする。
共有されている装置
瑛:もうちょっとレッツの場づくりとか今やっていることと引き寄せながら話そうと思います。このトーク会場のちまた公民館はある種の装置をこれから作っていかなきゃいけません。2年間やってきて、共有することがいかに困難かっていうことを思っています。ハッピーの家ろっけんが、「トラブルが2つだとそこの2つに集中しちゃうんだけど、トラブルが3つ以上だとどうでも良くなっちゃうから、3つ以上持ち込もう」みたいなことを言っていて、それがすごくいい話だなと思っています。ちまた公民館でも混沌としようと思ってはいるのですが、実際に混沌としたら混沌としたで難しい。単純な衝突で終わり、硬直した関係が続いてしまったり。
トラブルを起こしたときに、気にしなかったり強い人しか残らないみたいな、荒野になりませんか。どんなスペースにも言えることだと思いますけど、ある種配慮があったり身をひいたりトラブルが苦手な人はどんどんいなくなっていく。
岸井:フリーライダー問題ですかね。「共有ってことはここのものは全部自由に使っていいんですよ」って共有物が使えなくなるまで消費して壊しちゃう人のことです。
久保田:むしろ壊しちゃうっていう手もありますよね。大体関係性も場も硬直していく。そうした時にその人たちだけのものになってしまう、そうでない人が排除されてしまうっていうことが起こったら壊せばいい。そうするとまたガラッと場所が変わる。それってケアと逆の方向になるけど、変身を促進するかもしれない。その人たち自身が変わるチャンスかもしれない。他の場所を探す動機にもなるし悪いことではない気がします。
岸井:人を入れ替えかわり、継承や記憶が消えても、土壌とか根っこだけ残るのが大事です。ドゥルーズの言うリゾームですね。
いまの会場のちまた公民館は「たけし文化センターインフォラウンジ」「黒板とキッチン」ていう場所の跡地でやっている。あのころの雰囲気も人も記憶もないけど、耕された土壌だけが残されていると感じます。
久保田:そう、「黒板とキッチン」も悩んでたんですよ。同じような人たちだけがやってきてその人たちだけのスペースになっていく。でもそこで一回ケアされたっていう体験もある訳ですよ。その体験があればいいと思う。ある日突然出ていってと言われたとしても、なんてひどい奴らだっていうかもしれないけど、でも一回認められた経験もあるから、やっぱりじゃあ次ってなるかもしれないし、ごめんなさいちょっと気をつけますっていうふうになるかもしれない。変化は起こすしかないと思うんですよね。そこを怖がっていると、場はどんどん硬直して、結局働いている人もつまらなくなるっていう。私今日の話を聞いて、それでいいんだなって、気をつかわなくていいんだなって思いました。
その時に、重度の知的障害者の人たちってすごいんですよね、一気に場の硬直を壊してくれるから。誰も彼らを排除できなくなる。ちょっとこの人たちに意地悪できないなってなる。ここはこういう場所かっていうのを見せてくれる。
岸井:僕は、レッツは、豊かな土壌が装置の形で継承されているんじゃないかと思うんですよ。
意図的にできない「装置」
瑛:岸井さんがいろんなスペースを見られて、秀逸だと思った装置ってあります?
岸井:それが、最初にはなしたたけし文化センターBUNSENDOですね。無意味な高いイスは、今のレッツにも装置となって機能していると思う。レッツには無意味な高い場所が必ずありますね。でも高い椅子のことはだれも覚えてない。共有が意識されず残っている。これを装置じゃないですか。
久保田:たけしがいられる場所を作りたいって思いがあって、一般の人もお茶を飲みに来て欲しいって思いがあって生まれたもの。
岸井:なんでレッツがいい例なのかというと、あの高い椅子は役に立ってない訳ですよ。ただ、そこにいる人がお茶を持ち上げるだけでいいことに気づいたんです。そしててそれを話す時の舞台装置として「無意味な高い椅子」があり、「無意味な高い場所」が残ったんじゃないか。
このトークをうけてあとから文章をかくことになっているので、この話詳しくは文章にかきますので読んでくださいねー。
共有のトラブルを共有する
会場から:そもそも共有している前提であるっていうのは思ったことがなかったので、ちまた公民館に来る人はそもそも誰かと共有しようと思ってきているのか、という考え方自体が違っているのかなと。
岸井:そうですね。今日は共有の話をせよということだったので、共有の話をしました。
でもだれでも空気とか道路とか何かは共有しています。でも何を共有しているかを捉えるのは難しいし変な共有は忘れられがち。
私は共有のトラブルを面白く共有するということに興味があるんです。劇作家ですから。
瑛:岸井さんありがとうございました。