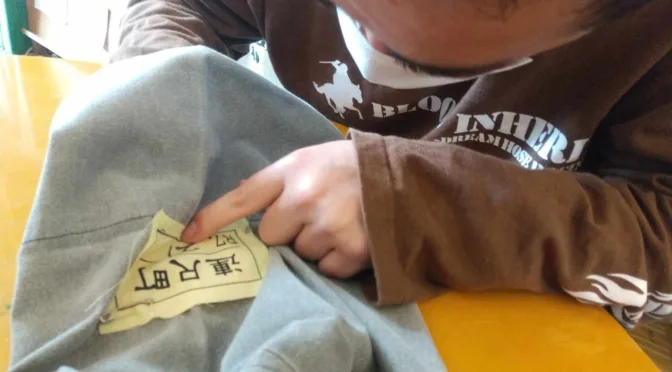![〈トークまとめ〉第9回 ゲスト:青田元さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/169A3257-scaled.webp)
〈トークまとめ〉第9回 ゲスト:青田元さん [ひとインれじでんす2024]
瑛 「生きのびるためのエクササイズ」というトークシリーズでは、自分たちが生き延びるために、いろんな価値観に触れるということをテーマにゲストをお呼びしていますが最終回が青田さんになります。そして今までお呼びしたゲストの中で一番異業種なのが青田さんだったと思います。今日はですね、青田さんに聞く、新規共創事業のリアルみたいなテーマなんですけど、まずは青田さんとヤマハ発動機さんがどんなことやってるんだろうっていうことから話を広げながら、そういうビジネスの世界にいる青田さんがこういう福祉施設兼アートNPO という特殊な場所に来てどんな感想を持たれたのかという話、そしてフリートークに入っていきたいと思います。
ではまず早速、自己紹介からお願いしてもいいでしょうか。
◼︎青田さんの自己紹介
青田 ヤマハ発動機で、1月から経営戦略本部長をやっています。青田といいます。よろしくお願いします。

私、出身が岡山県なので実は浜松は何の縁もゆかりもないんですが、岡山と浜松は実は共通点が結構多くて、80万人都市なんですね。街のサイズとしてはかなり近いと思います。商業都市っていうのも似てるかな。18歳まで岡山にいて、その後東京の大学に行って、最初の仕事は三井物産という総合商社に入り21年間、鉱山開発の仕事をやってきました。
2017年にヤマハ発動機という会社の新規事業担当の応募がありまして、そこに手を上げて移籍をしました。新規事業担当から、それから経営企画を2年半ぐらいやっているので、ヤマハ発動機に来てからは新しいことを作る仕事か、会社全体の方向性を整える仕事か、今年の1月からは両方をやることになりますね。
会社の話をしますと、ヤマハ発動機は全体の売上の94%が海外です。2兆4000 億の売上のうちたった6%しか国内に
売ってないんですよね。だから日本ではあまり広告を見かけない。でも会社の中は完全に日本語の環境で、経営も開発も基本的には日本語でやってる。ただ取締役会は英語ですし、僕が司会をやっているグローバル会議はやっと英語になりました。
また全体の売上を100とすると、60%ぐらいがバイク、モーターサイクルとかタイヤが付いてる乗り物ですね。で、20%が船とか船外機とかの水の上の乗り物。残りの10%ぐらいがロボティクスっていう領域です。ヤマハ発動機の雰囲気とか文化についてはヤマハ発動機も兄弟会社であるヤマハ株式会社も、車を作らなかったのは結構大きなポイントだと思っています。車を作るにはかなりのリソースを割かないといけないわけですけど、結果的に値段の競争になって、かけたリソースとエネルギーを取り返せない。もしヤマハも車に全リソースを注いでたら、ダメになってたと個人的には思ってるし、少なくともモーターサイクルが1番大きな商品になってはなかったと思いますね。
◼︎新規事業をやる理由
瑛 ありがとうございます。あと、経営戦略本部長と新規事業開発本部長、この2つの事業の詳細を教えていただいてもいいですか。
青田 経団連の資料を見ると、日本の上場企業では、初めて社長になる人が80%ぐらいなんですよね。日本の会社は大体、東京証券取引所に入れば60年ぐらい保つので、少しずつやることを変えていかなきゃいけないと思うんですよ。日本では、会社ごと潰して新しい会社を作るよりも、優秀な人材が集まり、長く働くので、その人たちを使って次のことをやる方がいいんです。僕らも一緒で、ヤマハ発動機っていう会社を将来どう持っていくかということと、新しいことをやる話は切り離せません。
◼︎新規事業の例
瑛 新規事業開発部ができたのは何年ぐらいからなんですか。
青田 僕が入った2017年にはもう始まっていて、その時は多分20人くらいの組織だったんですけど、今は海外を除いて106人、海外を入れると多分200人ちょっとなんじゃないかな。
瑛 新規事業ってどういうものか、具体例とか教えていただけますか。
青田 新規事業が今のヤマハ発動機のモノづくりの延長線上にあるならば、僕の仕事ではないと思っています。そうではなくサービス系の事業を行っています。今行っている新規事業にはアフリカとインドでオートバイを買えない人たちにオートバイを貸すという事業があります。毎日オートバイを借りた人が物を運んで10ドル稼いでくるんだったら、そのうち3ドルを僕らはもらって、残りの7ドルは皆さんのポケットに入れてください、で、1年半経ったらこのバイクはあなたのものになります、みたいな事業です。 それに、日本ではもうバイクに市民権がないんですよね。時間が経てば経つほど失われていく市民権をどうやったら長続きさせられるかというところで、今1番成長してる国でバイクを入れれば長続きするかなっていう思いもあります。
瑛 そのような商業的な目線もありつつ、一方で、若者の貧困率とか失業率がすごく高くて、そのオートバイさえあれば、Uberとかタクシーとか、すぐに職につけるみたいな、社会的なミッションも達成しているっていうような事業なんですよね。
青田 そうですね。やっぱりこの世の中には僕らが思ってる常識じゃないものがいっぱいあるんですよね。さっきのバイクの事業をやってるナイジェリアで言ったら、65%の人は定職についてないんですよ。失業率6割って言ったらすごく悲しく聞こえるかもしれないけど、彼らはセルフエンプロイド、自分たちは自立してると言うんです。そういう人たちが65%いるからできる事業です。僕らの常識で日本に座ってるだけだったら、ナイジェリアのその環境は分からないじゃないですか。海外シェアが94%という日本の外に物を売っているから見える世界があります。僕らが何をできるかっていうのをちょっとずつ集合知の形にして考えています。
◼︎ヤマハ発動機の風土、浜松や日本に対する思い
瑛 今回、青田さんは2日間お時間をいただいて、実は部下の方を4人連れて滞在していただいたんですけど、、ヤマハさんなりの風土とか、浜松に対する思い、それこそ6%の日本に対する思いとかはありますか。
青田 株主や従業員などいろんなステークホルダーがいますが、僕の考えではその中に地域が入っています。なぜかというと、僕らは工場や会社をこの地域で運営して、生きていますが、そこで働いてる従業員の人たちは地域にサポートされてなかったら暮らせないわけですよ。家庭ゴミの回収1つでさえ地域にサポートされているわけです。間接的な地域支援は、例えばサッカーチームやラグビーチームの運営があると思いますが、もうちょっと直接的に関わることが大事なんじゃないかなっていうのは自分の課題です。
◼︎レッツに滞在した感感想
瑛 ありがとうございます。昨日4名の方と一緒に滞在していただいたんですが、率直にどうでしたか。感想とか、グッときたポイントみたいな具体例があったら教えていただけますか。
青田 自分にとっては鏡みたいな感じがしました。結局、障害のある人たちから受け止めるメッセージが言葉としてあんまりないので、自分がどう考えるかっていうところと、自分がやった行動に対して、想像して納得するしかないんだなって。多分、初日の僕だろうが、10年経験してるプロだろうが、同じなんじゃないかなって思ったんです。感想という点では、僕より舟生さんの方がの方が話せると思います。
舟生 新事業開発統括部で、青田の下で新事業開発を担当している者です。青田は、0から1をクリエイトする、発想も飛び回る方なんですけど、私はどっちかというと枠にはめる、割と真逆なタイプです。レッツの感想についてはですね、私も実はこういう施設に来るのは生まれて初めてで、行く前からドキドキしていたのですが、扉を開けて入ったら、皆さんすごくフレンドリーで、利用者の皆さんもニコニコして自然に振る舞われていて、こんな幸せな空間があるんだっていうのがまず衝撃でした。その後、お散歩で佐鳴湖とお寺に2人の利用者さんと一緒に行かせていただきました。2人とも生き生きされてましたね。あと、当社から来たもう1人が利用者さんとお散歩でデパートに行った時も、利用者さんが一目散にロレックスに走っていって、周りが大丈夫かって焦ったという話を聞いたり。すごく楽しい時間を過ごさせていただいたのが本当に嬉しかったですね。僕は普段、磐田に住んでいるので、あんまり浜松は歩かないのですが、散歩っていくつになっても楽しいなと思いました。

◼︎社会共創事業
瑛 ここから青田さんに、社会共創事業とは何かというところからお聞きしていきたいと思います。
青田 1つは、社会共創活動の「共創」という言葉が意味するのは、「自分たちが苦手なことがあるんだったら、得意な人と一緒にやろうよ」ということなんですよ。
もう1つは、社会課題の解決ですね。社会に自分たちが役に立つのかもう一度見直して、新しいことをやる際に、自分たちがやることが社会にとってネガティブになるのならばやらないようにしよう、ということですね。そして自分たちが社会の基盤に何かを返していく際に社会の基盤に対するアプローチ方法がなかったり分かっていないのならば、そこを分かってる人とやった方がいいよねっていうことで、「社会」という言葉を置いてます。
ただ僕は去年1年間、死ぬほどAIと付き合ってみて、社会課題の解決はもう俺がやらなくてもいいかなって正直思っています。それよりは課題を見つけられる人の方が大事だな、と思い始めているんですよね。多分、そういうことができる人はAIに置き代わらないと思うし、そういうことに気づける人になってもらいたいなと思うんですよ。レッツに来て単に僕らは見学することしかできないかもしれないけど、レッツにどっぷり浸かってる人には見えないような課題が見つけられるんだったら、僕らには多分機能がある。自分たちがもし鍛えるものがあるとすると、そこなのかというのが、社会共創とか課題解決って言葉から僕が今考え方を変えようとしてるところです。
瑛 なるほど。私たちの活動がなぜ「アート」という言葉を使ってるかというと、アートは解決はできないけど、問題に気づくことができるからです。問題を社会に提示していく。そうしたことが、アートNPOのミッションなので、その感覚はすごく似てるなって思いました。
青田 アートっていう世界に対して、ビジネスの人たちから見てもそこが大事だって逆に追いついただけかもしれないね。 僕らはどちらかというと賽を投げられたものを受け止めてから考える人たちだったけど、僕らの中にも賽を投げる人がいないと、もう個性やユニークさがない、その人でなきゃいけない理由がなくなってしまう気がします。
◼︎非財務指標
瑛 また、お打合せの際に社会共創事業の中で、非財務指標を重要視してるというお話があったのですが、そこを噛み砕いて教えていただけますか。
青田 「財務指標」は分かりやすい言葉に変換すると売上や利益なのですが、それとは別に、「非財務指標」を提示す
る会社が増えてきています。会社は稼ぐだけじゃダメ、株主から見ると稼ぐ以外の指標も大事だねっていうことで、それらを評価するために「非財務指標」があります。自分たちのミッションを示す時に何を大事にしてるかを金額指標以外のやり方で表現し始めています。最近は働いている人の満足度やエンゲージメントなどをまとめて「人的資本経営」と言い方をしています。僕は企業が生きていく中において、人が大事だと思っています。だから、もしレッツに株主がいれば、「この人をどうやって育てているんですか」とか「この人はどういう人たちなんですか」っていうのを企業としては説明しなきゃいけない。僕はその説明を、働く人の持続可能性について表現する指標にちょっとずつ変えていきたいという思いがあります。
「財務指標」と「非財務指標」に対して、先日、TDKさんという会社が人に関する指標を全部まとめて「未財務指標」という言い方をしていました。「ここで育てた人は必ず会社の財務指標に貢献します」という言い方をしたんです。僕はこれはすごく良いアイデアだなと思いましたし、こういうふうに僕も整えていきたいと思いますね。でも単純に研修に多く出せば良いという話ではないので、一体どういう人を育てたいか、それに合った人の育て方ってなんだろうと考えています。もしかしたらレッツに2年間研修に出すことかもしれない。例えば、レッツがやりたいことがあった時にそれを回せるだけのお金とか、人の採用を、うまく両サイドに納得がいくようなストーリーが作れると、共創関係が綺麗に生まれていくかもしれない。共創関係は両方が幸せじゃなきゃいけないんです。どっちかが搾取する関係は共創じゃないんです。
瑛 Win-Winともまたちょっと違いますか。
青田 Win-Winは、成長しなきゃいけないんですよ。要はパイを増やして2人で分け合う話だから。そうではなく互助関係でもいいと思っています。常に成長神話を僕らは持ってしまうんですが、別に成長しなくてもお互いが分け合えばそれは それでいいんじゃないかな。
瑛 ありがとうございます。大企業の共創事業というとなんだかハードルが高く感じますが、今いただいたお話のように、Win-Winではなくて、互助の関係であること、それは私たちのNPOがやっているような、お互いが生き延びるためのプラットフォームを大小関係なく作ろうみたいなところから入っていくのも、共創と言えるんだなと思い、すごくエンパワメントされました。
◼︎企業にとっての「弱さ」「できなさ」
久保田 お話ありがとうございます。大体、障害のある人たちは社会から距離を置かれてきた長い歴史があります。マジョリティの方から見ると、守ってあげなければいけない、助けてあげなければいけないという対象だった。でもコロナが大きかったと思いますが時代が変わってきたような気がしますが、今日の青田さんの話の中にもあったように、とにかく儲ければいい、会社が大きくなればいいっていうだけではない、違ったフェーズの社会を作っていかなければいけないという時代に入ったなと思います。その中で私たちが、やっと企業の方々と何か共創できる時代がやってきたのかもしれないと思いました。そこで、「弱さ」や「できなさ」みたいなものの価値を私たちは追求しています。「弱さ」や「できなさ」というのは、ほとんどの人がマイナスのイメージを持ちますし、排除しなければいけないものと捉えられているかもしれません。しかし、そこにもしかしたら価値があるのかもしれないと思っています。なので一流企業で、94%海外で勝負している会社の方々にとって、その「弱さ」や「できなさ」にどういう価値があるのか。それから、CSRやボランティアの意味ではなくて、「弱さ」や「できなさ」がどういうふうに関わると、自分たちの企業にとって何かためになって、また新しい想像力みたいなものに変えていけるのかどうか、そのようなところをお伺いしたいなと思います。
青田 会社の中に優秀な人とできない人がいた時、できればみんな優秀になってもらいたいから、できない人にフォーカスを当てないんですよ。でも、もしかしたらそこを認めると、もっと違うことが起きるかもしれないなというのが、昨日今日で僕が考えているテーマです。あるいは、「弱い人やできない人がいていいじゃん」と認めさせるためにはどのような構造が必要なのか。またその構造で最終的に自分たちのパフォーマンスは元よりも良くなったというのをどのように証明するのか。その方法を考えていくのは面白いなと思いました。僕らはまだ多分、障害がある人よりも会社の中における弱い人を認めるのは遅れているような気がする。見たくない、触りたくないってみんな思ってるかもしれないっていうのが率直な感想です。
◼︎擬似体験か、リアルな体験か
久保田 いわゆるエリートと呼ばれる人たちを大きな企業であればあるほど雇っていくわけですよね。そもそも弱さみたいなものは本当はいろんな人たちが持っているはずだとは思いますが、あえてそれに着目するっていう機会はなかなか少ないとは思うんですね。だけど、そこに着目することによって何か新しい価値観や創造性が生まれる時代がやってきてほしいと思っているんです。それは一方ですごく怖いことかもしれません。自分が弱くもなっていくし迷うし悩むし立ち止まることにもなるんですよね。どうしても人は健康であれば健康であるほど、それを受け入れたくないものだと思います。でもそういう健康である人たちがあえて弱さを擬似体験するとか、人間には想像力があるので一緒にそれを感じてみるようなプログラムがもし本当に生まれたらどうですかね。
青田 僕は逆のことをイメージしていて、バーチャルで想像するとか疑似体験するって本当にできちゃうんですよ。でもフィジカルな体験ってもうできなくなってるんですよね。だからあえて僕はフィジカルにこだわる方がいいんじゃないかなって思うんですよ。やっぱりもっと実体験させるようなプログラムが増えていくような気がするし、本当に人の価値観を壊すようなこととか、人を成長させるようなことはやっぱりリアルな体験でしかないんじゃないかなって僕は逆に思いますけどね。
◼︎子育てというリアルな体験
久保田 もう1つ聞きたいんですが、私は一番生々しい体験っていうのは子どもを生んだ時だったんですよね。育てる
中でなんだこれっていう、もう異文化体験どころの話じゃなくて、自分の今までの価値観を全部投入しても理解できないっていうものが生まれました。だからといって放置するわけにも逃げるわけにもいかず、とにかく何かしなきゃと向き合ったことが1番リアルな体験だったような感じがするんですよね。企業の皆さんだって子どもや家族はいるし、その生々しい体験を実はいろんなところでできるチャンスはあるはずなんですけど、そこは割と簡単に乗り越え超えちゃうんですかね。
青田 例えば30代の前半で子どもができたとして、時々ご両親に手伝ってもらうとかあるかもしれないですけど、本当に核家族になってくると、もうパートナーと向き合うしかないですよね。パートナーと向き合った時って、押し付け合いもあるし学びじゃなくなっちゃう、損得の議論になっちゃうような気がしていて。子育て中の私の部下も、特にコロナ禍のタイミングで1LDKに住んでいて、夫婦共にリモートで会議が入っている後ろで子どもが泣いている景色を何度も見てきました。僕はあのタイミングで、本来だったら家にいて子どもの面倒を見てなきゃいけないあの世代を酷使してたんだなって思ったんですよ。ただそれが共有されずに、コロナが終わって、この経験とか辛かった時間が終わった、また日常に戻れたって皆思ったんです。本当はあのタイミングで、もう1回振り返って会社として何をしなきゃいけなかったのかとか、次の世代が子育てしていく中でどういうことができたのかとか、対話もしなきゃいけなかったんだと思うんですけど、もう昔に戻っちゃった感があって。これは自分の反省事項ですね。
◼︎弱さ・できなさが特異性のきっかけに
来場者A 弱さ・できなさの話に関連してですが、僕は養蜂をやっていて、生き物が好きでいろいろ進化論などを調べています。生き物は環境が変わると、その環境に適用できなくて、弱さ・できなさが出てくるんですよね。これって事業もそうだと思うんですよね。助けてほしいから技術を教えてと言って、隣でうまくいってる人に技術をもらってしまうと次の何か変化があった時に対応できないと思うんですよね。そう考えた時に、弱さ・できなさっていうのは、特異性を持つきっかけになり得るなと思います。なので、常にものを考える時に、「なんでこうなったのか」じゃなくて、「次に何をするか」を考える必要がある。こういう場で意見を交換し合えることがすごく面白い場だなって思いました。
青田 1個だけコメントすると、恒久的に今の組織が続くのだったら、今の発想で動いているし、今の発想で動いてきたんだと思うんですよね。組織論と進化論は比較されるんですけど、組織論で進化論が持ってない点を1個挙げるとすると、時間軸ですよね。スピードがないと生き残れない時に、進化を待てないという気がしますね。だから、共創活動は個人的にはセカンドベストだと思っています。全部自分たちでやって、悩んだり苦しんだりしながら克服して生きていければベストだと思います。しかしそれをやっている時の企業としての悩みは、だんだん先細りして良い人が入ってこなくなるということです。もう1つは、時間が経てば経つほど取れるパイも小さくなるかもしれないということです。この2つと戦う時に、どうするのがいいのかなっていうと、他の人と一緒にやる。それは長い目で見ると、組織のオリジナリティや独立性を失うかもしれないと思いながらもやっているような気がします。
◼︎子育てや家族の定義
来場者 子育ての話について思ったことのシェアなのですが、資本主義は、資源を消費して急速に成長する手段のように僕には見えるんですね。そのときの消費される資源には人間も含まれると思うんです。それは再生産ができない仕組みだなって僕は思っています。子育てをする、つまり資源である人を再生産すると、資本主義においては個人は不利になる、それをしない方が競争社会や資本主義においては有利になるっていう形が明確にあるので、基本的に少子化は今、問題視されているけども、いやこれは僕らが望んで作った世界だと思うんですね。なので、じゃあどうするかっていう新しい価値観を作らないといけないんじゃないかなと思っています。
それと、僕は蜂蜜屋さんをやってるんですけども、今年から社内食堂みたいなものを作ろうと思っています。うちは瓶詰めを沢山しないといけないのですが、瓶詰はいつでもできるので、出社時間や帰る時間を自由にしているんです。そしたら働いている人は見事に主婦ばっかりなんですよ。みんな主婦で、帰って家事をしないといけないから、うちのお店は4時までなんですよね。そこでちょっと考えてみたんです。例えば、5人いて、みんなが帰ってそれぞれ1時間、合わせると5時間をかけてご飯を作るのに対して、うちでみんなで1時間かけて5人分作れば、4時間の時間という資源が作れるなって思ったんですよね。それがきっかけで社内食堂を作ろうかなと思っているんです。
家族の形とか、会社と家庭を曖昧にするということをしてみていて、ちょっとうまくいき始めている過渡期になっていて、面白い状況です。
青田 僕、新明解国語辞典のすごいファンなんです。今までは、「夫婦が子どもを持つ」ことが多分1番ミニマムな家族の定義だと思うんだけど、「1つのキッチンを共有する」のが家族の定義になってたらいいなって今の話を聞いて思いました。それは多分レッツがやってることでもあると思うんだけど。
◼︎弱さを捉え直す
来場者 先ほど出たリアルな体験が必要だっていうことに対してですが、実はうちの会社でも最近ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの啓発活動が盛んに行われています。私もそういったワークショップに参加しました。そこで、VRのゴーグルをつけてADHDの脳内を体験するというのがあったのですが、私にはそれをつけてもイメージしづらかったんですよ。やっぱり頭の中で何を考えてるのかっていうのはVRだとわからないし、こういった場で実際の体験をしてもらうっていうのはすごく重要なことだと感じました。
あと、同じくその時のワークショップで講師が、障害とは連続性を持っていることだと言っていました。だから、医学的にそういった診断のつかない人は福祉の制度から外れてしまって、すごく居づらい環境になってしまってるのは問題だなと思ってます。あとは、そういった連続性があるということは、ひょっとしたら私自身にも何らかの障害があるんじゃないかなっていうふうに思うような時もあります。
それと、先ほど久保田さんがおっしゃった、「弱さ」「できなさ」の価値をなんとか追求できないかというところに絡んで、近年だと、例えばUSのIT企業なんかでは、インクルーシブデザインをやるような組織が体制化されていることがルール化されている。企画設計の段階から障害者でも使えるようなものにしていきましょうっていうことで障害者の意見を取り入れながらものづくりを進めていく方法なんですけど、私も技術部門でものづくりをしている視点から、そういった動きが広がってくるのはすごくいいことなんじゃないかなというふうに感じています。
瑛 青田さんをお呼びする際に話していたことなのですが、社会の中で、今なぜ、障害がある人が弱いって呼ばれてるのかを考えてみると、単純に強い人たちの言語的にコミュニケーションが得意であるとか、体が丈夫であるとか、認知がマジョリティの中で成立しているというところが知性として社会の中で認められてるからだと思うんですね。それは大学とかも含めて体系化されていってるし、今は競争社会の中で3分プレゼンみたいな形で、言葉が優位な時代だなと思います。一方で、今私たちが使っている言語的な知性ではない、身体的な知性なのか、何の知性なのかわからないんですけど、何かがそこに存在しているんじゃないかと思うんです。だから、私たちは今、相対的には弱いと表現されているけども、別に弱いとは思っていないっていうのが個人的な感覚です。身体知が強いとか感覚知が強いとか、あとレッツのメンバーさんのそれぞれの何か特殊な持ってるものが単純に健常者のマジョリティが感じ取れてないだけかもしれない。障害というものにグラデーションがあるように、知性にもグラデーションがある。よく使われる知性が強いと言われ、よく使われない知性は弱いと言われてる。そんな俯瞰したような感覚で私は捉えています。