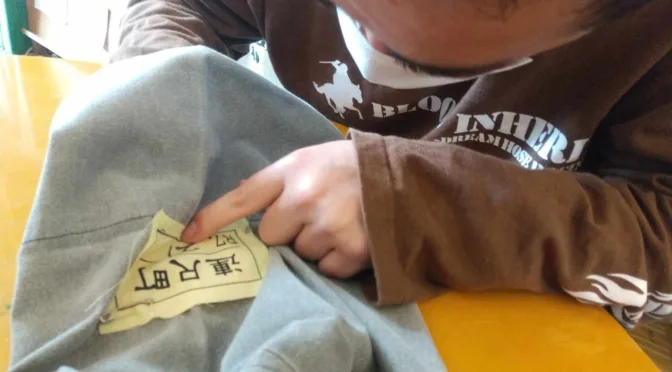![《寄稿》第4,5回 ゲスト:西川勝さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1369-2-scaled.webp)
《寄稿》第4,5回 ゲスト:西川勝さん [ひとインれじでんす2024]
「いしけっていしえんかいぎ」雑感
文=西川勝
ぼくが浜松の認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ(以後、レッツと略称)を初めて訪れたのは、いつのことだったろう。ホームページで沿革を確認してみると2011年に鷲田清一先生の講演があり、2014年には哲学カフェ『かたりのヴァ』がはじまっている。この間ぐらいに、哲学カフェの進行役としてはじめて呼ばれたのだと思う。
それからのお付き合いは多すぎて記録も持っていない。ぼくは大阪に住んでいるので、大抵は泊まりがけで浜松に行くのだが、ホテルに泊まることが多かった。たけし文化センター連尺町のシェアハウスには何度か泊めてもらい、ぐっと距離が縮まった気がしたのを覚えている。いつも夜遅くまで、レッツのスタッフたちと話していたので、生まれも育ちも縁のない浜松が友人の多い地元のような気分になっていった。だから、今回あらためて滞在感想記を求められても困ってしまうのだが、2024年10月8日9日のレッツ訪問はちょっといつもとは違う。その理由は、訪問の用件が『いしけっていしえんかいぎ』の進行役を務めることになったからである。
この会議で、レッツの最重要人物であるたけし君のてんかん手術の是非を検討するというので、ぼくは暗闇の深い穴に飛び込むような気分で大阪を出発した。レッツに到着すると、慣れ親しんだ「かたりのヴぁ」や「しえんかいぎ」の雰囲気を思い出すのだが、やはりちょっと違う。もともと進行役としてはおしゃべりの過ぎるぼくが、とめどなくしゃべり続けてしまう。沈黙することを怖がっている。その影響もあってか、参加者の発言も少ない。ぼくの焦りはますますひどくなる。どんな内容の会議であったかは、詳細な記録をレッツが残してくれているので、そちらを参照してもらいたい。ぼくとしては会議の後ずっと残っている不全感の根っこにあるものを明らかにしてみたい。
病気や障害によって自らの意思を表明することに困難を抱える人は多い。その人が医療や福祉の援助を受ける際に、本人の受諾の意思を確認する必要がしばしば生じる。そこで登場するのが「意思決定支援」という方策である。法律家や倫理学者などが医療福祉の専門家と協力しながら議論を重ね、一定のガイドラインが公開されている現状にある。そのことは事前に調べておいたので知ってはいたが、レッツの「いしけっていしえんかいぎ」では、ガイドラインに従うという方法はとらなかった。通常ならば、最も本人に近い存在として家族の参加が求められるのに、レッツの場合、家族の意向もあって家族抜きの会議にしたという背景もある。自己決定から自己責任へという幻想の自立個人主義に批判的なレッツの思想が、ケアを家族に押しつける社会への批判にも論を深めていくのは当然の流れだろう。
「私の意思決定」ではない「私たちの意思決定」をめざし、私たちをどのようにして結び合い、支え合うのかが問われている。このとき、唯一の結論に決定することが大切なのか、今一度考える必要がある。是か否かの二者択一でしか答えはないのか、選択の前に問うべきは問題設定が前提にしていることに対する反省なのではないか。
人生は無数の選択に満ちている。しかし、最後の選択となり得るような究極の問いは存在するのだろうか。これが最後だと覚悟しても、次の選択は容赦なく現れる。究極の問いがなければ、究極の答えもない。常に探求の途上にあるしかないのが人生の真相であるとさえ思える。自分だけに閉じこもっては行き詰まる。狭い関係だと煮詰まってしまう。次なる出口は開くのは、異なる他者との出会いだろう。わたしが脱皮して私たちになるときに、未知の土地へと続く長い道のりを共に歩む仲間ができる。「こうした方がいいよ」と訳知りが顔に促すより、「一緒にしようよ」と誘い合う笑顔が、ぼくには望ましい。互いが喜べるようにするには正解は一つでは足りない。自分だけでは見落としがちな小さな宝物を見つけてくれる仲間がいれば、どれだけ幸せになれるだろう。てんかんという躓きの石をよけながら、たけし君の大好きな小石を見つける旅に出かけてみたい。