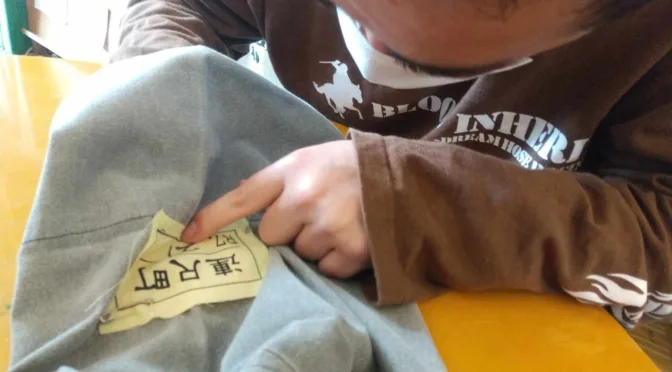![【スタッフ所感】第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1458-scaled.webp)
【スタッフ所感】第7回 ゲスト:小松理虔さん [ひとインれじでんす2024]
第7回 ゲスト:小松理虔(地域活動家)
塚本千花(認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)
参加者からの発言で、気にかかったものを書き出す。糸こんにゃくみたいな記憶力に頼っているので、内容は正確ではない(このときおでんを食べていた)。
◎久保田さんと理虔さんに感謝を述べたいと、マイクを持った男性。
「自分は統合失調症で、長いこと障害者をやってきて、なにが一番辛いかって、とにかく寂しい。社会の外にいる存在にされてしまう。だから、ただ一緒にいてくれることに、そういう場をつくってくれていることに、ほんとうに感謝している。」言葉に詰まりながら、震える声で発言されていた。「一緒にいてくれる」という彼の言葉には、自らが下であるというような意味合いが、なんの違和感もなく含まれているように思った。
◎別の文脈での発言、夏目さん。
「それを福祉と呼ぶことで、我々は立場を区切っているのではないか。現場には対人間としての関係があり、支援者は福祉の専門家である必要はない」
◎これを受けて、高本さん。
「しかし専門性が軽んじられてモヤモヤすることもある。転んだ利用者さんが、負担なく起き上がれるよう、介護職は専門的なスキルを身に着けている。介護は誰にでもできるという謳い文句で、技術の取得を蔑ろにされてしまうことに疑問がある」
レッツで過ごして三年になる。わたしは今、福祉もケアも本当は存在しなくて(それらは便宜上設けられた言葉や境界に過ぎない)、世界には”あなた”がいて、”わたし”がいるだけだ、と思っている。
一緒にいてくれる、という言葉の裏には<一緒にいてあげている>ひとがいる。<いてあげている>のではない。<いる>のである。ただそこに、あなたとわたしがいる。上も下も左も右もなくて、ただ、わたしとあなたがいるだけなのだから、いてくれる、なんて言う必要は、本当は無いはずである(理虔さんの言う「ただそこにいる」と、今わたしの考えている「ただそこにいる」は、きっと違う意味だろう)。マイクを持った彼が、おそらく無意識に<一緒にいてくれる>と言わざるを得なかったのは、福祉とかケアとか言っている、わたしたちを含める社会のせいだと思う。
専門的に、技術を取得しようとか物事を極めようとするのは、その対象に向き合おうとする、向き合いたいと思う現われのひとつに過ぎないのではないか。高本さんの言う「専門性を軽んじているひとたち」は、だから、そこにいる人間と向き合う気がない、ということではないか。
レッツに来る以前に、筋ジストロフィーの方の訪問介護の仕事をしていたことがある。わたしは介護のセンスがほんとうに無くて、後から入ってくる未経験ヘルパーたちにどんどん先を越されてしまうものだから(例えばお風呂上りに服を着るとき、上手な人は5分でできるのに、わたしは20分もかかってしまって、彼女に風邪をひかせてしまうわけである)、もう辞めたいというか、辞めたほうがお互いのためなんじゃないかと思ったことが何度もあった。わたし以上に彼女のほうがしんどかったはずである。ひとに注意するというのはエネルギーがいる。何度言っても上達しない人間に、その身を任せ続けなければいけない。言わなければ、身体に負荷が掛かり続けて、寝込むことになってしまう。諦めることも突き放すこともできないから、自分のためにも、彼女はわたしと向き合い続けなければならなかったと思う。そしてほんとうに辛抱強く、口頭だったり、人形を使ったり、絵で説明したり、色んな手段で、丁寧に丁寧に、自分の身体に対してどうアプローチしてほしいのかを、わたしに伝え続けてくれた。そんなひとに対して適当になることはできなかったから、わたしも彼女にちゃんと向き合いたくて、ヘルパーを続けることができた。結果、風呂上がりの着替えは5分でできるようになったし、後輩に仕事を教えられるようにもなった。彼女のヘルパーを辞めて浜松に来た今でも、彼女との交流は続いている。今も昔も彼女とわたしは、利用者と介助者でもなく、雇用主と従業員でもなく、ただお互いに生身の人間として、向き合っているだけである。
あえて専門という言葉を借りて言うなら、わたしは一時期、自分が高橋舞さんの専門家であるように自負していたことがあった。ヘルパーとして髙橋舞さんと関わっていた頃、彼女がどうしてそうするのか、そうなったときにどうすればいいのか、手に取るように分かるし、できるという、たいへんおこがましい勘違いをしていた時期があった。たぶんそのとき、わたしは彼女と向き合っていたのではなく、わたしの心の空白を埋める存在として、彼女を見ていたのだと思う。久保田さんが、「自分が壮の面倒を見ていてつくづく、人間が人間の専門家になるべきではないと思った」と発言していたけれど、それはだから、専門牲ではなく、関係性の問題ではないだろうか。親子だから、色んなことが分かってしまうし、限定してしまう。わたしと高橋舞さんも同じである。お互いを自分のものみたいに思ってしまうから、苦しくなった。他人を自分のものにすることはできないのに、相手が家族だったり恋人だったりすると、相手を自分の思うようにしたいし、できると思ってしまう。
この日話されていた”専門性”は、「目の前のひと・モノ・コトと向き合った結果、あるいは向き合いたいために身につく技術や知識」「相手に対する優位性を持っているというエゴ」というふたつの意味があり、そのいずれも、簡単にいうとだから、人間が人間に向き合う、あなたがいてわたしがいる、ということに過ぎないのだけれど、福祉とかケアとかいう言葉の文脈でそれが話されることによって、「こんな自分と一緒にいてくれてありがとう」と誰かに言わせてしまう社会をつくりあげることに、わたしは今、加担しているのだと思った。
いったいどうしたら、言葉の意味から解き放たれて、わたしたちは純粋に目の前のものを見ることができるのだろうか。(塚本千花)