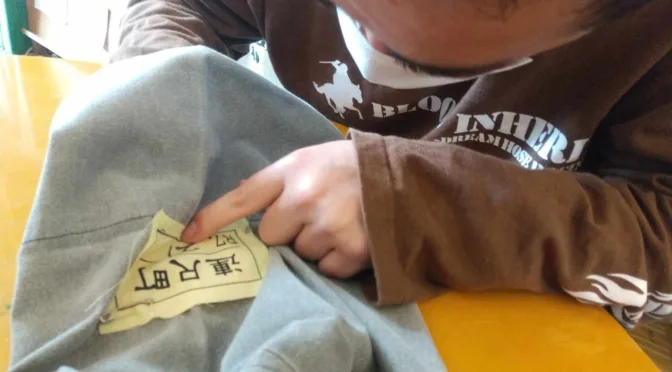![《寄稿》第2回 ゲスト:松村圭一郎さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/02/ca88dd965a4f1fa6304712816cf0524f-scaled.webp)
《寄稿》第2回 ゲスト:松村圭一郎さん [ひとインれじでんす2024]
生きのびるための<関係>の技法
文=松村圭一郎
「働く」がそぐわない場所で
2024年9月13日から14日にかけて、「ひとインれじでんす」の企画で、たけし文化センターに滞在した。簡単な説明が終わると、「あとはご自由に」という感じで放置される。とりあえず2階に上がって、しばらく様子をみていた。
DJブースのようなテーブルの前で音楽を流している人、それに合わせて身体を動かす人、ただ寝転がっている人、ずっと壁にテープを貼りつけている人……。誰もユニフォームを着ていないので、いったい誰がスタッフで利用者なのか、まったくわからない。
ところが2階の一角でミーティングがはじまると、雰囲気が一変する。そこに集まった人は、あきらかに「働いている」人にみえる。1週間後に予定されている「凸凹まつり」の準備のための話し合いだった。
ミーティングでは、名簿をつくる、時間を割りふる、分担を決める、連絡事項を確認するなど、あきらかに「会議」らしい言葉が飛び交う。周りでは、コウちゃんがサトちゃんにちょっかいを出すなど、いろんなことが起こりつづける。みんな真面目な顔で「会議」をする。その行為が、この場所ではあきらかに場違いな、異様なふるまいにみえてくるのが興味深い。まるで、そこだけ「仕事」という劇が演じられているかのよう。「働く」ことが、なぜかこの場にはそぐわないのだ。
1階に下りる。この日は、看護学校の学生が「実習」に来ていた。レッツには、リハビリとか、学習とか、みんなで一緒にやると定められたプログラムはない。実習生も、私と同じように放置されて、手持無沙汰にしている。ときどき利用者から話しかけられて話し相手をしたり、とくに反応もないまま自分から話しかけたりしている。なかには、机に向かって熱心にメモをとっている学生もいる。何を記録しているのかは、よくわからない。
はたして人と雑談することは「実習」なのか、この場の何がわかったら「学んだ」ことになるのか、本人たちも当惑している様子だった。その日を終えると、彼女たちは「実習レポート」を提出するのだという。いったい何が実習内容として「報告」されるのか、それをどういう基準で「評価」するのか、なかなかにシュールだ。

「福祉」とは何か?
レッツが開設している「アルス・ノヴァ」は「障害福祉サービス事業所」だ。たしかに、そこでは「福祉」という仕事が行われている。スタッフは給料をもらって働く従業員である。だが、なぜこうもこの場所は「仕事」から遠く離れてみえるのか。そこには、ただ時間をともに過ごし、生きている人たちがいるだけだからだ。障害があろうが、なかろうが、その場で一日を過ごす。そこにいるだけなのに、それが「仕事」になるのは、国の福祉政策というフレームがあるからにすぎない。
考えてみれば、私が研究してきたエチオピアの農村には、「福祉」という仕事は存在しなかった。もちろん子どもも、老人も、さまざまな「障害」をもつ人もいる。だが基本的には、施設に入ることなどないので、ただ村で生きている。お年寄りで足が不自由になれば、だんだん行動範囲が狭まり、家の周囲で用を足しに立つくらいしか、出歩かなくなる。家族などがその老人をサポートはしている。だが、とりたてて「介護」をしている様子ではない。人の手が必要な人に、近くにいる人が手を差し伸べる。それが大人だろうが、子どもだろうが、貧しい人だろうが、精神を病んでいようが、そこにあまり区別はない。それは「仕事」の範疇に入る行為ではないのだ。
「福祉」という領域は、人間が生きて老いて死んでいく道のりのなかの一部を「サービス」におきかえ、「仕事」にする仕組みだ。そこには、ケアする人がいて、ケアされる人がいる。だが、本来は、誰がケアされるべき人なのか、固定していない。手がかかる子どもが親になり、自分の子の面倒をみる立場になる。そして、やがて老いて人の手助けが必要になる。こうして一生のうちで、ケアする人とケアされる人の関係は、移り変わっていく。
それだけではない。たとえば「子育て」は、親から子への一方向的な行為ではない。親は最初から「親」ではなく、子どもとの関わりのなかで「親」になる。子は一方的に育てられる側ではなく、大人を「親」として育てる側にもいる。ケアされる側のある種の「欠如」や「不足」は、ケアする側の行為や能力を引き出す役割を担っている。はたして、どちらがケアしているのか、ケアされているのか、そもそもとてもあいまいなのだ。
その意味で、レッツで誰がスタッフで利用者なのか判然としないのは、自然なことのように思える。何かが起きれば、周りの人が手を差し伸べる。何も起きなければ、ただその場に一緒にいる。そこにスタッフと利用者の線引きはない。ただともに生きている人たちがいる。その様子を観察していると、レッツで「働く」人たちは、ふつうの企業の「労働」にはおさまらない人たちにみえてくる。利用者とスタッフの区別がつかないのは、ユニフォームを着ていないからだけではない。みんなそれぞれが自分の個性のまま、その場にいることを認められているからだ。だとしたら、この場所は「利用者」のためというよりも、特定の人たちが「社会人」として生きられる居場所だともいえる。ここでも、ケアの関係は固定していない。
スタッフ会議が終わり、2階から人が下りてくる。また、誰がスタッフで利用者なのか、よくわからなくなる。急にチハナさんがコウちゃんを誘って、外に出る。と、二人は大道路に向かって大きく身体を動かし、踊りはじめた。突然のことで、あっけにとられてしまった。だが、二人は踊り終わると、いつものことといった様子で、平然と戻ってくる。ここでの「仕事」は、これがふつうなのだ。スタッフが踊りというプログラムを利用者に提供しているわけではない。どちらかと言えば、踊りたくなったチハナさんがコウちゃんに付き添ってもらった、ともみえる場面だった。
帰りの時間が近づくと、みんな落ち着かない様子になる。帰り支度をはじめる人もいる。コウちゃんが、リュックを背負おうとするアキラくんの手助けをする。その横で、同じくリュックを背負ったサトウさんが、うろうろしている。そこにも固定的な境界はない。ただ、一日のうちのある時間をともに過ごす。目的と役割が明確に固定された「施設」とはかけはなれた場のあり方が、なによりも新鮮だった。

入れ替え可能な、でも固有な関係
レッツでお話を伺うなかで、いくつか印象に残った言葉がある。ひとつは、「スタッフと利用者の関係は入れ替え可能でなければならない」という言葉だ。この人の介助は私にしかできない。そんな固定した関係が生まれたら、それはケアを受ける側にとっても、大きな制約になる。その介助者がいなくなれば、生きていけなくなるからだ。介助者にとっても、24時間、気が休まらず、大きな負担になるだろう。だから、介助の関係は入れ替え可能でなければならない。
ただ、その一方で「介助のやり方は、人それぞれで固有なもの」という言葉も耳にした。たとえば、同じ利用者でも、トイレに付き添うときのやり方は、かならずしもスタッフ間で共有されていない。この人はいつもこうするものだ、と思っていたら、他のスタッフは別のやり方をしていた。そんなことがよくあるそうだ。つまり、利用者はこの人がトイレに付き添うときは、このやり方なのだな、とわかって対応を変えていることになる。そこには「この人と私」という固有な関係が築かれている。こうして利用者やスタッフは、それぞれに個性をもった固有な存在でありながらも、同時に入れ替え可能でもある。
タケシくんが、親元を離れてグループホームに入ることになった経緯も興味深い。生まれたときからタケシくんの面倒をみてきた母親のミドリさんにとって、その親子の関係は、まさに「入れ替え不可能」にみえていたはずだ。母親である自分以外の人がタケシくんの介助をすることも、タケシくんが他人の介助のもとで生きていくことも、可能だとは思えなかった。自分でもたいへんなのに他人に委ねるのは申し訳ないという気持ちもあった。
だがタケシくんは、母親に頼れないことがわかると、他の人の介助を積極的に受け入れはじめた。それは、あっけないほどの変化だったそうだ。親子は、きわめて固有な関係である。だが、永続的なものではない。家族も、固有でありながら入り替え可能な関係になる。それが、これからの「家族」のあり方を考えるときに重要に思える。
私がエチオピアで目にしてきた「家族」の関係は、とても柔軟だった。いつも一緒に過ごしているので、その家の子だと思っていたら、親戚の子だった、ということがよくある。基本的に、子どもはどこの家でご飯食べようが、遊ぼうが、寝ようがかまわない。親との関係が悪くなれば、子どもの側から親戚を頼ったりして、他の家庭で過ごすようになる。これはエチオピアに限らず、人類学が研究対象とする多くの社会で報告されてきたことだ。「家族」の関係は固有であっても、入り替え可能になっている。それは子どもに自由が認められているという以上に、互いを極限の状態に追い込まないための術でもある。
私がいなければ、この子は生きていけない。この親から見放されたら、自分は生きていけない。親も、子も、そう思えば思うほど、互いを強固な檻に閉じ込めてしまう。そんな「家族」の関係が、現代日本の親子を縛り、苦しめているように思える。「家族」だけではない。私が辞めたら会社に迷惑をかける、この会社をクビになったら私は生きていけない。この「働く」をめぐる閉塞した固定的な関係が「ブラック」な状況の背後にある。レッツで目にした関係のとり方には、「福祉」という領域にとどまらない、生きのびるための知恵がありそうだ。