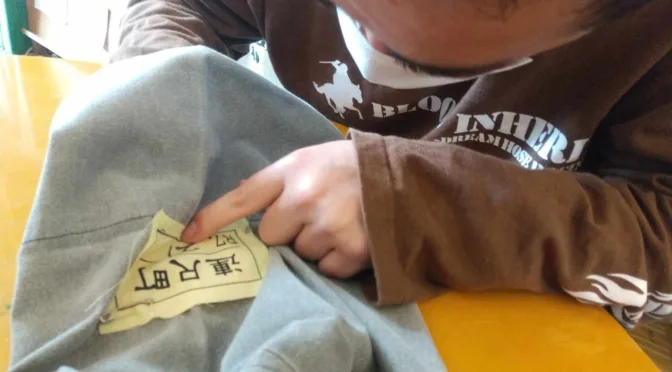![【スタッフ所感】第1回 ゲスト:岸井大輔さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/05/IMG_0734-scaled.webp)
【スタッフ所感】第1回 ゲスト:岸井大輔さん [ひとインれじでんす2024]
第1回 ゲスト:岸井大輔さん(劇作家)
塚本千花(認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ)
トーク当日は参加できなかったので、録音されたものを後から聞き、これを書いている。
六年前から、個人の活動のなかで、ひとり芝居をつくっている。戯曲を執筆し、演出を考え、俳優として舞台に立つ。これら一連の過程を経ることは、わたしにとって、自分と向き合うための行為であり、それは同時に他者と向き合うための行為だった。制作過程でも、上演当日のその瞬間にも、わたしは自分と、そして他者と向き合うことを余儀なくされる。(でも、それは特別なことではない。やり方が違うだけで、それはいつでも、誰しもがやっていることである。吸う。吐く。匂う。触る。聞く。視る。歩く。発声する……。)
昨年の十一月に、浜松の民家でひとり芝居の上演をした。アルス・ノヴァのメンバーたち数名が観に来てくれた。彼らは芝居の最中にずっと、喋ったり、近づいてきたり、入ってきたり、出て行ったり、好き勝手していた。わたしは彼らのリアクションを受けながら芝居を続けた。用意していた言葉(台詞)や身体(演技)は、彼らの反応を受けて自然に、そして必然的に、柔らかくなったり固くなったり、小さくなったり大きくなったり、速くなったり遅くなったり、きっとその瞬間そのかたちでしか出力できないかたちで出力された(観客に、静かに観てくださいね、と前置きすることはなんて馬鹿らしいのだろうと思った)。ダイアローグ(対話)ではなくモノローグ(ひとり語り)ばかりやってきたわたしは、その感覚を久しく忘れていた。彼らもわたしも、そこで起きている”今”に、お互いに反応していただけだった。わたしは自分の身体が熱を持つのを感じて、夢中で芝居を続けた。あとから思えば、それは音楽のようだった。
アルス・ノヴァの時間に、たけし文化センターの二階で突如始まるセッションを、いつも遠巻きに羨ましく聴いていた。楽器ができないわたしは、あの渦に飛び込む勇気が無かった(ここに来たばかりの頃、成り行きで巻き込まれたことはあるけれど、音楽なのかノイズなのか分からないその渦の中で、わたしは途方に暮れてしまった)。誰かの音に合わせようともせず、誰かの音から外れようともせず、弾いたり叫んだり叩いたり跳ねたり、自由に在れる彼らが、とても羨ましかった。十一月のひとり芝居を終えてから、わたしは時々、二階のセッションに混ざれるようになった。そのときその瞬間の自分に素直になる、という感覚が、なんとなく自分の内側で分かってきたからだと思う。自分に素直であるとき、きっと他者に対しても素直に在れている。
演劇やセッションが行われるとき、わたしたちが共有していたものは時間だった。今、このときに、あなたとわたしの間に生まれている間、その間(“関係”とも言えるのかもしれない)が成り立っている時間を、わたしたちは共有したと思う。岸井さんの言葉を使うなら、そこでは芝居や演奏という枠組みが「装置」として機能していたのだろう(トークでは、共有するためのモノや仕組みや環境を装置と呼び、それを検討することの意義について話されていた)。呼び方は何でもいいし、必要ならば装置は検討されるだろう。わたしには、その手前のこと……装置よりも共有よりも手前にあるもののことが、大切に思われた。装置を考えることは、「何かをしよう」とすることである。何かをしようとするとき、ひとは、あなたの心の中に生まれたはずの原初の震えを、無かったことにしてしまうのではないか? 裸のまま熱を持っているはずのかたちに、重くて分厚い服を幾重にも着せて、身動き取れなくさせてしまうのではないか?
どうして何かを「共有しよう」と思うのか。利用者さんの健康に関わる情報を共有するのは、かれの健やかな身体を維持するため(それが本当にかれの為になっているかはさておき)。フリースペースやシェアハウスで場を共有するのは、ひとりで負いきれない負担(例えば、寂しさとか、家賃とか)を分け合うため。恋人に自分の好きな本を贈るのは、”わたし”が”あなた”と同じ世界を見たいから。共有されているもの(装置)は、その裏側に、ひとつひとつ異なる背景を持っている。異なる背景から、異なる理由が生まれて、ひとは、ひとと「共有」をしようとする。それは本来、流れの中で生まれる行為であり、結果である。何かを起こそうとして起こるのではない。
どうして「何かをしよう」とするのか。何かをするために、何かをしようとしていることが、多すぎはしないか。ほんとうは、何もしなくていいのではないか。何かをしようとしなくても、”わたし”が、”あなた”に素直になって、――衣服を纏わず抱き合うように、ほんとうに素直になって、”今”に反応し続けていれば、そこには自ずと必要な装置が立ち現れるだろう。そして「行為」が、その瞬間そのかたちでしか出力され得ない 何か が自ずと出力されて、”わたし”と”あなた”の間に流れるだろう。わたしは、それを目撃できるのが演劇だと思っている。(塚本千花)
※当レポート執筆にあたり、友人の飛田ニケ氏による活動アーカイブ『むなしさのシェア』を参照させていただきました。