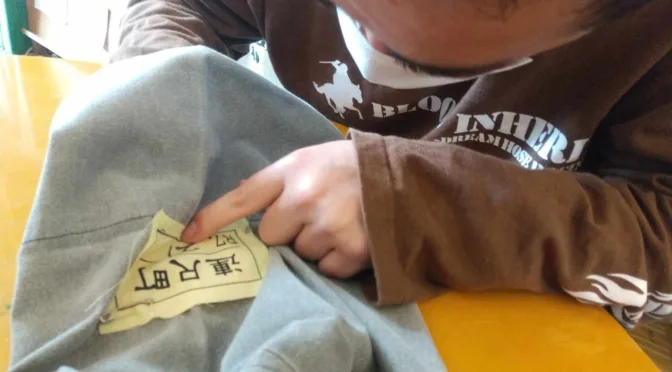![〈トークまとめ〉第8回 ゲスト:松尾亜紀子さん [ひとインれじでんす2024]](https://cslets.net/wp/wp-content/uploads/2025/03/d93fff8dade76cb43916b2dee52a41f4-scaled-1.webp)
〈トークまとめ〉第8回 ゲスト:松尾亜紀子さん [ひとインれじでんす2024]
◉イントロダクション
松宮
今日のテーマは「つなげる、ともに生きる」です。松尾亜紀子さんに、エトセトラブックスのお話しや滞在した感想をシェアしていただきたいと思います。
◉エトセトラブックスの紹介
松尾
エトセトラブックスは、東京の新代田駅の近く、閑静な住宅街の中にあります。お店を開く時に、駅から近い、路面店である、駅までの道が明るい、女性も入りやすい、というところを大事にしました。エトセトラブックスは、まだ伝えられていない女性の声、フェミニストの声を届ける出版社です。その声は無限にあって、フェミニズムの形も個人の数だけ無限にあります。
名前の由来
エトセトラブックスという名前は、ジュディス・バトラーという思想家の『ジェンダー・トラブル』という本の一文「無限のエトセトラ」から名付けました。有史以来、言葉は男性中心主義の中で作られてきて、「その他」とされてきた声を拾っていきたいという意味で、エトセトラ、つまり「その他」ブックスと名付けました。
独立の経緯
私は15年間、中規模の総合出版社で編集者として働いていました。
フェミニズムやジェンダーの本を作ってきて、その流れで独立して、2018年に出版社を立ち上げました。そしてその翌年5月にフェミニズム雑誌エトセトラを創刊(年に2回)しました。これまでに27冊の書籍、単行本15冊、エトセトラ12号まで出しています。
当初から本屋さんもやりたいと思って、準備を進めていました。フェミニズムの本を3000冊集め、販売しています。2021年オープン当時に日本でフェミニスト書店と名乗っているのは1軒だけでした。今はフェミニズムをメインとしている店が増えてきています。本屋は、店長の寺島さんやスタッフのほたてさんの3人で営んでいます。
◉松尾さんの生い立ち
生まれたのは九州の長崎です。三姉妹の長女です。幼い時から男尊女卑の空気に満ちていて、親族の集まりでは女性だけが台所で働いて、男性は同い年の小学生の従兄弟を含めて座って飲み食いで、それが普通だと思っていました。家では三つ指ついて父親を送り出していました。母も働いていたのに、母には三つ指ついて送り出すってことはなかったです。何事も父親に決定権があって、母親にあれこれ相談すると、「お父さんに言ってよ、お父さんが決めるから」と言われて。それも今思うと「はて?」なんですけど、その時は普通だと思っていて。小さい頃は成績がよくて「女の子なのによくできる、男の子に負けない女の子」と褒められていました。それが内面化されて、それが当たり前だと思っていたので違和感はなかったですし、むしろ名誉男性(男のようにふるまう少数の女)的な価値観を内面化して育ってきたと思います。私は普通の女の子とは違うんだと。
◉ジェンダーとの出会い
10代になって、性のことになると恋愛対象の男性に何も言えないというか、Noと言えなくなってきた自分がいて、おかしいぞって、なんかどんどん私は弱くなっているって違和感があったんです。そういう感じでもやもやしているときに、福岡の大学時代、たまたま上野千鶴子さんの社会学の本を手に取って、「ジェンダー」という概念に出会いました。
◉編集という仕事を通して出会った女性作家
「ジェンダー」とは、とても簡単にいうと「男だから」「女だから」というように、性別で決めつけられることです。言葉を知って、あれが差別だったんだとわかるようになって。本が大好きだったので、絶対編集者になるんだと目指して、編集の仕事を始めたんですが、初めの会社はブラックで蛸部屋のようなところで働いてました。河出書房新社に転職して、そこで学んだことが多かったです。本を作る過程で知ってきたことが私にとってのフェミニズムです。河出書房新社で、『世界文学全集(池澤夏樹責任編集)』という、20世紀以降の文学を集めるプロジェクトに参加したんです。全集を編むときに、その3倍くらい候補があって、100タイトルくらいを全て読んだんですよ。そこでものすごく多くのものを吸収した気がします。
出会った本
特に女性作家の本にすごく感銘を受けました。ジーン・リース『サルガッソーの広い海』(英)は、『ジェーン・エア』っていう広く知られた物語に、主人公のジェーンが恋に落ちるロチェスターっていう人物がいるんですけど、彼の悪い妻、当時の言い方で言うと「狂人」と表現されて閉じ込められている妻の立場から書いた物語なんです。なぜ彼女が生まれたカリブの島から連れて来られてこういう目にあっているのかっていう、彼女の事が語られる物語です。そして、クリスタ・ヴォルフ『カッサンドラ』(独)っていうのも有名な話なんですけど、アポロンに恋されて、それに応えなかったばかりに呪いをかけられた巫女の話なんです。自分が殺されることが彼女は予知できるんです。殺される前に彼女が自分を振り返る、これも一人称の物語です。こんなふうに、今までの物語を女性作家たちが書き換えてきたことを初めて知りました。
◉独立へと背中を押してくれた社会の動き
2010年代はSNSが発達して、そこで女性たちが内心を吐露するようになりました。自分が編集した本の感想が、SNSのなかでダイレクトに返ってくるようになったんです。母性神話をひっくり返す『ママだって、人間』(田房永子 著、河出書房新社)という本を出したときに、「3年ぶりにこのイベントのために、自分のために外出した」というお母さんがいたんです。まるで軟禁のようだと感じました。そういった読者とのやり取りの中で気づいたこと、育ってきたものがたくさんあります。
社会の流れを確認してみると、2017年に伊藤詩織さんが自身の性被害を告発しました。このとき、一介の編集者だった私は応援できなかったという悔いがものすごくあって、その後悔が原動力になりました。2017年、アメリカを中心に#Me Too運動が始まりました。その後、2018年にトランプ政権になって、大規模なウィメンズ・マーチが行われました。そして2018年7月、東京医科大で女性を一律減点する不正入試が発覚したんです。このニュースを聞いて、これは何かしなきゃいけないと、私は初めて友人たちとデモを主催しました。デモをしてみたら、想像よりはるかに多くの報道陣が来てくれました。そしたら土日の報道番組で、私が「ふざけんな」と叫んでいるのが放送されたんです。それを見た九州の親戚のおばちゃんたちから電話がいっぱいかかってきて、
「あんたなんしよっとね」と怒られると思って、怖くて最初は出なかったんです。でも「これはおかしい、よくやった」とおばちゃんたちが言ってくれたんですよ。塾の先生をやっていた一番怖いおばちゃんが、「ようやくあんたが言っていることがわかった」と言ってくれて、通じるんだなと思ったんです。それまで、たとえば本をつくっても営業部に「フェミニズム」って書いたら店頭で敬遠されちゃうよと言われていて、「フェミニズム」と帯に書くのもためらったりしてたんですが、やっぱりはっきり言わなきゃダメだなと思って、独立する時はフェミニズムを専門にしよう、と思いました。ちゃんと言えば通じるし、言わなきゃ通じないこともあるなと思ったんです。
◉フェミニズムマガジン エトセトラ
独立した最初から、雑誌は出したかったんです。雑誌は自分の出版活動の根幹になるだろうっていう予感があって。年に2回、毎回ゲスト編集者を招いて作りたいテーマを聴きながら一緒につくっています。その中に20から30人の執筆者がいるんですね。まさに「エトセトラ」を可視化するというか、フェミニズムには多様なテーマがあって、決して狭い概念ではないことを示したいと思いました。表紙のデザインは福岡南央子さんという方に信頼してお願いしています。店頭で表紙が並んだとき、もしくは電車の中で読んでる時にそのままプラカードになっているような感じを福岡さんがデザインしてくれました。
◉エトセトラブックショップについて
出版社だけでなく、書店も併設して、本同士の連帯を本棚で見せたかったんです。フェミニズムは強固な”絶対”があるように見えますけど、性差別を無くそうとそれぞれがもがく、その表現の仕方は多様なんです。一人一派と言われているくらい。古今東西の歴史のその連なりを本棚で見せたいと思いました。もう一つは、コロナ禍で、とくにケアワークを押し付けられた女性たちが家の中に閉じ込められて、居場所が早く必要だと実感したんですね。それで書店を作りたい思いはますます加速しました。あの、3年間軟禁されたお母さんが忘れられなくて。コロナ禍でも本屋はかろうじて売上も下がらないくらいで、本屋だったら案外行きやすかったのかもしれません。店長の寺島さんが一緒にやると決めてくれたことが大きいです。彼女は元々別の書店で店長をしていて、彼女の作るフェミニズムの棚に感動して一緒にやろうと誘いました。寺島さんが集めてくれた本がエトセトラの礎になっています。そして、もう一人のスタッフほたてさんがイベントやワークショップ、読書会などを担当してくれています。
◉影響を受けたフェミニスト書店
影響を受けた書店はいくつかあって、一つ目はイギリスのペルセポネブックスです。コロナ禍で残念ながらロンドンから引っ越してしまったんですが、半分出版社、半分書店の形態です。ここは絶版になった女性の本を復刊して販売しています。二つ目は女人書店です。台湾の有名なフェミニスト書店で、中は案外広くてセミナーとかもいっぱいやっているところです。日本には昔、京都にウィメンズブックストア松香堂(しょうかどう)という有名な書店があったんですが、2018年当時はフェミニスト書店と名乗っている店は日本になかったんです。だからこそ作ろうと思いました。今はフェミニズムをメインとしている店も増えてきています。
◉エトセトラブックスはどんな場所か
理想としては、本棚の前でたくさんのフェミニズムの言葉と向き合える場所であってほしいと思っています。フェミニストが本棚の前で、自分とは違うフェミニストに出会える場所だと思っていて。お客さんは、大学生から、ウーマンリブで活躍していた年配の女性までいます。お客さん同士の交流が結構自然に始まるんですよ。
もう一つ本屋を始めた目的は、いろんな人たちの集まれる場所になればいいなと思っていたんです。南米のアーティストが来てくれて、下着に主張(「私の体は私のもの」とか「指図するな」とか)を刺繍してそれを飾るという手芸の会をやったり、版画のワークショップや、いろんな展示、最近は、女性たちがつくった野菜の販売会もしています。そうすると、展示やワークショップに惹かれて来た人がついでに本も見てくれるんです。フェミニズムの本屋をやってますけど、場所もやっているという気持ちもあります。いろんな人が利用してくれているのが嬉しいです。
◉小山さんノートのこと
『小山さんノート』という本を去年出しました。小山さんというのは、公園のブルーテントに長く住んでいた女性ホームレスです。2013年に亡くなりました。小山さんノートワークショップというのは、小山さんが残した80冊のノートを文字起こししたグループです。全部手書きの、物凄く綺麗な文字のノートを8年間かけて全部テキスト化したんです。なんでそういうことができたかというと、公園に一緒に住んでいた人がいて、このノートを見ていいよ、と言われていたんですね。小山さんが亡くなった時、棺の中にノートを入れようとしたらしいんですけど、見てみると、直筆の物凄い筆致で大事なことが書かれているのを見つけたんです。小山さんと共生していた人たちやこのノートで小山さんを初めて知ったメンバーで週一回集まって、小山さんのことを語るというワークショップがはじまったんです。
小山さんノートとの出会いとその出版
2020年、東京の幡ヶ谷のバス停で女性ホームレスが撲殺されるという痛ましい事件が起こってしまって、彼女の一周忌スタンディングの時、小山さんノートワークショップの方も来ていて、ノートの一節を読み上げてくれたんです。私はびっくりして、読んだことがないものだなと思いました。ホームレスの日々が綴ってあって、自分の尊厳を守って自由になりたいということが書かれているんです。小山さんの生活は厳しく、食事も満足ではなかった。それでも、拾ったお金を持って、決まった喫茶店に通い、自分の想いを綴り、公園に帰る、というのを続けていた。ノートを世に出したいと小山さんは書いているんですね。誰かに読んでほしいという思いが確実にあった。
『小山さんノート』は非常に好評で、たくさんの方に読まれています。何かを学ぶということよりも、小山さんのことをみんなで一緒に知っていく。ワークショップの方たちは「小山さんが特別な存在じゃないということを知ってほしい。女性ホームレスというのは社会から見えづらい存在だけど、この社会にいて、共に生きているんだっていうことは知ってほしい」といつも言っています。
フェミニズムの出版社だから任せた
これを出せたのは私の中で大きなことだったんです。途中で私は珍しく弱気になって、フェミニスト出版社から出していいんですかね、小山さんの書いたことは、必ずしもフェミニズムとして読まれない方がいいかもしれない、と言ったらワークショップのひとりが、「何言ってんですか、私たちはこれをフェミニズムと思ってやってますよ」って言ってくれて。「私たちにとってはフェミニズムですよ」と。
ワークショップのメンバーの中にはいろんな人がいるんです。DV被害者の支援をやっている人、演劇をやっている人、一緒に公園に住んでいた人、引きこもりだった人とか、ルーツが韓国にある人とか。彼女たちのエッセイも本の中に収録されています。ワークショップのメンバーからは「フェミニズムの出版社だから任せたんですよ」と言っていただいたんです。フェミニズムとは一言も帯にうたっていないですし、考えずに読む人もいると思うんですけど、今まで聞かれていなかった女性の声を聞くことは、私にとって一番大事なフェミニズムです。「フェミニズム」とはっきり言わなければ届かないことは、雑誌エトセトラで言っています。この間、執筆者のひとりが言ってくれたのは、他の媒体では書けないことがこの雑誌では書けると。普段はマジョリティ男性にもわかるような言葉で書かなきゃいけないみたいな自己規制がはたらく、でもエトセトラでは自由に書けると言ってくださったんです。出版という活動においても、自分の思ったことを自分のまま言えるような場所を作っていけたらいいなと思っている。
◉レッツ滞在の感想
まず、居心地が良くて、びっくりしました。緊張しながら来たんですよ。福祉とかアートとか、障害者のための活動とか、そういう方面は不勉強で知らないことばかりだったので、私でいいのかなというのがありました。依頼がきたとき、重度の障害があり、自立生活センターを営んでいるフェミニストの知人に相談したら、「呼んでくれた人たちのためにはならないかもしれないけど、あなたのためにはなるよ」と背中を押してくれたんです。
◉爆音まで居心地がいい
昨日一日滞在して、実家みたいな居心地の良さがありました。なんとなく馴染んでいって、お昼ご飯を食べたら眠たくなったんです。2階にいいスペースがあって、利用者の方が寝てたんですよ。私もなんでもしていいと言われていたから寝てみたら熟睡しちゃって、利用者さんとお散歩に行く時間になるまで寝ていました。九州の実家では親族がたくさんいて、大人たちは宴会して子供たちは走り回って、ワイワイガヤガヤしていた記憶があるんです。うるさいんだけど居心地が良くて守られている感じ、なぜかその中ってぐっすり眠れていたなと。2階は爆音なんですよね。ボリューミーな音楽が流れているんです。私は普段は音楽があまり得意ではないんですけど、なんか爆音まで居心地が良かったんです。散歩はすごく楽しかった。
◉安心感のある場所
障害者の方たちが住んでいるシェアハウスに泊まって、住んでいる方の叫び声で2回くらい起きましたけど、ほぼ朝までぐっすり熟睡しました。私には小一の娘がいて、家でも2段ベッドで寝ているんです。家だと上からいつも娘に起こされるんです。それに比べたら、こたつもあるしのびのびできました。うちの店もみんなから居心地がいいと言ってもらえるんです。多分、ここにくれば否定されないみたいな、ここならフェミニズムの話をしてもいいっていう安心感があるんじゃないかと思います。レッツさんにもそういうところがあるのかな、スタッフの人たちがそういう空気を作っているのかなって思いました。場所ってやはり大事だなと感じた。
◉新しい拠点の構想
実は長崎に祖母がいて、102歳で去年大往生したんです。戦後、土地を開墾して、20人くらい住める広い家を建てて住んでいました。そこが空いてしまったので、もう1箇所拠点を作って長崎と東京を行ったり来たりしたいなと思っています。今はどんどん政治が窮屈になっていると思っていて、政府も行政も「少子化対策」とつければなんでも言えると思っていると思うんですよ。私の体は私のものだし、産む機械じゃないというのはフェミニズムがずっと言ってきた事なんです。ところが今、特に地方で、少子化対策という言葉で産めよ増やせよと言われている。地方にいないと見えないこともある。祖母の家は山の中にあるからシェルターになるかわからないけれども、ここにいたいなと思う人たちがいれる場所を作りたいと思っています。本棚を置いて、本が作れればいいなと。私がやっていることは、自分が本を作る理想の場所を作っているだけであって、自分がここにいたいなという場所で本を作っていたいと思っています。その過程でレッツにも呼んでもらえて。浜松でみなさんどんなことをやっているのか見させてもらって、代表にお金のこととかも聞いて、来られてすごくよかったです。
松宮
先々週にエトセトラブックスに僕も行かせてもらって、居心地の良さを僕も感じました。普通の大型書店に並んでいないような、松尾さんと作家さんとの繋がりがあるからこそ置いているようなZINEとかいろんなものが置かれていて、エトセトラブックスだからこその店内なんだなと思いました。
<対話>
◉生きづらさについて
会場から
自分は生きづらさをテーマにしていて、自分は発達障害を持っています。ASDは構造化という言葉が使われるんです、それって多様化と逆の方向で、生きやすさってどっちにあるんだろうというのをお話を聞きながら考えていました。
松尾
生きやすさっていうけど、みんな別に生きやすくないですよね。もちろん楽しいことや、やりたいことがある人はいるんだけど、むしろ「生きやすさ」みたいなものがどっかにあるって思わされていることが問題で、自分と他人の生きづらさを認めることの方が大事かなと思っています。でないといつまでも「生きやすさ」を前にぶら下げられて、お金を稼がなきゃならないとか、男らしくしなきゃいけないとか女らしくしなきゃいけないとか、痩せなきゃいけないとかに縛られてしまう。それで、他人の生きづらさを大事にできなくなってしまう。小山さんノートにしても、小山さんは生きやすくはなかったけど、自分の尊厳だけは大事にしていた。そういうことをみんなで考えるタイミングにきているのかなと思います。
◉男性にノーが言えないことをどうやって解消したか
会場から
男の人と付き合った時うまくものが言えないというお話がありましたけど、それはどうやって解消したんですか?
松尾
やっぱり自分と同じような想い、Noを言えないことで苦しんでいる人がたくさんいると知った時に前に進めた気がします。
会場から
私も若い頃、うまくいかないなってことがあって、私と同じ想いをしている人がいるっていうことを学んだ時が乗り越えられた時でした。
松尾
Noと言っていいということをフェミニズムや性暴力の問題を知る中で学びました。あの頃、もっと自分のNoを大事にできていればよかった。そうすれば同意していない性行為があったときに、自分から進んでその行為をしたんだって思い込まなくてもよかった。私は性暴力に反対する活動もしているのですが、10代の頃の自分に向けてやっている部分もあります。
会場から
学ぶことによって解放される面があって、自分にも小5の娘がいるんですけど、より自由にこれから先の人生を歩んで欲しいので、同じように思うんです。ジェンダーに関することだけじゃないけど、学校のこととか、世の中の不条理とか感じたタイミングで色々話し合うようにしています。
◉もやもやの表明
会場から
飲食店で働いていて、オーナーと僕で話す機会がありました。その際に、オーナーが言うには、30代から40代の女性は採用しにくいという話があったんです。ライフステージでやめてしまうから雇いにくい。「どう思う?」ってオーナーに聞かれた時に、答えたくもなかった。どうやってオーナーに言葉を伝えればいいのでしょうか?
松尾
それをやらないと差別だ、採用して当たり前だ! とか言ったらそのおじさん(オーナー)もついてけないと思うけど、むずかしくてもやらなきゃいけないんですよとは言いたいですよね。でも、なかなか一対一じゃ言いづらいのもわかります。だけど、その身近な対話こそが、性差別をなくす一歩なんですよね。これ、よくジェンダーをテーマに講演会とかしている友人が言ってたんですけど、そういう時は、名のある人がこう言ってた、というとおじさんは聞いてくれやすいそうです(笑)。頭ごなしにいうんじゃなくてその人に響くような言葉を言った方がいいから、男性の権威ある学者とかが言っていたいい感じのことを探して、っそれで伝えてみるとか。
◉バイアスを超えて、どう広めていくか
会場から
自分がいじめられたり差別される側だったので、自分を肯定するために差別する状況が生まれてきたと思っています。フェミニズムも思い込みやバイアスがあるから、広めていくときにどうやっていったらいいですか?
松尾
楽しくやることを一つの目標にしています。楽しさを見せつけるというか、隠さないです。エトセトラブックスは大きな店でもないし、個性的な人たちが集まっている感じです。それなりに楽しくやってますと言うようにしています。それを見て、楽しそうだなって誰かが思うかもしれないので。
松宮
雑誌エトセトラは見た目がポップで、手に取りやすいと思います。ビジュアル含め、フェミニズムを広めようとしているんだなと思いました。
◉エトセトラVol. 3について
夏目
エトセトラブックスを始めてから、結構年数が経っていると思うんですが、今フェミニズム界隈、女性をめぐる社会はどんなふうに見えていますか?
松尾
2020年コロナ禍入りかけの時、身体をテーマに特集をやりたいと思ったんです。「私による私のための身体」はフェミニズムも障害者運動も言ってきたこと。自分ですら自分の体を思い通りにできないのに、国とか強いものに自分の体をコントロールされてたまるか。身体についての1300人のアンケートを長田杏奈さんと取って、その回答をみんなで読もうという企画をしました。そこから5年経って、状況はよくなるどころか、先日(2024年11月)バックラッシュですよね、ある政治家の発言、「30歳を超えて出産していない女性は子宮を取ってしまえばいい」というものがありましたね。トランプの第二次政権が決まって、アメリカでは昔からフェミニストが言ってきたスローガン「My body my choice」ではなくて、「Your body my choice」というタームが広がりました。つまり、「お前の体は俺のもの。」トランスジェンダーへの差別も激化している。これはいかんと思って、「私の体は私のもの」というトークイベントをやったら、500人以上申し込みがあったんです。私の体は私のものってもう一回強く言わなきゃならないタイミングだったんですね。申し込みには地方在住者が多かったです。地方にいると「少子化」と言われて、求められる圧力が強い、でも地方にいればいるほど同じ思いの人とつながれない。よりリアルにつながりたい時はどうしたらいいかしらと聞かれます。
◉今雑誌を作るならどんなテーマで
今だったらどういうテーマで作りますかという問いに対して、もう一回これ(身体)作らなきゃいけないなという想いが強いです。
お笑い芸人が自分たちの会合で女性に性加害したとされる問題も、彼がどうではなくて、女性をブスって罵ったり、セクハラして笑ったり、そういう暴力的な「お笑い」を、それを見て喜ぶ視聴者を含めてみんなで作ってきたでしょうと。お笑い番組と現実は地続きですから彼がそういう場所で性暴力をしたってそれ自体は起こりうることだろうと思う。一人の悪者がいるんじゃなくて、みんなで作ってきたじゃん。これはお笑いだからって子供たちと笑ってたわけじゃないですか。そういうのそろそろやめましょうって言っていかなきゃいけないと思います。
◉草の根でフェミニズムを始めるには
会場から
男の人が下駄履いてるとやっと言えるようになったと思っていて、女の人は裸足かというとむしろ纏足だなと思っています。フェミニズム界隈が良い方に変わってきているなっていうのはすごく感じていて。一方で、断絶というか、言っている人たちとそうでない人たちの線があるなとも感じています。浜松で、松尾さんの話を聞こうとしている人たちがいるということに勇気づけられます。どこから始めたらいいのかな、っていうのをすごく感じていて、草の根的なものの始め方を知りたいと思っています。
本でつながる
松尾
私が始めた頃よりは、フェミニズム、フェミニストというワードを口に出す人は断然増えました。8年前よりはふつうに言い合える状況だと思っています。実際地方でどうやって繋がれるかをよく聞かれるんですよ。ひとつは読書会ですね。読書会は初めてみる活動としてはハードルが高いようで低い。フェミニズムとは書いてなくても、誰かと語り合いたい本で、誰かと集まって読んでみるとか。あとは、ZINEを自分で書いてみるとかもひとつあります。
自由なかたちでデモに参加する
あとはデモですね。デモを主催する時に、デモじゃないけど本屋さんで長田さんの本を読み合うとか、連動してくれる方がたくさんいて、1人でデモに立つのはハードルが高すぎるかもしれないけれど、地方でも自由な形で広がればいいなと思って始めたんです。自由にやってもらいたいと広く言っています。東京のデモをきっかけに、浜松でもやっていますと言えるし、意志を同じくする人が来るかもしれない。意外と楽しそうにやっているとアンチも来ないです。
過去からの蓄積とつながる
あとは、見えてないだけで、地域には昔から活動している先輩たちがいて、地方の男女共同参画センターにいけば、その方たちの蓄積があります。蓄積を溜めてる方たちに繋がるのも大事なことです。
久保田
レッツは24年間やっているが、浜松にはそういう活動をしてきた人たちがたくさんいると思います。
語り合える場に行ってみる
久保田
障害など一度辛い目にあった人たちがもう一回再生していくという部分では、昔の社会の障壁にぶつかるんです。それをどうやって壊すかではなくて、こういうふうに苦しんでいるとか、なんなんだろうと語り合う場所がたくさんあります。レッツもそういう場を作っているし、いろんなNPOも作っています。福祉施設も人権の問題は非常に重くのしかかってくるから、そういうことで考えている人たちもいます。浜松はそんなに捨てたものでもないですよ。人口が多いだけに、どうしても声が大きいマッチョな人たちに覆われちゃうけど、私たちも生存しているし、ぜひうちなんかに遊びに来てくれればなと。やっぱり松尾さん言ったように、1人2人から始める。フェミニストという言葉を使うのがいいかどうかわからないんですけど、自分のことに寄せて話すということを始めてみるとか。面と向かって話すのはとってもいいと思います。
松尾
小山さんノートの読書会どなたかやってくださっているんですけど、体のことを話そうとか、戦争について話そうとか、そういう話す場を作ってみるのはいいですね。フェミニズムっていう看板かけてなくても、社会運動している人たちのところに行ってみるとか。この場所にも何人かいますよね。フェミニストって言っていなくても、その思いを持った人たちはいますので、探してみてください。
高木
私は強気なのに気弱なので、フェミニストとも名乗れずにいたんですけど、研究会をやって、ベルフックスをみんなで読む会をやったんです。すごい怖かったけど、いろんな人が来てくれて、人権のこととか言うのびびってたけど、朝鮮人虐殺の読書会やったり、少しずつでもやると仲間が見つかったりします。最終的には仲間がいなくたって自分のできることをその場でやるんだ、と言う強い気持ちはまだ持てないんですけど。政治的な手芸の部活も企画してたりします。ぜひ一緒にやりましょう。
◉フェミニズムと男性の関わり
会場から
政治的な手芸の文脈の中で、フェミニズムって、男性の立ち位置ってどうでしょう?集まりの中で、男性も手芸しても良い?男性の関わり方ってどんなふうにしたら良いんでしょう?ローカルな話と、エトセトラでやる話と、お聞かせいただけたらと思います。
高木
前に研究会やった時とかルッキズムのZINEとか作った時とか、男性も来てくれたんですけど、男性が責められている気がしたりとかして、難しいなと思いました。
男性同士でお茶をしてほしい
松尾
誤解を恐れずに言うと、私はまず男性同士お茶をすることから始めてほしいなと思っています。男性どうしお茶を飲んだりしたことありますか?男性同士お酒を挟まず、話し合うっていう方が大事だと思うんですよね。女性と話す前に、男性同士で話してよって思うことはあります。
ベルフックスの「フェミニズムはみんなのもの」
松尾
もちろん、ベルフックスも言っている通りフェミニズムはみんなのもの。ただ、黒人の理論家である彼女が言っているのは、それまでのフェミニズムはホワイトフェミニズムだと批判しているんです。それまでのフェミニズムは中産階級の白人のもの、そこに自分達は入っているのか、と批判している、抵抗の言葉なんです。最初からみんなのものなんですと男性が言うのとは全然違うんです。黒人の女性が言ったって言うことに意義がある。もちろん開かれている場所にするのは大事なんですけど、成り立ちが違うんです。
エトセトラにきたある男性
松尾
エトセトラブックスにも男性が来ます。ウエルカムです。この前来た男性は、自分は介護の仕事をしていて、社会的には意識のある方だと思っていたが、婚約者がフェミニズムに目覚めて、それこそあなたは下駄を履いてきたでしょと、私は結婚制度に反対すると言って婚約破棄されたそうなんです。自分がまさか生きているだけで誰かを踏みつけているなんて思ってもいなかった。どうしたらいいですか、と。フェミニズムについて全部知りたいですと話にきたんです。全部は無理ですよと答えました。よくよく話を聞くと、結婚制度のことと、男性がなぜ加害者だと言われるのかということを自分に引きつけて考えたいということを話してくれました。そういう切実なことを腹を割って話す体験が男性同士では少なすぎると思います。
安心安全な場所の大切さ
会場から
私たちが住んでいるのは、昔ながらのコミュニティの力が残っているところなんです。中山間地に行くと、人口減少で、男性だから女性だからと言っている場合ではなく、もう残っている人たちでそこの地域を守っていかなきゃならない状況なんです。まずは男どうしで腹を割って話し合うみたいな状況じゃ無くなってきているのかなと思います。だから女性も男性も関係なくウェルカムで受け入れちゃった方がいいのかなと思います。
松尾
一概には言えないですけど、場所の安心性だったり、ルールのわかっていない人が入ってきた時に、せっかくそこで紡がれようとしたことが、話せなくなってしまうことがあります。安心安全な場所が大切だということがわかった上で、きてくれるのはいいと思います。
会場から
松尾さんは、おばあさんの家は、居心地がいいと思っていたと言っていましたよね。そこには、男性もいたはず。
松尾
犬も鳥もいました。
会場から
楽しそうに女の人だけで手芸をしながら、腹を割ってフェミニズムについて話してみたいと思ってやっていると思うんです。女同士で集まるからこそ話せる場もあると思っていて、男性がその集まりに入るか入れるかではなくて、自分で集まりを作ってみた方がいいと思います。
松尾
おばあちゃんちが楽しかったのは、女は台所、男は居間、の台所の方がすごく楽しかったからです。文句を言いながらも料理を作る。男も女もいたから楽しいでしょ、というのはちょっと乱暴かなと思います。記憶は細部の積み重ねなので、男性はいばっていて嫌だったけど、女たちでワイワイしていた時間も否定できない、それが大きいですね。
会場から
名誉男性という言葉があるように、女性だけの集まりに、名誉女性という人がきた時に、ああ、となると思うんですよね。
松尾
エトセトラブックスは私たち3人だけでやっていて、その楽しい場所を大切にしているんですね。そうするとこうやってこの浜松のレッツみたいな違う場所とも繋がれます。
(松尾補足:「男も女も関係なく」については、どちらの性にも決定権があり、同意が大事にされる関係があってはじめて語れることなのかなと思いました)